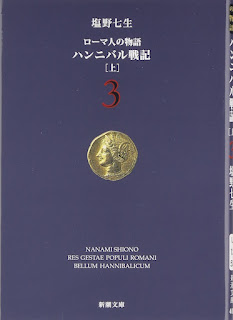ローマ人の物語〈10〉ユリウス・カエサル ルビコン以前(下)
「ローマ人の物語」では、全8年にも及ぶガリア戦役を詳細に追ってゆきます。
本書では1年ごとのカエサル軍の進路を地図上で示してくれるため、読者が戦役の遷移をイメージし易いように配慮されています。
本作品全体にも言えることですが、図解によって読者の理解を助けてくれる点は大変優れている点です。
カエサル軍の戦闘の模様や進路、そして戦略に至るまでを詳細に紹介できるのは、何と言ってもカエサル自身が執筆した「ガリア戦記」が役に立っています。
キケロをはじめとした当時の知識人、そして近代の評論家に至るまで、「ガリア戦記」の簡潔で要点をまとめた装飾のない文章を絶賛しています。
「ガリア戦記」は本国(ローマ)の元老院への現地報告書として、また当時のローマ市民たちの間でもベストセラーとなったようで、遠く離れたガリアの地で活躍するカエサルの宣伝としても役に立ったのです。
「ガリア戦記」は現代でも岩波文庫などで手軽に入手することが出来るため、いつか本ブログで紹介したいと思います。
ところでカエサルの指導するガリア戦役は、5年目まで破竹の快進撃を見せますが、6年目にして変化が訪れます。
まずオリエントのパルティア王国へ攻め入ったクラッススが戦死するという事態が発生し、三頭政治の一角が崩れます。
これを機会に主導権を奪われて久しい元老院が、ポンペイウスをカエサルから離反させ自陣へ引きこもうという動きが活発になります。
またガリア戦役の7年目にして、今までカエサルが平定した地域においてガリア人たちが一斉蜂起するのです。
この一斉蜂起は部族間で共闘することの苦手なガリア人をはじめて1つにまとめることに成功したウェルティンジェトリクスが中心になっています。
つまりガリア人の中で唯一カエサルに対抗できるリーダーが登場し、この蜂起の鎮圧に失敗すると6年間に渡るガリア平定が"無に帰す"どころか、彼の政治生命さえ失われてしまう危機を迎えるのです。
ガリア人との決戦の地となったアレシア攻防戦では、5万のカエサル(ローマ)軍に対し、35万ものガリア兵が対峙することになるのです。
やはりリーダーとしての真価を問われるのは順風満帆に事が進んでいる時ではなく、絶体絶命の危機の時ではないでしょうか。
そしてローマ史最大の英雄であるカエサルは、圧倒的に逆境に強いリーダだったのです。
ガリア戦役でも、その後のローマの内戦でも敵より少ない軍勢で戦う機会の多かったカエサルでしたが、限られた条件の中で優先順位を見失わない冷静さと知性、そして迷いのない決断力と大胆な行動力をカエサルは備えていました。
つまりピンチの時でも配下の兵士たちの目には、"つねに揺るぎない絶対の自信を持った最高指揮官"と写っていたに違いなく、いつも最後にはカエサル軍が勝利し続けてきたのです。
それは決して若さから来る勇猛や、一か八かの賭けとは明らかに違うものです。
8年間におよぶ戦役でガリアを平定して自らの地盤を築き上げたカエサルは、もう1人の実力者であるポンペイウス、そして何よりも彼の後ろにいる元老院との和解が成立しないと判断した時から、ローマを二分する内乱を戦う決意を固めます。
それがかの有名なルビコン川のエピソードとなり、43巻にもおよぶ「ローマ人の物語」のクライマックスの1つとなるのです。
ルビコン川の岸に立ったカエサルは、それをすぐには渡ろうとしなかった。しばらくの間、無言で川岸に立ちつくしていた。従う第十三軍団の兵士たちも、無言で彼らの最高司令官の背を見つめる。
ようやく振り返ったカエサルは、近くに控える幕僚たちに言った。
「ここを越えれば、人間世界の悲惨。越えなければ、わが破滅」
そしてすぐ、自分を見つめる兵士たちに向い、迷いを振り切るかのように大声で叫んだ。
「進もう、神々の待つところへ、われわれを侮辱した敵の待つところへ、賽は投げられた!」
兵士たちも、いっせいの雄叫びで応じた。そして、先頭で馬を駆るカエサルにつづいて、一団となってルビコンを渡った。紀元前四十九年一月十二日、カエサル、五十歳と六ヶ月の朝であった。
ローマ人の物語〈9〉ユリウス・カエサル ルビコン以前(中)
40歳にして共和政ローマの表舞台にデビューしたユリウス・カエサル。
以前紹介したようにポンペイウスとは対照的に"大器晩成型"のカエサルでしたが、政界の中心にデビューして以降、常に息をつく間もない忙しさになります。
ポンペイウスを筆頭とした元老院派(スッラ派)が優勢の中にあって、反スッラ派の民衆派としての旗色を鮮明に打ち出し、執政官に就任して以降、政策や法律を次々と打ち出します。
これはスッラによって親族を処刑をされ、自らもスッラのブラックリストに乗りかけた経験があることも関係していると思いますが、何よりも行き詰まった共和政ローマの"政体"そのものを打倒する大きな野望を胸に秘めていたからに他ありません。
カエサルは軍の総指揮官としだけはでなく、その政治的な手法も一流でした。
強力なバックボーンを持たないカエサルは、強い政治的信条を持たず"虚栄心"の強いポンペイウスを自陣に引き込み、莫大な資産を持ったクラッススさえも同志に仕立てます。
これが有名な共和政ローマの「三頭政治」ですが、この体制はもっとも力を持たないが、もっとも創造力のあったカエサルを中心に回ってゆきます。
政治の中心地であるローマで後顧の憂いを断ったカエサルは、ガリア属州総督を経て、いよいよ自身による「ガリア戦記」で有名な、8年にも及ぶガリア戦役に突入してゆきます。
絶え間ない部族ごとの抗争、そしてライン川以東のゲルマン人の脅威により1つにまとまることのなかったガリア(ケルト)人の住む地域は、ローマへの侵攻を防ぐといった国家防衛上の観点からも平定することの望ましい地域でしたが、何よりもカエサルの目には、自らの地盤を確立できる未開のフロンティアに写ったに違いありません。
当時は生きながらにして若い頃の軍功により軍神のように崇められていたポンペイウスがいましたが、カエサルはこのガリア戦役によって、初めて武将としての才能を世の中に知らしめるのです。
ライン河を渡りガリア人の領地のみならず、ゲルマン人の領土にまで攻め入り、またドーバー海峡を渡りブルタニア(イギリス)にまで攻め入ったりと、カエサルとその軍は縦横無尽、神出鬼没であり、またたく間にガリア人の領土をローマの支配下に組み込んでいきます。
またローマ軍が軍事活動を停止する冬営地の間にはイタリア半島へ舞い戻り、精力的に政治工作や公共事業に取り組みます。
本巻で触れられているガリア戦役最初の5年間は、三頭政治が完全に機能して政治的な立場が安定し、ガリア人の平定も順調であったため、軍人としても政治家としてもユリウス・カエサルは日の昇る勢いで躍進してゆくのです。
ローマ人の物語〈8〉ユリウス・カエサル ルビコン以前(上)
文庫版「ローマ人の物語」は全43巻にも及ぶ長編大作ですが、のちに広大な版図を持つことになるローマ帝国1000年の歴史をひと通り網羅するのであれば、それが必要不可欠な分量になるということは納得できます。
その1000年以上に及ぶローマの歴史には数々の英雄が現れますが、「ローマ人の物語」ではユリウス・カエサル1人のために43巻中6巻もの分量を割り当ています。つまりローマ史においてカエサルには、それだけの価値と魅力があるのです。
本書ではカエサルの幼年期から追っていきますが、カエサルの6歳年上のポンペイウスが20代の頃より活躍した"早熟の天才"なのと対照的に、カエサルは40歳にしてようやく頭角を現す"大器晩成型"の人物といえるでしょう。
よってカエサルの幼年期や少年期にそれほど特筆すべきことはありませんが、その紹介の過程で古代ローマの一戸建ての間取り、教育、そして服装に至るまで、当時のローマの日常が紙面を割いて詳細に紹介されています。
我々日本人は中世や江戸時代の暮らしであれば歴史資料館で学ぶことができますが、本書には、こうした日本人にとって馴染みの少ない古代ローマの暮らしを紹介することで、作品の内容がより身近に感じられるよう配慮されています。
カエサルの幼年期から青年期の前半にかけては、マリウス、スッラが相次いで台頭した時代と重なります。
また青年期の後期は、ポンペイウスがスッラの後継者という形で絶頂期を迎えています。
その中でカエサルは、女性と借金についてのみ派手なエピソードで知られていました。
特にカエサルの借金については、30歳にして1300タレントという数字に登り、これは11万人以上の兵士を1年間まるまる雇える金額であったというから驚きです。
実績はともかく当時のカエサルが並大抵の人物でなかったのが分かるのは、この膨大な借金を抱えても平然としていたばかりか、更に借金を重ねるという行動に出たことです。
それほど名門でも裕福でもない家庭に育ったカエサルでしたが、金の使い方については大金持ちに生まれたクラッススやポンペイウス以上に心得ていたようです。
たとえばカエサルの借金の仕方として、次のような後年のエピソードがあります。
そこでカエサルは、大隊長や百人隊長たちから金を借り、それを兵士たち全員にボーナスとして与えた。これは、一石二鳥の効果をもたらした。指揮官たちは自分の金が無に帰さないためにもよく働いたし、総司令官の気前の良さに感激した兵士たちは、全精神を投入して敢闘したからである
また数多くいた愛人たちへ対しても高価なプレゼントを惜しまなかったということで知られています。
ともかく30代後半にしてカエサルは最高神祇官に就任し、ようやく人並みの出世をはじめたカエサルは、少しずつ反元老院(反スッラ派)の旗色を鮮明にし、はじめて政治的な主張を前面に押し出し始めるのです。
ローマ人の物語 (7) ― 勝者の混迷(下)
共和政ローマのシステムが行き詰まりを見せる中、マリウスとスッラという優れたリーダーが現れます。
仮にリーダーが1人であれば、そのリーダーの元に混乱が収拾してゆきますが、2人のリーダーが同時に現れる時に衝突を避けられないのが人間社会の性なのかも知れません。
しかも民衆派のマリウスとは違い、スッラは元老院派と考えられていた人物でした。
結果的にローマへ平和は訪れず、マリウスとスッラの争いにより元老議員や執政官までもが殺害されるという事態にまで発展します。
ポエニ戦争最大の英雄であるスキピオ・アフリカヌスでさえ、元老院に矛先を向けるという行為は考えられず、むしろ元老院によってスキピオが失脚させられた事実を考えると、確実に時代が変わろうとしているのです。
マウリスを中心をした活躍で外敵の脅威を追い払い、またポントス王ミトリダテスを屈服させたスッラにより共和政ローマの覇権はさらなる広がりを見せるのです。
高齢のマリウスが亡くなり、やがて「味方にとっては、スッラ以上に良きことをした者はなく、敵にとっては、スッラ以上に悪しきことをした者はなし」と墓碑に刻ませたほどの勢力を持ったスッラが亡くなると、スッラ配下の若き武将たちが後を継いで活躍を始めます。
それがポンペイウスとクラッススです。
ポンペイウスはスペインで起こったスッラ体制への反乱「セルトリウス戦役」の鎮圧を、クラッススは奴隷や剣闘士たちの反乱「スパルタクスの反乱」の鎮圧によって共和政ローマの危機を救うのです。
理想国家の実現という崇高な理念を持たなかったスッラと同じく、やはり彼らも自らの野望に忠実であり、引き続き共和政ローマ末期には"個人の台頭"が続くのです。
優れた軍事的才能と市民から絶大な人気を得たポンペイウスと、ローマ一の大金持ちであるクラッスス。
この2人が図抜けた形で共和政ローマを牽引することになりますが、マリウスとスッラの時代と決定的に違うのは以下の2点です。
- ポンペイウスとクラッススはいずれもスッラ幕下の出身であり、敵対する関係ではなかった。
- 2人を比べた時、明らかにポンペイウスの実力がクラッススを上回っていた。
地中海の海賊討伐、そしてスッラの死後に再び反乱を起こしたポントス王ミトリダテスを完膚なきまでに粉砕したポンペイウスは、ローマ市民から絶対的な支持を得ることになります。
クラッスス自身もNo2の地位を受け入れている以上、ポンペイウスを中心に時代が動き続けることが確実と思われていましたが、結果的にはそうはならなかったのです。
なぜなら同時代に「ローマが生んだ唯一の創造的天才」と評されたユリウス・カエサルが同時代にいたからです。
ローマ人の物語 (6) ― 勝者の混迷(上)
ローマがイタリア半島を統一するのに実に500年もの年月を費やしました。
一方でローマがスペインからギリシア、マケドニア、小アジア、アフリカの北海岸と地中海の島々、つまり地中海世界を制圧するまでに130年しか要していません。
その要因はローマ人たちがはじめて外界に出て戦った相手が、当時の地中海最強の国"カルタゴ"だったということに尽きます。
規模はまったく違いますが、たとえば織田信長が"海道一の弓取り"と言われた今川義元を討ち取って以降、急激に勢力を広げた例に似ています。
共和政ローマは元老院を中心とした少数指導制によって国家を運営してきましたが、領土拡大と共に経済成長を遂げた結果、元老議員以外に経済力をもった騎士階級(エクイタス)が生まれ、何よりも大きな経済的な格差によって多くの国民が失業する事態が発生したのです。
ローマ軍を支えてきた重装歩兵はローマ市民ですが、ローマ市民と認められるためには一定の資産を有している必要があり、その条件を満たさない人は無産階級(プロレターリ)となり、兵役の免除と免税が定められていました。
その結果として社会不安とローマ軍団の弱体化を招き、それは共和制ローマを構成する同盟都市国家にまで波及することになるのです。
改革の必要性を心の底で認めることと、それを実行に移すこととはまったく次元が違います。
何故ならシステムの変革は既得権益を得ている人々がそれを手放すことを意味している以上、例外なく彼らが激しい拒絶と抵抗を示すからです。
それは2000年以上を経た現在日本の政治や企業においても、まったく変わることはありません、
高い志と固い意志を持って改革を実行しようとしたグラックス兄弟は、元老院の抵抗によって非業の最期を迎えることなります。
彼らの打ち出した政策は当時のローマにとって間違いなく"正しいこと"でしたが、それが既得権益層(元老院)に認められることはなかったのです。
改革を先送りにし時代の流れ取り残されたローマ。
普通の国であれば、そのまま衰退期に向かっていくはずでした。
しかし共和政ローマには、マリウスとスッラといった実力を持ったリーダーが出現します。
彼らはグラックス兄弟ほど純粋な動機も改革への意欲も持っていませんでしたが、軍隊を私兵化し有無を言わせぬ実力で元老院を黙らせ、本人たちは意図せずとも共和政ローマのシステムを壊してゆくことになるのです。
また彼らが登場しなければ、外敵から身を守ることも内乱でさえも鎮める指導力を元老院は失っていたのでした。
「勝者の混迷」というタイトルが付けられていますが、私には"混迷"というよりも"実力ある個人の台頭"の時代が到来したという印象を受けたました。
ローマ人の物語 (5) ― ハンニバル戦記(下)
ローマ軍に10万人以上の犠牲者を出し、約10人にも及ぶローマ軍司令官を戦死に追いやったカルタゴの将軍ハンニバル。
後世の我々から見ればハンニバルは天才ですが、当時のローマ人にとってハンニバルは天才どころか"正真正銘の悪夢"であり、16年間にも渡って彼とイタリアを恐怖に陥れた張本人でした。
そんなハンニバルと正面切って挑戦できる"もう1人の若き天才"がローマに彗星のごとく現れます。
その名はスキピオであり、彼はハンニバルがローマ(イタリア)へ対しておこなった作戦をそのままカルタゴへやり返すという戦略を立てます。
つまりカルタゴ領であるスペイン、そしてアフリカへ攻め込み、イタリアへ居座り続けたハンニバルをアフリカへ引っ張りだすことに成功するのです。
それがザマの戦いとして実現し、著者はそれを次のように表現します。
ハンニバルとスキピオは、古代の名将五人をあげるとすれば、必ず入る二人である。
現代に至るまでのすべての歴史で、優れた武将を十人あげよと言われても、二人とも確実に入るにちがいない。歴史は数々の優れた武将を産んできたが、同じ格の才能をもつ者同士が会戦で対決するのは、実にまれな例になる。そのまれな例が、ザマの戦場で実現しようとしていた。
後世の私たちはザマの戦いの結果を知っていますが、それでも読者としてこれから本書で触れられるザマの戦いを期待せずにはいられなくなります。
やはりカンネの会戦の時と同じく、歴史小説にも関わらず戦闘の模様を図で解説してくれる手法は秀逸であり、読者が戦闘の経過を理解しやすくなることで臨場感が増し、さらにそこからは二人の戦術や考えをも読み取ることが出来るのです。
結果的に第二次ポエニ戦争(ハンニバル戦記)の勝者となった共和政ローマは、絶頂期を迎えることになります。
共和政ローマとは、300人の定員からなる元老院によって実質的に運営される政治システムであり、たとえばローマの最高権力者である執政官は市民投票によって決定しますが、そもそも元老院からの承認が無ければ立候補することすら出来ませんでした。
つまり共和政ローマは少数寡頭政治であり、独裁君主制とはまったく異なるものでした。
それは絶対的な英雄となったスキピオが元老院の大カトーらにより起訴され、表舞台から消えるという結末になって現れます。
それでも絶頂期を迎えていた共和政ローマは、向かう所敵なしの勢いで快進撃を続けます。
アレクサンダー大王で有名なマケドニアを滅亡させ、ギリシアをも事実上の支配下に置きます。
さらに第三次ポエニ戦争でカルタゴを滅ぼし、地中海を制覇することになります。
しかし人間に寿命があるように、共和政ローマもその例外ではありません。
つまり"絶頂期"を迎えるということは、以降は下降線を辿ってゆくことを意味しており、次巻ではそんな共和政ローマの黄昏が書かれることになるのです。
ローマ人の物語 (4) ― ハンニバル戦記(中)
ローマと比べて経済力では上回っていても、兵士の質そして指導者の戦略によってカルタゴが一敗地にまみれた第一次ポエニ戦争。
やがて23年の月日が流れて、カルタゴに1人の天才が現れます。
その人物こそ世界史でもその名が必ず出てくる"ハンニバル"であり、古代最高の戦術家として敵として向かい合ったローマ人からも認めらている将軍なのです。
著者の塩野氏は、"天才"を次のように定義しています。
天才とは、その人だけに見える新事実を、見ることのできる人ではない。
誰もが見えていながらも重要性に気づかなかった旧事実に、気づく人である。
ハンニバルは強大なローマを打ち破るため、戦いの序盤から早くも常識(と思われてきたこと)を打ち破るのです。
それは険しいアルプスを大軍で越えるのは不可能という常識であり、またローマの内部(イタリア半島)へ飛び込んで戦いを繰り広げるという発想でした。
さらにそこに待ち受けていたのは、兵の数でも質でもカルタゴ軍を上回っていた名高いローマ軍です。
それでもハンニバルは、ティチーノ、トレッビア、トラメジーノ、そして歴史に名高いカンネの会戦でローマ軍を徹底的に撃破することに成功します。
数万の兵士からなるカルタゴ軍が1人の天才の出現にによってここまで変わるのかと思われるくらい、ハンニバルの戦いは完璧なものでした。
たった1人の人間によって地中海を制圧した大国ローマが存亡の危機を迎えるに至って、当時のローマ人が第二次ポエニ戦争を「ハンニバル戦記」と呼んだのも当然といえます。
ローマの重装歩兵の突進力はカルタゴのそれを上回っていましたが、ハンニバルは騎兵を巧みに操り、包囲戦によってローマ軍を殲滅し、カンネの会戦では実に7万人にも及ぶローマ兵が戦死したと言われています。
この16年間にも及んだハンニバル戦記において10人以上ものローマ軍司令官が戦死したというのは衝撃ですが、10人以上もの司令官が戦死したにも関わらず戦争を遂行できた事実にローマの底力を感じます。
それどころか積極果敢な「イタリアの剣」と称されたマルケルス、我慢強い持久戦を得意とした「イタリアの盾」と称されたマクシムス、奴隷を訓練して率いるという困難な任務を遂行したグラックスをはじめ、ローマ軍にも優れた指揮官が次々と登場します。
これは希代の戦略家であるハンニバルの目の前にローマの秀才たちが次々と立ちはだかり、勝利は難しくとも少しづつカルタゴ軍を消耗させることになるのです。
つまり1人1人の能力はハンニバルに敵わずとも"人材の層"についてはローマが勝っていたのです。
しかしやがてローマにも若き天才・スキピオが登場します。
これはハンニバルと正面から戦うことのできる人材が初めて現れたことを意味しますが、それは次巻のお楽しみになります。
本書では戦いの段階ごとに図解されており、著者の解説とともに読むことで読者が一目でその経過を知ることができるのは優れている点です。
「ハンニバル戦記」を余すこと無く堪能できる本書は、そのスケールの大きさと臨場感を味わえる1冊であり、ローマ史に興味のない人でも間違いなく楽しめると思います。
ローマ人の物語 (3) ― ハンニバル戦記(上)
上中下に分かれる第2巻では、序盤のハイライトである「ポエニ戦争」に突入してゆきます。
本書ではハンニバルやスキピオが登場する以前の「第一次ポエニ戦争」に触れられています。
イタリア半島を統一したローマとフェニキア人の建国した通商国家カルタゴが地中海の覇権をめぐって激突することになる戦争です。
地中海の南北両岸そして地中海の島々に領土を持つカルタゴは、地中海周辺において最大の経済力を誇っており、強大な海軍を備えていました。
一方ローマでは、南イタリアの一部の都市が地中海交易をしていたくらいで、海軍のノウハウさえ持っていませんでした。
当時のカルタゴでは「カルタゴの許可なくしては、ローマ人は海で手も洗えない」と皮肉られたほどの実力差が存在していたのです。
海軍を短期間で準備するため、ローマ人はカルタゴの軍船を拿捕・解体して見よう見まねで五段層軍船を製造し、兵士たちを急いで訓練したのです。
それでも経験値がモノを言う熟練度は、カルタゴの方がはるかに高いのは当たり前でした。
そこで操船技術に劣るローマ海軍は、敵船の甲鈑に打ち下ろす通路「カラス」を発明し、海戦をローマの得意とする歩兵戦へ持ち込む発想をするのです。
船の外観を損ねる「カラス」をあざ笑っていたカルタゴ兵たちですが、やがてその威力を経験した彼らの顔が恐怖に歪んでゆきます。
「素人考え」と表現すると悪い意味に取られがちですが、これは素人の発想が玄人たちの常識を覆した好例になります。
さらに2巻で触れたターラントがピュロス王を雇ったのと同じく、カルタゴはスパルの傭兵隊長クサンティッポと傭兵からなる軍勢でローマ軍と対峙しますが、やはり結果は同じことになります。
選挙権を持ち経済的にも独立しているローマ市民が中心となって構成されるローマ軍は、自らが血を流して祖国を防衛することに誇りにしており、一丸となってカルタゴと戦い続けます。
その士気はカルタゴに金で雇われた傭兵たちとは比べ物にならず、さらに貴族間の派閥争いが絶えないがために団結することの出来ないカルタゴは、経済的に優位だったにも関わらず、20年以上も続く"第一次ポエニ戦争"の中で徐々に劣勢に立たされ、シチリア島をはじめとした領土を失ってゆくのです。
最終的にローマの圧倒的有利な講和条件によりこの戦争が終結したのは、カルタゴ側の戦意喪失によるものだったのです。
本書の後半では、ポエニ戦争の第一次と第二次の間の23年間についても言及しています。
そこではローマの税制や統治体制、そして軍制に詳しく触れらており、2200年以上も前にローマ人の知恵によって創りだされた優れたシステムを知ることができます。
特に興味深かったのは、ローマ軍の中核をなす重装歩兵のもっとも基本的な単位である小隊を率いる百人隊長(ケントゥリオ)へ言及している部分です。
百人隊長と聞くと"百人の兵士を率いる小隊長"、つまり数万規模のローマ軍における下士官といった役割を想像していましたが、実態はまったく異なるというものです。
軍を率いる最高司令官は執政官、そして中隊長クラスまでの人選は市民集会によって決まる一方で、百人隊長は兵士たちによって選出される戦いのプロ中のプロといった存在でした。
そんな百人隊長の重要性を著者は次のように表現しています。
最高司令官の武将としての能力は、百人隊長をどれだけ駆使できるかで決まったという。カエサルを頂点とするローマの名将たちはいずれも、百人隊長の心を完全に手中にし、彼らを手足のごとく使いこなせた男たちであった。
当時ローマ軍の将軍は、1年間(前執政官を入れれば2年間)という短い任期の執政官が務めていました。
執政官は内政・軍事の最高責任者であったため、中には戦争を得意としない執政官もいたはずですし、そもそも長い期間に渡って軍を掌握すること自体が無理だったのです。
それにも関わらずローマが常勝軍だったのは、戦場では常に百人隊長が陣頭指揮を執っていたからであり、そこからは彼らが「ローマ軍の背骨」として賞賛されていた真の意味が分かる気がします。
ローマ人の物語 (2) ― ローマは一日にして成らず(下)
ローマの創成期は王政によるトップダウンによって急速に都市国家として成長してきました。
しかし王政が個人の資質に左右されてしまい、安定的、かつ長期的な成長に適していないと判断するとさっさと共和制へ移行してしまうあたりは状況に応じて抜群の適応能力を持っていたローマ人らしさが表れています。
任期が1年という短い2名の執政官、非常時には任期が半年という独裁官を頂点とした体制となり、とにかく安定した成長を見せ始めます。
周辺の同盟都市とローマ連合を結成し、イタリア内陸部の山岳地帯に住むサムニウム族とはなんと40年以上に渡って戦いを繰り広げた末に勝利を収めます。
たとえば軍事能力に優れた王であれば、この戦争を10年で終結できたかも知れません。
しかし無能な王であれば、逆にローマは10年以内に滅亡したかも知れません。
それこそ何人もの執政官が軍隊を率い、ずば抜けた実績をあげられずとも、何十年にも渡って全体的に見れば有利に戦いを進めてきた結果といえます。
また時にはケルト人の襲来によりローマを一時的に占領される危機が訪れるものの、地道に都市を復興させ、やはり以前よりも少しずつ着実に成長してゆきます。
これをプロ野球で例えると、当時のローマの指導者たちはエース級の実力はないものの、毎年安定して10勝7敗くらいの成績を残す3、4番手くらいの先発ピッチャーのような印象を抱いてしまいます。
こうして着実に貯金を蓄えたローマの前に、南イタリア最大のギリシア植民都市"ターラント"が立ちふさがります。
このターラントは海運により発達した商業都市であり、財力はあっても(特に歩兵の)軍事力は不足しています。
そこでターラント首脳陣たちは、北部ギリシアから"戦術の天才"といわれるピュロス王をスカウトしてローマ軍と戦わせることを選択します。
軍隊や指揮官さえも財力にモノを言わせて買ってしまうターラントの発想は面白いところです。
ピュロス王は噂に違わぬ実力者であり、執政官率いるローマ人は急造ターラント軍によって撃破されてしまいます。
"泥臭い田舎育ちのローマ軍"と"スマートな都会育ちのターラント軍"といった感じの対照的な両軍ですが、ここでもローマは「らしさ」を発揮します。
自国の運命を傭兵に委ねたターラント、市民たち自らが血を流し続けた戦い続けたローマ。
ローマ軍の消耗はターラント軍よりも激しいものの、その高い士気が徐々にターラント軍を追い詰めてゆき、ピュロス王を戦意消失に追い込んで勝利を得ることになります。
さらにこの勝利によって、ついにローマはイタリア半島を統一することに成功するのです。
とはいえイタリア半島の面積は日本の本州と同じ程度しかありません。
しかもイタリア半島を統一した時点でローマは建国から500年が経とうとしていました。。
一方で地道に領土を広げてきたからこそ、のちの広大なローマ帝国の礎となる密度の高い骨肉をこの時点で身につけていたのであり、まさに「 ローマは一日にして成らず」なのです。
登録:
コメント
(
Atom
)