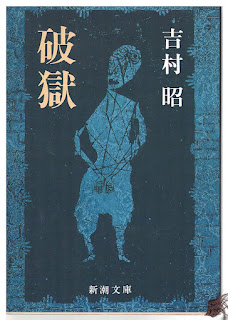還るべき場所
笹本稜平氏の長編山岳小説です。
彼の山岳小説は、未踏峰ルート登頂や過酷な条件下におけるサバイバルだけに主眼を置くのではなく、大自然を舞台にした人間ドラマに力を入れているという点が特徴です。
世界の名だたる山や絶壁に挑戦するクライマーたちにとって困難や危険を克服することは、何よりの名誉と生きがいを与えてくれるのです。
同時にその挑戦は常と死と隣合わせであることを意味しています。
主人公の翔平は世界的に名の知れたクライマーでしたが、世界第2位の高さを誇るK2の東壁において恋人であり登山パートナーであった聖美を事故で失い、4年間もの間、山から遠ざかり家に引きこもる生活を続けていました。
そんな翔平を見かねて、かつて登山仲間であり聖美の従兄弟でもあった亮太が、自らが経営する登山ツアー会社・コンコルディアツアーズのガイド役を依頼するところから物語が始まります。
翔平はかつて次のように登山を考えていました。
生命を失うことが暗黙のルールとして組み込まれているスポーツが登山以外にあるだろうか。登山における死はアクシデントではなく、ゲームのルールに基づく敗北なのだ。
しかしツアーは商業目的で組まれたものであり、かつて翔平の経験してきた登山とは異なり参加者全員の"安全"を守ることが何よりも重要な任務となります。
8000メートル級のブロード・ピーク登頂がツアーの目的ですが、そのツアー客の中には、心臓病というハンディキャップを抱えながら登頂を目指す会社経営者・神津も参加します。
彼もまた社会のさまざまなしがらみを抱えながら、今回のツアーに参加してきたのです。
著者の描き出す人間模様は、過酷で美しい大自然だけがあるヒマラヤだからこそ読者に鮮やかに伝わるのかも知れません。
またそれは都会の喧騒を離れて自然の中で人生を見つめ直すという感覚を極限まで突き詰めたパターンなのかも知れません。
本書はかなりの長編ですが、山岳小説としても読み応え充分です。
大自然の厳しさと人間ドラマがしっかりと交差している点でもおすすめできます。
仮釈放
本書は吉村昭氏の作品としては比較的めずらしい完全なフィクション作品です。
主人公は妻と2人暮らしの元教師。
真面目な性格で趣味といえば釣りくらいで平和に暮らしていましたが、ある日妻と釣り仲間の不倫現場を目撃し殺人を犯してしまいます。
そのため無期懲役の判決を受けますが、男は模範囚として16年間を刑務所で過ごし、50歳を過ぎて仮釈放となります。
刑務所での単調で変わり映えのない生活と比べ、男にとって久しぶりの世の中は大きく変貌を遂げていました。
ここまでは小説の序盤ですが、この作品は多くの作家が試みてきた"罪と罰"をテーマに扱っています。
吉村氏は本作品を実在した脱獄囚を扱ったフィクション小説「破獄」から着想を得たと語っていますが、刑務所の風景が描かれている点を除いては案外共通点は多くありません。
「破獄」ではなるべく事実に基づいた描写がメインでしたが、本作品では過去に犯罪を犯した男の複雑な心理が描写されています。
"罪"とは、倫理的または法的な犯罪を指すとともに、自己の良心に照らし合わせた心理的(時には宗教的)なものに大別されます。
人を殺めたという点では、男は間違いなく法的な罪を犯しています。
一方で、自分の信頼を裏切り不倫を行った元妻の殺害、そしてその不倫相手の男へ傷を負わせた点については後悔どころか必然であったと考えています。
つまり男にとって内面的には罪を認めていないのです。
しかし間違いなく16年間もの懲役により肉体的・精神的な"罰"を受けていますが、それは男へ何をもたらしたのでしょうか。
主人公の男は真面目で教養もあります。
社交性にはやや欠ける部分があるかも知れませんが、せいぜい控えめな性格と見られる程度です。
恩義を受けた人の助言は素直に聞き入れますし、職場の上司の指示にも忠実に従います。
つまり短気で荒っぽい性格の人間ではなく、外見上はどこにでもいそうな人間をあえて主人公にすることで"罪と罰"といったテーマがはっきりと浮かび上がってくるのです。
一見すると仮釈放された(平凡に見える)男の日常を描いているだけのように見えますが、その内面の変化を丹精に描くことで作品に起伏をもたせ、いつの間にか読者もその挙動に目を離せなくなるのだから不思議です。
ぜひ最後まで読んでその余韻に浸ってもらいたい作品です。
破獄
戦前、戦中、そして戦後に4度の脱獄を実行した、佐久間清太郎の半生を描いた吉村昭氏の作品です。
執筆当時はプライバシーに考慮したため、作品中の登場人物名は創作ですが、史実にこだわり記録文学の新境地を切り開いた著者だけに、実際の出来事を綿密に調査した上で執筆されたノンフィクションに近い作品であると言えます。
文庫本でぎっしりと350ページにも及ぶ長編作品であり、佐久間が収監され脱獄するまでの過程が事細かく描かれています。
驚かされるのは、佐久間が脱獄したのは野外作業のどさくさに紛れての脱走ではなく、独居房や鎮静房と呼ばれる堅牢で監視が厳重な場所からの脱獄であることです。
誰もが脱獄不可能と思っていた場所から常人には想像のつかない観察眼、知力、体力、そして忍耐力を発揮して脱獄する佐久間は、もし彼が犯罪者でなければ、一流のアスリートになれる素質が充分にあったと思わせるものでした。
さらに真冬の網走刑務所から脱走した際には、山狩りから逃れ捜査は打ち切られ誰もが凍死間違いなしと思っている過酷な自然の中で廃坑に潜り込み冬を過ごすといったサバイバル術にも長けていました。
看守たちも佐久間を逃せば懲戒処分を受けるという危機感から警備を強めますが、常にそれを上回る能力を発揮して合計4回も脱獄を繰り返すのです。
彼の30年近くに及ぶ刑務所における生活は、戦前・戦中・戦後という日本の行刑にとって激動の時代であり、その移り変わりの風景についても充分に触れられています。
戦前には非人道的な強制労働によって多くの囚人が安価な労働者として厳しい現場に駆り出され、多くの死者を出した時代もありました。
そして戦中は食料不足によって、多くの囚人が栄養失調のために死亡したというデータも残っているようです。
戦後はGHQの占領政策により囚人へ人道的な扱いを行う政策が打ち出されましたが、戦後の混乱で物資不足が続き、さらに行刑への理不尽な介入もあり決して安定していた訳ではありません。
作品中で明言されている訳ではありませんが、佐久間のとった行動は時代の犠牲となった囚人たちの声なき声を代表した行動であるような気がしてきます。
最後に府中刑務所の所長が佐久間を1人の人間として扱い、のちに模範囚となってゆく過程は、長い物語の最後で読者が報われたような気持ちになるのです。
富士山の謎と奇談
著者の遠藤秀男氏は、富士宮市に生まれ地元で教師をしながら富士山研究を続けてきた"郷土の歴史家"ともいえる方です。
本書は、富士山にまつわる著者の研究成果を新書という形で幅広く紹介している1冊で、静岡新聞社から出版されています。
まずは"富士山"命名の謎を歴史書から紐解いてゆき、特に富士山信仰についてはページを割いて解説しています。
富士山信仰は私の想像以上に盛んであり、富士山を祀った浅間神社(せんげんじんじゃ)が東海・関東地方を中心に1316社も現存していることには驚きです。
加えて過酷な自然条件にある富士山において約800年前の経文が発掘されたこと、今だに富士山から新しい発掘品が見つかるなど、長い信仰の歴史を感じさせます。
ちなみに19世紀のはじめ頃までは山頂付近に多数の仏像が立ち並んでいたらしく、これら仏像に1人ずつ人間が付き添っており拝観料として銭を八文ずつとっていたという記録も残っているようです。
こうして江戸時代に全盛期を迎えた富士山信仰ですが、明治政府による廃仏毀釈によって山中の仏像や仏具がことごとく破壊されて谷に捨て去られたことによって急速に衰えてゆきます。
このときに多くの歴史的価値のある遺産が失われてしまったという点は残念です。
昔から日本人を魅了し続けてきた富士山は、時代によって形や姿を変えながら、神道から仏教、それから派生したさまざまな信仰に影響を与え続けてきました。
ちなみに登山者が富士山山頂から朝日を拝む行為は、江戸時代から人気のあったイベントであり、御来光や御来迎(ごらいごう)は形を変えて現在でも脈々と受け継がれています。
私自身、富士山への登山を経験したことがありませんが、本書で紹介されているような歴史的背景を頭の片隅に入れておくと、登山がより一層味わい深いものになることは間違いありません。
高校野球「裏」ビジネス
ここ数年、高校野球の人気は衰えるどころか、ますます盛り上がってきています。
私自身毎年、試合結果や熱闘甲子園といった番組は欠かさずに見ている高校野球ファンです。
しかし高校野球に国民的人気があるということは、裏を返せばそこにさまざまな利権があることは容易に想像できます。
チームの勝利のために必死に白球を追う高校球児たちの姿は、見ている側の気持ちまでも純粋にしてしまう魅力があり、高校野球の裏にはびこる世界に殆ど関心を持ってこなかったのが正直なところです。
本書はノンフィクション作家の軍司貞則氏が、北海道から九州までを各地を取材し、将来を有力視された球児たちの裏で動く裏ビジネスの実態に迫っています。
2007年に「西武球団裏金事件」、つまりプロ野球球団がドラフトで有望な学生球児に金銭を供与していた事が発覚しましたが、著者はそれを昔から延々と存在してきたことであり、今回発覚した事件は氷山の一角に過ぎないと断言しています。
金銭供与はプロ野球球団どころか、リトルリーグと強豪高校の間でもやり取りされていることであり、"野球ゴロ"や"悪徳ブローカー"と言われる人たちがそこで利益を得ているということを取材で明らかにしています。
創立間もない高校、少子化の中で生徒を確保したい高校にとって"甲子園出場"という肩書きは、名前を全国的に宣伝するこの上ない機会であり、そののために手段を選ばない高校が出てきても不思議ではありません。
一方で特待生として授業料や寮費を免除するという制度は、経済的に余裕のない家庭にとって、子どもが好きな野球を強豪校で続けられるという点からも魅力的な条件なのは間違いありません。
こうした両者の思惑を橋渡しすると称して、行き過ぎた勧誘や引き抜きが横行し、あたかも球児を"人身売買"するかのような事態にまでなってしまったのです。
著者はこうした事態に陥った要因の1つとして、統一された野球連盟が存在せず、関連組織が乱立する制度的な問題にも切り込んでいます。
本書には休日返上で自費で全国を行脚し有望な選手のスカウトを続ける熱血的な監督も取り上げられていますが、割に合わない厳しい環境で野球を指導している監督が全国に多数存在するという状況の裏返しが「裏ビジネス」を生み出す土壌になっているという見方もできます。
もちろんアスリートの養成にはお金が必要なことも確かですが、甲子園を楽しめるか以前に、学校教育の一環として位置づけられる高校野球の理念と乖離してしまってはその存在意義が失われてしまうのではないでしょうか。
登録:
投稿
(
Atom
)