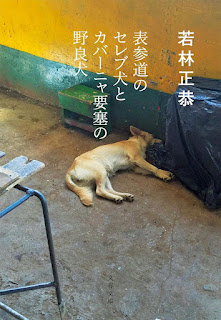前田利家(下)
津本陽氏による「前田利家」もいよいよ最終巻です。
利家は信長麾下の武将として14歳で初陣を果たし、天下人となった秀吉の右腕として80万石以上の大大名として出世します。
つまり利家は勇敢な武将としてだけなく、有能な政治家としての能力をも兼ね備えていたのです。
そして秀吉亡き後、まだ幼い秀頼の後見人として指名されたことにより、事実上、豊臣政権を支える最高責任者となったのです。
秀吉政権下で最大の実力を備えていたのは関東に255万石という領土を持つ徳川家康でしたが、彼に比肩しうる実力を備えていたのは前田利家ただ1人でした。
何より利家自身に、もし家康が豊臣家へ反旗を翻すことがあれば、それを討伐できるのは自分しかいないとう覚悟がありました。
前田利家と徳川家康による2大勢力のにらみ合いという構図であれば比較的単純な構図でしたが、そこに第三の勢力として生前の秀吉から絶大な信頼を得て、その死後も政権の中枢で絶大な権力を握っていたのが石田三成をはじめとした奉行派でした。
はじめに三成と家康との間に深刻な対立が起こりましたが、利家にとって難しいのが彼自身も三成へ対して苦い経験を持つ武将の1人であったということです。
それでも利家が秀頼の後見人として豊臣家へ絶大な忠誠心を抱いていたというのは生涯にわたって一貫しており、結果的に利家は三成と家康の対立を調停するという役割を担うことになります。
そこに加えて秀吉の晩年から利家自身も体調を崩しはじめ、健康が悪化の一途を辿るという状況に陥ります。
彼には利長・利政という2人の後継者候補がいましたが、誰よりも家康の力量を知っているだけに、彼らが自分の死後に家康に対抗できる器を持っていないことを冷静に見抜いていました。
それは三成へ対しても同様で、武将たちからの信望が薄いという致命的な欠点を持っていることを見抜いていました。
それらの問題をすべて解決するために自らの存命中に家康を討つことを決意しますが、慎重で用意周到な家康はそのための決定的な口実を作らせませんでした。
いよいよ自分の命が長くないと悟ったとき、前田家としてあくまで豊臣政権への忠誠を貫き通し続けるべきか、それとも家の存続を優先させるべきなのかに苦悩することになります。
歴史ファンにとってIF(イフ)を考えるのは楽しいひとときですが、もし前田利家があと5年生きながらえることが出来たなら、その後の歴史は大きく変わっただろうと思わせる人物です。
上中下巻合わせて1000ページ近くに及ぶ本作品は、前田利家の生涯を仔細漏らさず描き切ったと言える大作であり、読み応えのある戦国時代小説を読みたいという欲求を充分に満たしてくれるのです。
前田利家(中)
津本陽氏による「前田利家」中巻のレビューです。
上巻では利家の14歳の初陣から賤ヶ岳の戦いまでが描かれていましたが、中巻では秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)までを描いています。
秀吉陣営の武将となった利家でしたが、当時秀吉と対立していた家康陣営に組みした越中の佐々成政と対峙することになります。
2人の関係は信長存命中、その親衛隊として利家の所属する赤母衣衆、そして成政は黒母衣衆の一員として武勇を競い合ったライバルでもあったのです。
利家は秀吉から能登と加賀の統治を任され、年齢も40代半ばを迎えて昔のように先陣を切って槍1本で敵陣へ突っ込むような立場ではなくなりました。
それでも利家配下の村井長頼、奥村永福といった有能な武将たちを統率することによって、苦戦しながらも成政との戦いを有利に進めてゆきます。
秀吉は低い身分から裸一貫で天下人となりましたが、それだけに信頼できる一族や武将の数が少なく、信長時代から同僚として気心の知れた利家を右腕のように重宝するようになります。
さらに秀吉の妻であるねね(北政所)、利家の妻であるまつ(芳春院)が昔から懇意であったことも大きく関係していたようです。
それでも天下人として関白そして太閤へと昇り詰めた秀吉との力関係には明らかな差があり、いかに利家といえども上手な世渡りが求められる立場となったのです。
五大老の中でもっとも大きな勢力を持ってたのは徳川家康でしたが、秀吉は心の底から彼を信用していたわけではなく、その抑え役としての役割を利家に期待していたのです。
さらに世間の武将たちの目から見ても秀吉政権下で家康と比肩しうる実力と器量を持っているのは利家しかいないという見方が一般的でした。
血の気の多い勇敢な武将という立場から一転して政治的な指導力を求められるようになりながらも、その役割を全うできた武将は少ないような気がします。
たとえば前述した佐々成政は勇猛な武将ではありましたが、天下の帰趨を見抜く力がなく、また政治的な知見も不足していたため破滅へと至りました。
作品では利家がどのような役割を果たしたのかが事細かく記述されており、かなり硬派な歴史小説という印象を受けますが、それだけに前田利家の生涯を知りたいという戦国ファンの期待に充分応えられる作品になっています。
前田利家(上)
剣豪小説で有名な津本陽氏ですが、本書は有名な戦国武将を題材にした長編小説となります。
一口に戦国武将といっても色々なタイプが存在しますが、前田利家は「槍の又左」という異名から分かる通り、自らの槍で敵武将の首級を挙げて出世してゆく分かりやすタイプの武将だと言えます。
14歳から戦場に出ていた利家は当時の常識から考えても若い初陣だったようですが、六尺(180cm)を超える立派な体格を備えていたことも関係しているように思えます。
まさに戦国時代の申し子のような人物ですが、合戦では剣豪同士の果たし合いのように1対1での対決ではなく、芋を洗うように敵味方が入り混じっての乱戦になるのが普通です。
つまり最前線で戦う武将たちはいつ背中から敵に狙われるかも知れず、世に名を知られた豪傑が合戦であっけなく命を落とすことも珍しくありませんでした。
常にこうした戦場へ真っ先に飛び込んでゆき敵武将の首級を取ってくる利家は、信長から「肝に毛が生えておるわ」と称賛されるほどでした。
命知らずだけに若い頃の利家は短期で喧嘩早い性格であり、信長の寵臣である拾阿弥と口論になり、ついには斬殺してしまいます。
そのため信長の怒りに触れて勘当となり、一時期は浪人となるような苦労も経験しています。
当時は武将同士がちょっとした言い争いから喧嘩となり、たちまち殺し合いとなる事件が日常茶飯事であり、合戦が身近であった当時の武将の気性がいかに荒かったが分かります。
利家の戦歴は、信長が家督を相続し尾張1国を統一する頃からはじまり、本能寺の変が起こる頃には信長の宿老である柴田勝家の与力として能登一国を与えられるまでに出世しています。
利家にとって勝家は、彼が信長に勘当された際に取り直して帰参させるなど多くの恩を受けた存在でした。
一方で信長亡き後、その後継者の最有力候補として頭角を現した秀吉とも身分が低い頃からの同輩であり、家族ぐるみの付き合いをする仲でした。
それだけに秀吉と利家が賤ヶ岳で戦った際には、思い悩んだはずであり、結果的に中立のような立場を取ることになります。
勝利した秀吉から見ると、利家と勝家の関係性を充分に承知しているだけに、勝家へ助力しなかっただけで充分であったようで、秀吉に重用されてゆくことになります。
本作品は時代背景に関する解説は最小限であり、当時の書状が解説なく掲載されていることも多く、歴史小説の中でもかなり硬派な部類に入ります。
それだけに戦国ファンであれば、かなり読み応えのある作品として楽しめるはずです。
DIE WITH ZERO
タイトルの「DIE WITH ZERO」を直訳すると"ゼロで死ぬ"という意味になります。
これを要約すれば「死ぬまでに、金をすべて使い切る」という生き方になります。
著者の主張は、「金やそれによって得られるモノのために人生を犠牲にするべきではなく、そのときにしかできない経験の合計こそが人生の喜びである」という考えで一貫しています。
従ってすでにそうした価値観で人生を計画し、日々を過ごしている人にとって本書から得られるものはないかもしれません。
一方でなんとなく著者の主張に賛同はしながらも、
- なぜ経験こそが貴重なのか?
- 自分の寿命を予測していつまでにどのような経験をすべきなのか?
- 老後の不安へ対してどのような計画を立てるべきか?
- どのタイミングで資産を取り崩しはじめるのか?
といった具体的な内容について深く考えていない人にとって、著者の示唆することは大いに参考なるのではないでしょうか。
本書は2024年度のビジネス書部門においてベストセラー&ロングセラーを記録しており、逆の見方をすれば多くの人たちにとって本書の内容が新鮮だったということになります。
例えば遺産相続という考えがありますが、著者はいつ、誰に、いくら与えるか今すぐ考え、自分が死ぬ前に与えるべきだとしています。
なぜなら金から価値(経験)を引き出す能力は、年齢とともに低下してゆくものであり、それは自分の子どもへ対しても当てはまるからです。
たしかに高齢になってからのハードな登山や、バックパッカーとして世界中を放浪するような経験をはじめるのは、たとえ資金があったとしても健康上、または体力的な問題で難しいケースが大半です。
著者のビル・パーキンス氏はエネルギー分野のトレーダーとして成功した富豪であり、すくなくとも老後を平均的な支出で暮らし続けた場合、確実に資産を使い切ることのできない人たちを対象に本書を執筆していると思われる箇所があります。
よって現実問題としてたとえば仕事からの収入が安定せず、住宅ローンや子どもの教育費で日々の暮らしに経済的な余裕のない人にとっては、どこか他人事のように思えてしまうのも事実です。
一方で貯金や節約が手段ではなく、趣味や目的にまでなってしまっている人にとっては本書から新しい価値観を得られるのではないでしょうか。
身近な話題であれば新NISAや老後資金、103万の壁といった税の話題、大きな視点でいえば世界経済を牽引するアメリカ企業による株価の上昇や戦争・政治的要因による先行き不透明感もあって、本屋にはかつてないほど貯蓄や投資に関する本が並べられています。
つまり貯蓄や資産運用の方法が書かれた本が多い中で、いかにお金を使うかをテーマにした本書の視点は斬新であるといえ、その辺りに本書がベストセラーになった要因があるのではないでしょうか。
幕府軍艦「回天」始末
タイトルに幕府軍艦「回天」とありますが、実際には榎本武揚を中心とした戊辰戦争、その中でも宮古湾海戦、そして箱館戦争を中心に描いた歴史小説となります。
榎本は幕末の中でもかなりユニークな経歴をもつ人物です。
彼は幕臣としてオランダへ留学した経験を持ち、船舶技術や国際法を学んで帰国し、当時もっとも開明的な考えと知識を持ち合わせていた人物です。
一方でいざ薩長連合による倒幕運動が本格的になると、大半の旗本や幕臣が慶喜の意向もあり恭順の姿勢をとった中にあって、上役でもある勝海舟の制止を振り切ってまで旧幕府艦隊を率いて江戸を離れ、新政府軍へ対して最も強固かつ最後まで抵抗を続けることになります。
やがて箱館戦争で力尽き降伏することになり、当然のように抵抗勢力(蝦夷共和国)の総裁という立場から死罪を免れないところですが、新政府側の黒田清隆らが彼の才能を惜しんで助命嘆願して赦されることになります。
江戸の無血開城を実現し、一度も新政府軍と戦うことのなかった勝海舟が明治政府の要職への誘いを断り、隠居生活に入ったのとは対称的に、最後まで戦い抜いた榎本は、明治政府の駐露特命全権公使をはじめ、大臣を歴任してゆくといった栄達を果たします。
「忠臣は二君につかえず」といった価値観から見ると、彼の豹変ぶりは褒められたものではなく、才能があったことは間違いないものの、彼の評価が分かれるのはこの辺りに原因があるような気がします。
個人的には榎本武揚の性格には頑固な面と柔軟な面が同居していて、良い意味で切り替えができる人物であったと思います。
そうした意味では維新志士の1人でありながら、榎本と同じく勝海舟を師と仰いだ坂本龍馬と雰囲気が似ていて、この2人が出会っていたら意気投合したのではないかと歴史のIFを想像したりします。
本作品を執筆するきっかけが、いかにも吉村昭らしいものです。
それは著者が三陸海岸にある田野畑村を訪れた際に、ここが宮古湾海戦へ向かった旧幕府軍の軍艦である「高雄」が座礁した地であったことを知ったからです。
榎本艦隊の「高雄」は、旗艦である「回天」とはぐれているところに新政府軍の「春日」に追い詰められ、岩礁へ乗り上げ、乗組員たちは岸へ上がって散り散りになって逃げます。
そしてすぐ近くの田野畑村に逃げ込んだ彼らの中には、村人にかくまわれているうちにそのまま土着した者もいたそうです。
そうした逸話を地元の史家から聞き、資料を集めているうちに本書の構想が生まれたといいます。
めったに歴史の勝者側の視点で作品を描くことがないという点でも、まさしく吉村昭氏らしい作品です。
魚影の群れ
吉村昭氏の動物を扱った短編が4作品収められています。
タイトルから推測しずらいものはカッコ内へ作品中で扱っている動物を追記しています。
- 海の鼠(ドブネズミ)
- 蝸牛
- 鵜
- 魚影の群れ(マグロ)
吉村氏の作品を読み始めた頃、読んでいた作品は歴史、戦史、そしてノンフィクションを扱ったものが中心であり、たまにエッセイや短編を執筆し、稀に本書のように動物を扱った作品も発表しているのだと思っていました。
しかし、動物を扱った作品は著者がもっとも得意とする分野であり、世に知られている代表的な作品とまったく遜色ないほど完成度が高いことを知るようになりました。
まさしく本書もその評価が当てはまる1冊であり、中でも「海の鼠」と「魚影の群れ」は動物、そして自然と人間との関わり合いという視点において大いに考えさせられる作品になっています。
「海の鼠」では、かつて宇和海に浮かぶ戸島(そして日振島)へ突如、ドブネズミの大集団が筏のようにまとまって海からやってきた出来事を元にした作品です。
いわゆるネズミ害により島の食料(農作物や海産物)が大きな被害を受けることになるのですが、さまざまな方法でネズミを駆除しようとする人間、そうした対策をくぐり抜けるために学習してゆくネズミとの戦いが描かれています。
柳田國男の「海上の道」で沖縄の島々などでは、海からネズミが大挙してやって来るという古い伝承が残っていると読んだことがありますが、戦後間もない1949年(昭和24年)に伝説と同じことが起きてしまうのです。
たまたま島へ上陸してゆくネズミの大群を海上から見かけた漁師の目には次のように映ったといいます。
海岸の岩石や砂礫が、一斉に動いている。
目の錯覚かと疑ったが、上方の斜面は静止しているのに磯がかなり長い距離にわたってゆらいでいる。
地震が発生して、島が陥没するのか隆起現象を起こしているのか、いずれかにちがいないと、かれは思った。
著者の特徴である無駄を削ぎ落とした精密な描写は、ネズミやその大群が苦手な人にとっては嫌悪感を抱く場面があるかもしれません。
(それほど苦手ではない私自身も、思わず鳥肌が立ちそうな箇所があったほどです。)
漁と僅かな平地や斜面を利用して栽培される農作物以外に目立った産業のない島の人びとにとってネズミ害は飢餓に直結する文字通りの死活問題であったのです。
それでも本作品で描かれているのは、人間とネズミとの単純ないたちごっこだけではなく、人間といえども大自然の営みからは無縁ではいられないという、当たり前ながらも忘れがちな事実なのです。
「魚影の群れ」は大間のマグロ漁師を主人公とした作品ですが、そこへ父娘の絆といった人間ドラマを取り入れたより文学色の濃い作品になっています。
1983年に緒形拳、夏目雅子をメインキャストにして映画化もされており、機会があれば是非見てみたいと思います。
メロンと鳩
吉村昭氏による10篇の短編小説が収録されています。
- メロンと鳩
- 鳳仙花
- 苺
- 島の春
- 毬藻
- 凧
- 高架線
- 少年の夏
- 赤い月
- 破魔矢
長編小説、それも歴史や戦史を扱ったものが代表的な作品として知られていますが、これらの作品はいずれも創作小説です。
冒頭の3作品(「メロンと鳩」、「鳳仙花」、「苺」)はいずれも死刑囚や受刑者を題材としており、いくつか同様のテーマを扱った長編小説を発表していることから著者らしさを感じさせます。
たとえば健康な状態で死を強制されるという、ある種究極の状態に置かれた人間を第三者の視点から見つめるという物語は小説ならではといえます。
続く2作品(「島の春」、「毬藻」)は"人の死"を強く意識した作品でありながら、文学作品にありがちな「死にゆく人=主人公」という視点ではなく、つねに第三者の視点から描かれており、その無駄な装飾を削ぎ落とした文章からは、登場人物たちの息遣いが聞こえてきそうです。
「凧」、「高架線」の2作品は、老齢を迎えた孤独な男性の視点からストーリーを構成しており、こうした哀愁を感じさせる作品も著者の得意とする構図です。
「少年の夏」は自らの少年時代を振り返った私小説的な要素がふんだんに盛り込まれており、本書の中ではもっともオーソドックスな小説といえるかもしれません。
最後に「赤い月」、「破魔矢」は、家庭を持っている働き盛りの男を主人公にしているものの、扱っている題材はそれぞれ異なり、前者では家族を、後者では動物を扱っています。
とくに動物を扱った短編はほかの作品にも多く、登場する動物の習性が細かく調べられた上で書かれており、たとえ創作小説であっても細部をおざなりにしない著者の几帳面な性格も相まって驚くほどリアリティのある作品になっています。
私自身は著者の作品を50冊近く読んできているため、このように作品を分類したがるのは悪い癖なのかもしれません。
もちろん吉村昭を知らない読者であっても硬派な文学品として充分に楽しむことが出来るはずです。
JAL 虚構の再生
日本航空(JAL)が2010年に経営破綻し、当時京セラ会長だった稲盛和夫氏が社長に就任して奇跡の再建を果たしたという事実は知識として私もなんとなく持っています。
当時、稲盛和夫氏がJALの再建に取り組んでいる様子がTVでしばしば放映されていたことも記憶にあります。
一方でJALがどのような経緯で巨額の債務を抱えて破綻へと至ったか、またどのようなやり取りを経て稲盛氏が社長に就任したかについては、殆ど知識を持っていませんでした。
本書は共同通信社の記者であった小野展克(おの のぶかつ)氏によって、まさにJALの再建が始まろうとしていた2010年に発表された本です。
よってJALという企業が破綻に至るまでの過程、再建プランが立案され決定していったかのプロセスが中心に紹介されており、まさしく私がよく知らなかった部分に焦点を当ててくれている1冊です。
本書は全6章で構成されており、はじめにJALがリーマンショックによる国際線の不振により大赤字を出し、それにより過去の放漫経営もが明るみになってゆく経緯を知ることができます。
さらに政権交代により民主党の意向によって発足した民間のタスクフォースによるJAL再生プランの立案、さらに政治家や関係各省による主導権争いよって再建の担い手がタスクフォースから企業再生支援機構へとバトンタッチされていった無体裏が描かれています。
ここまで来て一旦時間を巻き戻し、戦後まもなく国策会社としてJALが創立された経緯から御巣鷹山のジャンボ機墜落事件を経て、その経営に暗雲が立ち込み始めるまでの経緯が詳しく紹介されています。
そこかから全日空(ANA)さらには世界各国を含めた航空業界全体の現状や見通しを述べつつ、羽田国際化をはじめとした規制緩和の行く末を大きな視点から分析しています。
そして終章では、CEOに就任した稲盛氏率いるJAL再建への見通しや課題、つまり再生シナリオを予測しています。
運輸省で航空局長、事務次官を経て、最終的には成田国際空港社長に就任した黒野匡彦氏、つまりJALの歴史からその内幕の全貌を知っている人物ですが、著者の取材へ対して次のように答えています。
「なぜ日航が破綻したか-。それは、国有会社だったからじゃないかなあ」
捉えようによっては人ごとのような回答ですが、まさしくJALの紆余曲折はこの一言に集約されているような気がします。
国策会社という国民全体の利益や利便性提供を目指して設立された企業が莫大な利権を生み出し、そこへ政治家、官僚、そして歴代のJAL経営者たちのエゴが絡み合って翻弄され続けた結果であり、これを1度リセットするためには会社更生法の適用、つまり破綻という道のりは避けられなかったというのが個人的な感想です。
JALの再建をテーマにした書籍はたくさん出版されていますが、JALという企業がどのような過去を経て現在も存在し続けているのかを網羅したい人にとっては是非一読してみることをおすすめします。
絶滅危惧職、講談師を生きる
私は年に何度か寄席へ足を運ぶ程度の演芸好きであるものの、熱心なファンというわけではありません。
今やYoutubeなどで自宅にいながら様々なコンテンツを手軽に見ることができる時代になっていますが、寄席というさほど広くもない空間で生でプロの芸を聴くというのは、個人的にある意味で贅沢な時間の使い方だと感じています。
本ブログでも過去に円朝、志ん生、米朝、談志といった落語の名人と言われる人たちの本を紹介してきましたが、落語家に比べてかなり少ない講談師の本は今まで読んだことはありませんでした。
著者である神田松之丞は、本書の発表当時(2017年)では二ツ目の講談師であり、真打ちでない芸人が本を出版しているという点で異例ではありますが、今では真打ちに昇進し大名跡を継いで神田伯山へと改名しています。
それだけに本書の発表当時から将来を有望視されている講談師であったことは間違いありません。
本書は文芸評論家である杉江松恋氏が松之丞へインタビューを行うという形式で、自らの生い立ちや講談師になるまでの過程、さらに前座としての修行時代から真打ち昇進を見据えての将来像などを存分に語っています。
私自身は著者の師匠であり人間国宝でもある神田松鯉をはじめ何人かの講談師の高座は寄席で聴いたことがありますが、歴史小説が好きな私にとって宮本武蔵、忠臣蔵、清水治郎といった講談の題材が馴染み深いこともあり、すぐにその高座に引き込まれた記憶があります。
一方で著者の講談をまだ生で聴いたことはありませんが、今を代表する講談師の本ということで手にとってみました。
まず本書で驚くのは、著者がかなり早い時期に芸人を目指して計画的に行動しているという点です。
大学では定番の落語同好会などに所属せず、観客としての立場でひらすら寄席へ通い続けたという点です。
たしかに自らの芸を磨くのはプロになってから幾らでも出来るので、今しか見れない真打ちたちの芸を生でなるべく多く体験しようという考え方は理にかなっている気がします。
そして計画通り、神田松鯉一門に入門してからは、ひたすら自分の芸を磨くことに専念することになります。
下働きが多い前座時代から自分の芸を磨くことを最優先にするという姿勢は、時には脈々と受け継がれてきた伝統にはそぐわないこともあり、実績もない下積み時代から我が道をゆく松之丞の姿を一言で表すと、本人も語っているとおり面倒臭い新弟子以外の何者でもありませんでした。
それでもタイトルにある通り、落語家に比べて圧倒的に稀少な20代の講談師という立場、師匠の温かい人柄もあって前座時代を破門されることなく過ごすことができます。
私には著者が本当の天才なのかを判断することはできませんが、かつて天才と言われた人たちには多少なりとも変人扱いされてきた過去があり、たとえば志ん生は常軌を逸しているかのような半生を送った末に名人と評された師匠なのです。
著者の講談へ対する熱量が充分に伝わってくる内容ですが、自身の芸を高めてゆくだけではなく、真打ちに昇進する前から講談界全体の未来までを視野に入れて客観的に自身の役割を自覚しているという点にも驚きます。
今をがむしゃらに進むだけではなく、長期点な目標へ対して信念を持って進んでいるという点から察すると、今後の講談界は神田伯山を中心に回ってゆく可能性が高いのではないでしょうか。
ちなみに神田伯山ティービィーがYoutubeで開設されており、著者の高座も見ることができます。
さっそく数日にわたって中村仲蔵や畔倉重四郎の全話の高座を見てみましたが、神田伯山という講談師の魅力が少し分かった気がします。
"少し"という表現をしたのは、やはり演芸は生で見てこそ本当の魅力が伝わるものであり、私も近いうちに生で神田伯山を味わってみたいと思いますが、今一番チケットが取りにくい講談師ということもあり、その機会を得ることが難しそうなのが心配のタネになっています。
表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬
最近は作家や専門家だけでなく、芸能人の作品も読み始めています。
深い理由はありませんが、なるべく多くのジャンルの作品に触れてみたいという気持ちと、単純に今まで芸能人が執筆した作品を読んでこなかったからです。
本書は人気漫才コンビ・オードリーのツッコミ担当である若林正恭氏によるキューバ、モンゴル、アイスランドを訪れた紀行文です。
TV、そしてたまにラジオでも著者の声を聴くことがありますが、本人も自覚している通りインドア派でシャイな性格という印象が伝わってきます。
芸能界というきらびやかな、そしてお笑い芸人といえば明るいイメージがある中では珍しい存在なのかもしれません。
肝心の内容についてですが、比較的珍しい国を訪れているもののバックパッカースタイルというわけではなく、極地や治安の悪い危険地帯を訪れたわけでもなく、紀行文として見ると平凡なレベルに留まっています。
しかし本作品の秀逸な部分は、紀行文の中で書かれているエッセイ的な部分になります。
少年の頃より周りの人間との関わりが苦手で内向的な性格を充分に自覚している著者は、自らが生まれ育った場所とは異なる文化を持つ国を訪れることで新しい気付きを得ようとします。
一時期「自分探しの旅」という言葉が流行りましたが、著者にとってこの旅は「自分の外の世界を知るための旅」であり、つまり自分のことしか考えてこなかった著者が、他人との関わり合いによって外界を知り、自分自身の輪郭を再認識する旅だったのです。
本作品の3分の2はキューバを訪れた旅で占められています。
これは著者にとってはじめて1人で出かけた海外旅行であり、社会主義国家でありながらも明るく陽気で気さくなラテン系らしい、ある意味で自分と正反対の性格を持つ人びととの交流が強く印象に残ったからではないでしょうか。
本書を通じて思うのは、とにかく若林氏自身が心境を正直に吐露しているという点です。
それを一言でいえば自身が感じている資本主義・新自由主義という競争社会の中でのある種の生きづらさであり、競争の激しい芸能界に身を置く立場であれば多少なりとも自分を取り繕いたくなるものですが、作品からはそうした"見栄"を一切感じさません。
これはある種の才能といってもよく、それだけに著者に共感し、励まされた人たちも多いはずです。
その代表的な存在であると公言しているのが、あとがきを寄せている音楽ユニットCreepy NutsのメンバーであるDJ松永氏であり、その熱量の高さに驚くとともに、微笑ましい気持ちになれます。
メトセラの子ら
SF小説はその黎明期において、単なる妄想を描いたものとしてその地位が他のジャンルと比べて相対的に低く見られていた時期がありました。
しかし作品の中に最新の科学的知見を取り入れ、綿密なストーリーの作品を生み出すことによってその地位が見直されてゆき、やがて小説として確固たるジャンルを築いてきた経緯があります。
そのジャンル確立に貢献したSF作家の1人が本書の著者であるロバート・A・ハインラインです。
メトセラ(Methuselah)とは、旧約聖書に登場するユダヤ人指導者の名前であり、969歳まで生きたという言い伝えが残っていることから、キリスト教、ユダヤ教圏では長命な人のたとえに使われることがあるようです。
舞台は23世紀頃の地球となり、この頃の人類は金星や火星に移住できる科学力を備えていました。
そして人類の中にはひっそりとハワード・ファミリーと言われる遺伝子的に寿命が極端に長い"長命族"と言われる人たちが、ひっそりと暮らしていました。
ハワード・ファミリーは全人類の中で10万人ほどを占めており、かれらは評議会を頂点とする共同体を運営していました。
評議会における最大の論点は、自分たちが長命で何百年も生き続けることのできる存在であることを世間に公表すべきかと否かという点にありました。
なぜなら周りの人たちと比べてはるかに長生きできる彼らは、普段は一般社会に紛れて生きていますが、年月が経過するにつれ怪しまれないために定期的に移住する必要性があり、その際に身分証明書などの問題も出てきます。
つまり正体を公表した方が暮らしやすくという考えがある一方で、その際に生じるマイノリティへ対しての迫害の方が深刻であるといった考えがあります。
なぜなら彼らの持っているのは、全人類が長い年月を通じて渇望し続けてきた"不死不老"なのです。
しかし評議会で決定が下される前に、時の権力者たちによって彼らの存在が知られることになります。
さらに長命族が遺伝子的に受け継いだに過ぎない特性を、彼らが世間から隠している秘密のテクノロジーを独占しているといった誤解が広がり、マイノリティである長命族たちは人びとのねたみと憎悪の対象して迫害が本格的なものとなってゆきます。
長命族のリーダーが誤解を解くために権力者たちと交渉を行いますが、一度火の付いた迫害の嵐は止めることが困難であることを悟ります。
だた1つ残された道は、人類未踏の大宇宙への旅立ち、つまり新天地を求めての恒星間飛行へ挑戦することになるのです。
ストーリーの前半は長命族のリーダー、そして世俗の権力者たちの駆け引きが政治的に描かれており、ある意味ではSF小説らしくありません。
しかしストーリーが進むにつれ、長命族たちにとって新天地候補となる惑星において遭遇する未知の生命体との遭遇といった王道のSF小説へと移り変わってゆきます。
結末もきわめてSF作品らしいものであり、完成後の高いエンターテイメントとして読むことができます。
個人的に驚いたのは本作品が執筆されたのが、今から80年以上前の1941年であるという点であり、SF界のビッグスリーと言われたハインラインの真骨頂を味わえます。
amazonのすごい会議
本ブログでは、巨大企業アマゾンの末端で働く労働者たちの過酷な現場をルポした作品を紹介しました。
それでもアマゾンが時価総額で世界5位(2024年時点)という規模にまで急成長したという事実は揺るぎません。
著者の佐藤将之氏は、2000年にアマゾンへ入社し2016年まで勤めていた経歴があり、その成長の過程をよく知っている人物です。
そんな著者は日本の会議は総じて効率的、生産的ではないと指摘しています。
私自身、基本的に会議は好きではありません。
それでも多い時には1日に5~6時間の会議がスケジュールされ、とくにオンライン会議が普及した昨今では物理的なスペースを気にすることなく会議へ参加できるようになったため、参加者が多い時には20名以上にもなります。
当然、これだけの参加者がいれば一度も発言しない人が大多数になることもあり、私自身も心の中では他のタスクを消化する時間を奪われるだけの非効率な会議へ毒ついています。
それでもすべての会議を無くすことはできませんし、むしろ場合によっては必要です。
アマゾンでは企業のその規模に相応しく、膨大な数のプロジェクトが同時進行しており、会議もそれに比例して増加してゆきます。
一方でアマゾンは、そうした会議をいかに洗練させてゆくかの試行錯誤を続けてきた企業でもあるのです。
本書ではアマゾンので行われいる会議の具体的なルールやノウハウが紹介されており、以下のような目次から構成されています。
- CHAPTER 0 アマゾンが「減らしたい会議」「増やしたい会議」
- CHAPTER 1 アマゾン流 資料作りのルール
- CHAPTER 2 アマゾン流 意思決定会議
- CHAPTER 3 アマゾン流 アイデア出し会議
- CHAPTER 4 アマゾン流 進捗管理会議
- CHAPTER 5 アマゾンのOLP
- CHAPTER 6 会議をスリム化するヒント
まず意外なのが、アマゾンでは会議資料を簡潔に箇条書きしたものではなく、文章で書く必要があるという点です。
資料が文章で作成されることで、発表者の思考が伝わりやすく、その意図するところの解釈の違いが人によって生じにくくなるというメリットがあります。
また事前に資料へ目を通しておく必要はなく、会議の冒頭で各人がそれを黙読する時間が与えられます。
資料の上限は「1ページ」か「6ページ」に統一されている点も特徴的であり(関連データなどの添付資料はページ数に含まない)、会社にとってどんなに重大な決定事項であってもこのルールに変わりはありません。
続いて会議の目的別に、オーナー(会議の主催者)がそれらを運営するための役割やルールについて言及しています。
確かに報告や意思決定を行うための会議と、新規事業のアイデアを生み出す会議ではやり方が違って当然となります。
最後のほうでアマゾンの価値観を表した14カ条かなるOLP(Our Leadership Principles)が説明されています。
これはアマゾンの全社員が共通して持っておくべき価値観のことであり、これに則って会議も洗練されてきたのです。
つまり闇雲にアマゾン流会議のルールを自社へ取り入れてもうまくは行かず、その背景にある考え方を理解した上で行う必要があるのです。
このOLPは誰にでも公表されており、Webページで参照することができます。
ビジネス書の中ではかなり具体的で実践的な内容であり、世界的な企業の取り組みの参考として一度は目を通しておいて損はないと思います。
十六の話
司馬遼太郎氏の評論、追悼文、さらには講演内容を1冊にまとめたものです。
テーマは本職の歴史はもちろん、宗教、思想・哲学、美術から人物評、さらには環境問題など多岐にわたり、普通は代表的なものから本の表題を付けるのですが、著者自身も迷った末に掲載されている作品の数を単純にカウントして「十六の話」と名付けたようです。
本書に掲載されている作品は以下の通りですが、文庫版は付録として著者と井筒俊彦氏の対談が収録されています。
- 文学から見た日本歴史
- 開高健への弔辞
- アラベスク -井筒俊彦氏を悼む
- "古代史"と身辺雑話
- 華厳をめぐる話
- 叡山美術の展開 -不動明王にふれつつ
- 山片蟠桃のこと
- 幕末における近代思想
- ある情熱
- 臨海丸誕生の地
- 大阪の原形 -日本におけるもっとも市民的な都市
- 訴えるべき相手がいないまま
- 樹木と人
- なによりも国語
- 洪庵のたいまつ
- 二十一世紀に生きる君たちへ
司馬氏は1996年に亡くなりますが、本書は最晩年に近い1993年に発刊された本であり、この頃は小説の創作活動から離れてエッセイや批評の執筆が中心となっていました。
それだけに本書の内容はどれも長年の作家人生の中で養われた知識や経験の集大成といえる内容であり、読み応えは充分です。
歴史といえば年表と出来事、そしてそこに登場する人物を順番に暗記してゆく教科だと思っていましたが、私にとって歴史の面白さを教えてくれたのが司馬遼太郎という存在でした。
実際に作品を読むと、歴史上の人物たちが生き生きと描かれており、読者の胸を躍らせると同時に、過去の出来事を不思議と新鮮な感覚で読ませてくれる魅力があります。
本書では次のように語っています。
歴史とはなんでしょうか、と聞かれるとき、
「それは、大きな世界です。かつて存在した何億という人生がそこにつめこまれている世界なのです。」
と、答えることにしている。
私には、幸い、この世にたくさんのすばらしい友人がいる。
歴史の中にもいる。そこには、この世では求めがたいほどにすばらしい人たちがいて、私の日常を、はげましたり、なぐさめたりしてくれているのである。
歴史上の人物に関する記録などを読み漁り、現地を訪れて取材を続けているうちに、次第に彼らが著者にとって友人のような身近な存在になってゆくのであり、著書を通じて読者たちへも同じような感覚をもたらせてくれるのです。
著者は自嘲気味に自身を第二次世界大戦の敗残兵であると言っていますが、20世紀が終わろうとしている当時、国家間で発揮するエゴ、つまり戦争を最大の懸念事項として考えていました。
そして残念ながらその懸念はウクライナや中東で現実のものとなりつつあります。
本書ではその本質を著者らしく次のように表現しています。
「あの国は、ひとびとはすばらくいい。だが、国家としてはじつにいやな国だ。」
という言い方を、しばしばききます。
近代国家というものは、自国の国民の幸福をもたらす機関として成立し、二十世紀後半になって多くの国家が誕生しました。
こんにち、大小無数の国家が、自国民の利益という二十世紀の神話を守るために、怪物群のように地球上を横行しています。
どの国にとってもその隣国は、悪魔に似ています。なぜなら、隣国は、自国にとって荀子の思想でいうところの、"利己的欲望"しかもっていないからです。
とはいえ、世界中の叡智を集めたところで決して無くならないのが戦争でもあります。
著者は"壊れた地球"を子孫へ相続させないために、かぼそい可能性ながらも国家やイデオロギーを超えた影響力のある思想が生まれてくることが必要だと考えていたようであり、長年にわたり歴史を身近に触れてきただけに、その難しさを誰よりも実感していたに違いありません。
事故物件、いかがですか? 東京ロンダリング
前回紹介した原田ひ香氏による「東京ロンダリング」の続編になります。
前作は連続性のある1つのストーリーでしたが、本作品は8篇の短編から成り立っています。
前作からの続編という面を持ちながらも、短編1つ1つが独立した物語という不思議な1冊となっています。
告知義務のある事故物件に住むことでロンダリングを行う人たち、そしてそれに関係する人たちを描いているという点では共通しています。
物件のロンダリングに関わる人を作品中では"影"と呼びますが、この職業自体が作者の創造によるものです。
一方で高齢化、独身の割合が増え続けている社会情勢を鑑みると今後、ますます孤独死が増えていくことが予想され、かなり現実味のある設定のように感じます。
作品中においては物件をロンダリングする"影"の知名度は低く、関係者以外に世間には知られていません。
短編の主人公は事故物件の大家さん、ロンダリングの仕事をしている同僚を持つ会社員、人生に行き詰まり新たにロンダリングの仕事を斡旋された男女、またロンダリングを斡旋する側の業者、さらには失踪した人を探すことを専門をしている業者などが登場します。
その中には前作の主人公であるりさ子も登場し、相場不動産の人たちも同じように登場するため、前作を読んでおいた方がより楽しめるという点は間違いありません。
物件ロンダリングという仕事そのものよりも、この仕事を通じて生まれてくる人間ドラマが作品の中心になっています。
それと同時に大都会東京において、たとえばそれぞれの事情で家庭を飛び出したり、1度社会のレールから外れてしまった人が抱える生きづらさという社会構造を鋭く観察しているという点も特徴になっています。
どの分野の小説であれ、人間社会の抱える諸問題と何らかの接点を持たない作品は読者の共感を得ることができないと言う点は今も昔も変わりません。
本作品はこうした問題への冷静な観察眼、そして問題を抱えてしまった人たちを暖かく見つめる視点がストーリーや場面によって書き分けられており、読者を共感とともに引き込んでくれる魅力があります。
冒険家の角幡唯介氏は、現代日本はシステムが整備され、かつ街が清潔になっていったことで、そこに住む人びとが"死"というイメージから遠ざけられた状態で日常生活を送っているという主旨の発言をしていました。
こうした風潮が、かつて人が病気や事件によって死んだ場所を極端に忌み嫌うといった感情を生み出している原因になっており、個人的には確実に増え続けている"事故物件"という存在を改めて考えさせてくれるきっかけにもなった作品です。
東京ロンダリング
本ブログでも何冊か紹介している原田ひ香氏が2011年には発表した作品です。
ロンダリング(laundering)には洗浄、洗濯という意味がありますが、"マネーロンダリング=資金洗浄"というマイナスイメージのある言葉にも使われます。
宅建業法上の告知義務として、賃貸物件の契約者へ対して過去に人の死があった物件の告知義務があるそうです。
いわゆる"事故物件"である事実を伝えなければならないという法律らしいですが、これは事故があった直後にその物件に住む人が対象となるらしく、いわゆる2人目以降の人には告知義務は発生しないようです。
そこで大家の要請に応じて、事故物件に1ヶ月だけ住んでその物件をロンダリング(洗浄)する人たちを描いた作品です。
世界有数の大都市である東京では、人知れず借りている部屋で事故や事件で死を迎える人もそれなりの数に昇り、いわゆる"孤独死"として報道される機会も多い社会問題です。
しかもこうした孤独死は近隣へ漏れる匂いによって気付かれる、つまり死後一定の時間が経過してから発見されることも多く、こうした部屋の原状回復を専門に行う特殊清掃業者が存在します。
一方で事故物件に1ヶ月だけ住んでロンダリングする人たちというのは著者が本作品を執筆するために考え出した職業であり、著者が社会問題に関心を寄せ鋭く観察していることが分かります。
作品中でロンダリングをする人たちは事故物件に1ヶ月だけ住み、次々と事故物件を転々として暮らすことを生業としています。
ロンダリングの報酬として家賃は無償、そして1日あたり5000円が支払われ、それを斡旋する相場不動産が作品のおもな舞台となります。
主人公はりさ子という30過ぎの女性であり、離婚して家を飛び出し住む場所を失って途方に暮れていたところ、偶然にもロンダリングの仕事に就いています。
仕事を紹介した相場社長は、ロンダリングという仕事の秘訣を次のように説明します。
「いつもにこやかに愛想よく、でも深煎りはせず、礼儀正しく、清潔で、目立たないように、そうしていれば絶対に嫌われない」
つまり近所から怪しまれない程度の振る舞いをしつつ、目立たないままロンダリングの期間(1ヶ月)を過ごすということですが、控えめで地味な性格のりさ子にとっては天職といえるほどぴったりとハマります。
しかし事故物件にはそれぞれ個別の事情があり、りさ子が望む平穏無事な生活を脅かすようなトラブルが起きるのです。
事故物件でトラブルが起きるといっても、本作品はホラー小説ではなく、心霊現象などを扱っている訳ではありません。
それはあくまでも生きている人間が引き起こすトラブルであり、著者が創造したロンダリングという仕事を通じて描かれる人間ドラマが見どころになります。
この架空のロンダリングという仕事は現代社会においてかなりリアリティがあり、読み進めてゆくと本当にこうした仕事があるのではないかという錯覚を抱いてしまうほどストーリー構成がしっかりとしています。
現代社会らしい題材を扱いつつも物語はどこか昭和っぽさを感じさせるのは、相場不動産が多くの若い世代が暮らしつつも、雑多な下町的な雰囲気の残る高円寺を舞台にしていることも関係していると思います。
結果としてあらゆる世代が楽しめる作品に仕上がっており、是非一読して欲しい1冊です。
麻雀放浪記 4 番外篇
第4巻は1~3巻とストーリーに連続性があるものの「番外編」と銘打たれています。
それは主人公である坊や哲が博打で生計を立てるバイニン(麻雀玄人)から足を洗い、完全に勤め人へ転身してからのストーリーだからです。
昭和30年も近くなると日本は戦後の復興が進み、同時に治安が良くなるにつれ堂々と違法である賭博をする雀荘も減ってきました。
さらに手軽に楽しめるパチンコが大流行したことにより、麻雀そのものが不況になってゆきます。
そこへ重なるように哲は栄養失調で入院してしまい、実家に戻ったのを機にサラリーマンとして再出発することになります。
それでも彼はまだ幸運だったといえます。
敗戦後の混乱期にごろついていた仲間(博打打ち)の大部分は、体を壊して寝たきりになったり、貧窮の中で消息不明となっていったのです。
このようにバイニンたちが活躍する余地は殆ど残されていない状況でしたが、本巻ではそれでも麻雀で生きていゆくことを止めない人たちが登場します。
1巻目から登場しているドサ健は戦後間もなくから活動し、今でもバイニンとして生活している稀少な1人ですが、本巻では李億春という新しい登場人物も登場します。
彼は無国籍者であり、つねに黒い手袋をしていますが、それは勝負に負けて、あるいはイカサマがバレたことにより殆どの指を失っているからであり、哲は李のことを生きるということに関してまったく無責任だと評しています。
勤め人となり守るものが増えた哲にとって、李の生き方は、そこにかつての自分を見出してしまうような存在として描かれています。
哲たちはふとした偶然から、強引な手法で都内の雀荘を乗っ取る(今は使われない言葉ですが)三国人たちの組織と麻雀勝負をやることになります。
もちろんイカサマ何でもありのルールで、そこではある意味で自分の持てるテクニックや勝負感をすべて賭けた真剣勝負が繰り広げられます。
イカサマがバレれば時に死ぬほどの制裁を覚悟しなければなりませんが(実際に作品中でガスという麻雀打ちはイカサマがバレて刺殺されてしまう)、相手のイカサマ技を見抜くことができなければ、それは見抜けなかった方が悪いという弱肉強食の世界であり、足を洗ったはすの坊や哲も面子の1人としてその卓に座ることになるのです。
本巻での主人公は、現役バリバリの"坊や哲"としではなく、元バイニンとして1歩引いた目で周囲のバイニンたちを観察しているような描写が印象的です。
物語の最後は、田舎町まで逃れてきた彼らがそこまでも相変わらず麻雀を打ち続けるというシーンですが、その結末はどこか物悲しい小説作品らしい終わり方になっています。
麻雀放浪記 3 激闘篇
昭和27年、本作の主人公である坊や哲がバイニン(麻雀玄人)となって7年の月日が流れましたが、彼ら博打打ちは1晩でサラリーマンの月収を超える金を手にすることもあれば、同時に失うこともある稼業です。
彼はその世界では名前を知られるようになりましたが、相変わらず着たきり雀であり、家もないため雀荘で仮眠ととるか道路や山手線の車中で寝ているような生活を送っていました。
さらには洗濯や入浴といった習慣もなかったため、外見だけを見れば浮浪者と何ら変わりない状態だったのです。
戦後直後ならまだしも焼け野原だった東京は着実に復興を進めていき、バラック小屋や闇市、そこで屯していた怪しげな人間たちも姿を消しつつありました。
一般人にとっては治安や衛生環境が良くなるという意味で歓迎すべき状況でしたが、戦後の混沌が収まってゆくにつれ違法賭博を生業にするバイニンたちにとっては確実に住みにくい世の中へと移行しつつあったのです。
さらにこの頃から麻雀という遊興が一般に普及してゆき、麻雀賭博を生活の糧としてイカサマ何でもありというバイニンたちの数は次第に減っていったのです。
一方で彼らの代わりに登場してきたのが、スマートな麻雀を打つ次世代雀士たちがであり、彼らは本職を別に持ちながらも賭博麻雀を趣味の範囲で楽しむことをモットーとしていました。
つまり副業で麻雀をやっている人たちです。
少なくとも全財産を(時には命までも)賭けるような麻雀は行わず、彼らを近代的なスタイルとするならば、坊や哲やかつて彼とコンビを組んだことのあるドサ健たちのスタイルは古臭いものになってきたのです。
そんな中、坊や哲は長年の麻雀のやり過ぎが祟ったのか右肘を痛め、イカサマを使うことが難しい状況にあり、行き詰まった末に地下組織から高利な金を借りて麻雀で返すといった危うい生活を続けていました。
彼は組織に所属せず一匹狼として生きてゆくことをモットーとしてきましたが行き詰まり、偶然の縁から会社勤めをするようになります。
しかしその会社の社長が賭博好きであり、次第にその腕を認められた坊や哲は、その会社を中心に、つまりある意味で組織に属しながら麻雀を続けることになるのです。
もっとも麻雀の徹夜勝負で無断欠勤などしょっちゅうという有り様でしたが、賭博麻雀における社長の右腕として重宝されいたためクビになることもなかったのです。
やがて社長の別宅で新しいスタイルの麻雀打ちたちと大きな勝負をすることなるのですが、ここからは読んでのお楽しみです。
坊や哲が厳しい勝負を繰り広げるという点では今までのストーリーと同様ですが、やがて自分のような昔ながらのバイニンが生きる世界が無くなるという予感を抱きつつ麻雀を打っている点が大きく異なります。
勝負に疲れた坊や哲は、もうろうとする意識の中で自嘲気味に、同じ昔からのバイニンであるドサ健へ対して心の中でこうつぶやくのです。
世間の人は、暮らしていくことで勲章を貰うが、俺たちは違う。
俺たちの値うちは、どのくらいすばらしい博打を打ったができまるんだ。
だからお前も、ケチな客をお守りして細く長く生活費を稼ごうなんてことやめちまえよ。 麻雀打ちが長生きしたって誰も喜びはしねえよ。
麻雀放浪記 2 風雲篇
第1巻では終戦直後の昭和20年の東京の焼け野原に立つドヤ街を舞台に、主人公である坊や哲がバイニン(麻雀玄人)として1人立ちするまでのストーリーが描かれていました。
第2巻では昭和26年から始まり、バイニンを続けていた坊や哲がヒロポン中毒者になり、自暴自棄な生活を送るというショッキングな場面から始まります。
ヒロポン浸けのため普通の生活を送れなくなり、その影響でイカサマ技が相手にバレて袋叩きにされるなどして東京に居場所が無くなってしまいます。
さらに逮捕までされてしまい、幸いにも豚箱生活でヒロンポン中毒から立ち直った坊や哲は、ふとしたことから知り合ったクソ丸(博打好きの禅僧)、ドテ子(クソ丸と一旧知の博打好きの女性)と連れ立って大阪へ逃れるように旅立つのです。
ただその移動手段である夜行列車でも賭博が行わており、終戦から復興までの日本の混沌とした様子が伺われます。
信じられないかもしれないが、その頃、警察の眼をのがれるために貸元が団体を作って客車をひとつ貸し切り、夜じゅう、賭場にしたことがあった。
むろん車掌の眼には触れないよう両側の客車に立番をおいておく。
当時の関西では関東とは違ったルールで行われるブウ麻雀が盛んな地域であり、ルールの細かい説明は省きますが、簡単に言えばせっかちと言われることの多い関西人らしく短時間で勝ち負けをつけることのできるルールです。
このブウ麻雀で勝つコツは大きな手を作るのではなく、とにかく早くアガることのようです。
やはりと言うべきか、関西にも東京と同じく一癖も二癖もあるバイニンたちが登場し、いわば剣豪を目指す若者が諸国で武者修行を続け、他流試合を繰り広げるかのような展開が楽しめます。
大阪、神戸のバイニンたちと勝負をしてきた坊や哲が関西での最終決戦の場所にしたのが京都の大恩寺です。
寺銭(テラ銭)という言葉が今でも残っていることから分かる通り、江戸時代には寺社の境内で賭博が行われることが多く、賭場でのアガリの一部を場所提供代として寄進してきた歴史があります。
博打好きの老師が密かに開催している麻雀というと独特の雰囲気がありますが、そこでの勝負の結末は意外なものとなります。
詳しくは読んでからのお楽しみですが、勝負における博打打ちの非情さ、したたかさ、そして時には遊び心を垣間見ることができます。
麻雀放浪記 1 青春篇
1969年(昭和44年)に発表された作品ですが、文庫本として発刊され続け、ひと昔前の麻雀好きであれば必読の書と言われた小説です。
私自身は学生時代に麻雀をしていた時期がありましたが、社会人になってからは牌を触る機会も無くなり、たまにゲームで遊ぶ程度のため熱心な麻雀好きとは言えないかも知れません。
また本作品を原作の一部として取り入れた漫画「哲也-雀聖と呼ばれた男」は学生時代に読んでいた好きな作品であり、本書を楽しみに読み始めました。
舞台は終戦直後、焼け野原の上野のドヤ街の一番奥にあるバラック小屋で行われるチンチロ賭博からはじまります。
主人公は著者自身、つまり阿佐田哲也(通称:坊や哲)であり、彼は戦争中は軍需工場で勤労動員として働いていましたが、ふとしたきっかけで博打打ちの道へ足を踏み込むことになるのです。
今でも何かと話題になるギャンブラーと本作品に登場する博打打ちでは本質的に違うところがあります。
それは麻雀博打であれば、それは"積み込み"や"すり替え"、"ぶっこ抜き"、"コンビ打ちの通し"(サイン出し)といったような不正行為をためらわずに実行する点です。
彼らはこうした技を他人に見破られないようなレベルにまで磨き上げ、地道な努力で自分の思った通りのサイの目を出す技術を習得したりします。
たとえイカサマをしても玄人の博打打ち同士であれば、それを見破ることをできなかった側が悪いのであり、とにかく勝つことが絶対正義という弱肉強食の世界です。
こうした混沌とした独特の世界の中で坊や哲は"バイニン"(麻雀の玄人)として頭角を表していきますが、彼の前には年季の入った化け物のようなバイニンたちが登場して作品を盛り上げていきます。
本作品では文章の中に配牌や手牌がフォントとして印刷されているため、麻雀のルールを知らない人にとってはとっつきにくいかも知れませんが、逆に麻雀好きであれば手に取るように対戦の模様を知ることができます。
よく年配の人たちがやっている健康マージャンとは対極の世界観であり、勝負に負けて全財産どころか身ぐるみを剥がれて路上に追い出される人、徹夜麻雀で集中力を保つためにヒロンポンを常用する人など、登場人物はほぼ例外なく破滅型の人生を送っている人たちばかりです。
坊や哲自身もやがて家出をして、タネ銭(博打に参加するための資金)以外は使い果たして路上で寝起きするという生活を送っています。
本作品は完全なノンフィクションではないものの、著者自身の経験を元にして構成されたものだといいます。
一見すると治外法権といえるこの世界にも存在する暗黙のルール、バイニン同士の勝負の様子などがリアルに描写されており、多くの読者がこの独特の雰囲気を持つアウトローな世界に引き込まれた理由がよく分かります。
アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した
作家やジャーナリストが現場に潜入して書き上げたルポタージュは本ブログでも何冊か紹介していますが、海外版は読んだことがありませんでした。
日本での潜入ルポとしてもっとも古い部類に入るのが、鎌田慧氏による1972年にトヨタの期間工として潜入取材を行った「自動車絶望工場」であり、本ブログでも紹介しています。
一方ジャーナリズム発祥の地であるイギリスでは、19世紀頃からたとえば貧民街へ潜入してどん底の暮らしを送る人々を取材した作品が発表されており、その歴史の長さに驚かされます。
本書はイギリス人ジャーナリストであるジェームズ・ブラッドワース氏による潜入ルポです。
タイトルにアマゾン、ウーバーとありますが、実際にはこの2つに加えて訪問介護、コールセンターでの潜入取材も本書に収められています。
これらの仕事に共通にするのは、イギリスにおいて最低賃金、もしくはそれに近い賃金での労働という点です。
また同時にイギリスではこうした仕事における「ゼロ時間契約」が問題になっています。
これを簡単に説明すると、定まった労働時間がなく、仕事のあるときだけ雇用者から呼び出しを受けて働く契約のことであり、基本給という概念がなく、何かの事情で働く時間を減らされたり、病気などの欠勤に対して何の保障もない、不安定な生活を送る労働者を増加させる大きな要因になっています。
たとえば病気によって1週間寝込んでしまうと、家賃を払えず簡単にホームレスとなってしまう境遇にある労働者たちが多いのです。
ジャーナリストという立場から政府の政策を検証し、その数値を上げながら批判することも可能でしたが、著者は最低賃金で働く労働者たちの生活の一部を実際に体験し、彼らの声を直接聞く"血の通った取材"を望んで本書を書き上げたのです。
本書を読み進めると、著者自身の体験はもちろん、同じ職場やそこに住む人たちにも積極的にインタビューを実施しています。
かつてはリゾート地として、または鉄鋼産業で繁栄した町から雇用が失われ、活気が失われてしまった様子を古くからの住人から取材したり、ルーマニアからの外国人労働者たちとルームシェアしその生活を観察したりと、数字からは見えない当事者たちの切実な声が多く掲載されています。
一番最後に著者が経験したウーバーについては他とすこし毛色が違い、ギグ・エコノミー(Gig Economy)といった新しい経済概念のなかで働く人びとの姿が見えてきます。
ギグ・エコノミーとは、インターネットを通じた単発の仕事でお金を稼ぐといった働き方のことであり、時間に縛られず自分な好きなときに好きなだけ働くといった新しい労働スタイルです。
そこで働く人たちは、従業員としてではなく個人事業主として雇用主(本書ではウーバー)と契約することになります。
実際、こうしたフレキシブルな働き方に憧れて飛びつく人たちは多いようですが、現実的にこうした仕事によって安定した生活基盤を築くのが容易でないことが分かります。
個人事業主といっても、それを事実上支配しているのはスマホにインストールされたアプリケショーンからの指示であり、監視であるのです。
つまりこうしたサービスを提供する企業が作ったアルゴリズムが労働者たちを支配しているのであり、業務内容について個人事業主たちに自由な差配の余地や賃金の決定権などは存在しないに等しいのです。
総じてイギリスで起こっていることは日本でも起こっていることですが、さまざまな制度において効率化や民営化が進んでいるイギリスの方が、より厳しい現実に晒されているイメージを抱きました。
ただしこうしたイギリスの殺伐とした労働者を取り巻く環境が、数年後の日本に訪れたとしてもまったく不思議がない状況です。
さらに言えば、こうした問題はグローバル化された世界中で起こっている現象であり、「一生懸命に働く人たちが人並みの生活を送ることができる自由」という当たり前のような権利の実現がいかに難しいかを実感させられる1冊でもありました。
潜入ルポ アマゾン帝国の闇
アマゾンといえば世界最大のショッピングサイトとしてあらゆる分野の商品を取り扱い、翌日、早ければ当日中に商品を届けてくれるインターネットを利用している人であれば誰もが知っている企業です。
さらに月額(または年額)でアマゾンのプライム会員になると配送費が無料となる上に、映画・TV番組が見放題のPrime Videoが利用できるなど、ほかにも多くの特典が用意されています。
アマゾンの提供しているサービスはそれだけでなく、おもに企業向けにAWS(Amazon Web Services)というクラウドコンピューティングサービスを提供しており、世界中の著名な企業がAWSのユーザであり、この分野でも世界一のシェアを持っています。
私自身もかなり前からプライム会員に加入済みでインターネットで何かを購入する際には、まずはアマゾンで検索する習慣が付いており、その便利さを日々実感している1人です。
アマゾンは「地球上で最もお客様を大切にする企業」を目標として掲げており、そのユーザーは世界中に20億人以上いるというから驚きです。
本書はノンフィクション作家である横田増生(よこた ますお)氏が、帝国というにふさわしい規模を持つアマゾンの闇を取材した1冊です。
まず手始めとして著者はルポ取材の王道としてアマゾンの巨大物流センター(巨大倉庫)にアルバイトとして潜入します。
日本にいくつかあるアマゾンの巨大倉庫の中でも、東京ドーム4個分という床面積を持つ日本最大の小田原郊外の倉庫でピッキング作業を経験する著者ですが、1日で2万5千歩、約20kmの距離を歩くというから驚きです。
若者であってもかなりの運動量であり、年配者にとっては過酷な仕事量といえるでしょう。
しかも作業従事者はハンディ端末の指示によって秒単位で管理・監視され、その実績はすべて数値となって集計され続ける仕組が導入されています。
詳細は読んでからの楽しみですが、あまりに殺伐とした職場であり、ネットの情報だと現時点で1300~1500円ほどの時給でアルバイト募集されていますが、個人的には倍の金額をもらっても働きたくないと思ってしまいました。
続いてアマゾンで注文された商品を配送する宅配ドラバーたちの現状にも迫っています。
著者はヤマト運輸のセールスドライバー、アマゾンと契約する中小の宅配業者であるデリバリープロバイダのドライバに同乗する形で取材に挑みます。
ドライバーたちの仕事量も倉庫でのピッキング作業に劣らず過酷な内容で、ニュースにもなっている物流問題を凝縮したかのような内容になっています。
さらに著者は日本の問題と比較するためにイギリス、フランス、ドイツでも取材を行いますが、そこでも日本と同じ問題が起こっていることが分かってきます。
ほかにもマーケットプレイスへ出店している事業者、フェイクレビューを募集している違法業者、AWS事業の現場などを精力的に取材しています。
読み進むにつれ、普段利用しているアマゾンを支えている裏方の人たちの苦悩が次々と紹介されてゆき、かなり複雑な気持ちになってゆきます。
一方で、小売、物流、製造、医療、福祉、出版、サービス業などあらゆる業種で同質の問題が潜んでおり、本質的には行き過ぎた資本主義の抱える共通の問題であることも分かってきます。
私自身も徹夜で働くことも当たり前であったブラックな環境にいた経験がありますが、彼らの苦しい状況に共感できる部分がありました。
ほかにもアマゾンを創業したジェフ・ベゾスの生い立ちからその考え方を考察したり、アマゾンが世界中で行っている租税回避の取り組み、アマゾンが出版業界へもたらした影響なども取材されており、かなり広範囲に渡って精力的に取材を行っています。
先ほど書いたように本書に書かれている問題はあらゆる業種で共通の問題なのかも知れませんが、時価総額で世界5位の規模を誇るというアマゾンという巨大帝国を精力的に取材した本書は、その代表例といえる内容であり、社会や企業の仕組みの抱える問題を知る上でも読む価値のある1冊です。
浅草ルンタッタ
お笑い芸人である劇団ひとり氏が執筆した小説です。
著者が2006年に発表した処女作「陰日向に咲く」、続いて2010年に発表した「青天の霹靂」を本ブログで紹介してきましたが、本作品は2022年に発表された最新作ということになります。
今までの2作品は現代を舞台にした作品でしたが、本作品は大正時代初期の浅草で物語が繰り広げられれます。
読み始めてすぐに気付いたのは、今までの作品と違い、かなり入念に下調べをしてから作り上げられた作品であるという点です。
当時の浅草の風景や地理、遊郭や芝居小屋の様子などが細かく描写されており、より本格的な設定が取り入れられた作品という印象を受けました。
ただし本作品の登場人物たちは従来の作品同様に、不幸な生い立ちを持っていたり、社会の片隅で暮らしている人たちという点では共通しています。
舞台は浅草に当時流行ったという(政府公認の遊郭である吉原とは違い)非合法な売春宿の1つである燕屋です。
そこで娼婦として働く女性たち、そしてその店の前の往来で捨てられ燕屋で育てられた孤児、加えて店を取り仕切る元締めたちがおもな登場人物です。
ネタバレしない程度に内容を紹介すると、拾われた女の子は"お雪"という名前を付けられ、かつて子を失った経験を持つ千代をはじめとした遊女たちによって育てられてゆきます。
お雪は学校には通わないものの、賑やかな燕屋という特殊な環境の中でそれなりに順調に育ってゆきます。
身寄りのない子どもを同じく身寄りのない大人が育てるというストーリーは、どこか人情噺のような温かさがあります。
しかしちょっとした出来事が大きな事件へと発展してしまい、さらに大正12年に起きた関東大震災によってストーリーが大きく動き出すことになります。
そのためお雪は母親と慕う千代と別々に暮らさざるを得ない状況へと陥ってゆくのです。
物語の中心に親子の絆というテーマがありつつも、かつて日本の芸能の中心地であり、今なおその面影を残す浅草という街を舞台としている点も著者の強いこだわりを感じます。
おそらく浅草以外の街を舞台に同じテーマの作品を描いたら、まったく違うストーリーになってしまうのではないでしょうか。
ストーリの流れに落語の人情噺、あるいは講談のような雰囲気を感じてしまうのは、やはり著者が芸人であることが関係しているように思えます。
作品としての完成度、スケールの大きさという点では本作品が最も優れており、着実に作家としての技量を身に付けつつつある劇団ひとり氏の作品が今後も楽しみになる1冊です。
青天の霹靂
デビュー作「陰日向に咲く」に続いてお笑い芸人である劇団ひとりによる小説を手にとってみました。
デビュー作が2006年、本作品が2010年に発表されていることから著者にとって4年ぶりの作品というこになり、専業作家が1年に複数作品を発表することも珍しくないことを考えると、かなり時間が空いています。
本書を読み進めてすぐに気付いたのは、デビュー作品と比べてかなり文章が洗練されている点です。
一方で作品の内容は、現状に不満を持つ主人公が過去にタイムスリップするという小説としてはありがちな構成であり、デビュー作で見られた勢いはやや影を潜めている印象を受けました。
本作品に登場する主人公はマジシャン(手品師)という設定であり、著者の職業であるお笑い芸人と共通しており、かつ作品発表当時(2010年時点)での主人公の年齢も著者とまったく同じに設定されています。
主人公(轟 春夫)は場末のマジックバーで働いている独身の売れない芸人という設定で、主人公が"社会の落ちこぼれ"という点では、デビュー作品と共通している点です。
芸人には大別すると、"売れてスターになった芸人"と"いつまでも売れない芸人"の2種類があり、おそらく後者である日の目を見ない芸人が圧倒的に多い世界であるはずです。
つまり芸人になるような人間はロクでもないという世間の価値観を前提に、著者の視点はつねに売れない芸人へと向いており、かつその目線はとても暖かいということです。
ちなみに迂闊にも作品の終盤になってから、以前、本作品が映画化された同名の作品を見たことあることに気づきました。
作品自体は心温まる感動のストーリーであり、作品の完成度としては確実にデビュー作品を上回っています。
オリジナリティのある特筆すべき作品ではないかも知れませんが、エンタテインメントとして読者を楽しませてくれる作品です。
陰日向に咲く
お笑い芸人である劇団ひとりが2006年に発表したデビュー作となった小説です。
私自身は頻繁にTV番組を見ているわけでなく芸人に詳しい訳ではありませんが、時々見ている番組の中にテレビ東京で放映されている「ゴットタン」があり、司会の1人として活躍しているだけに著者のことは昔から知っています。
一方で日常的に読書をしていると、エッセイは別として本職の作家が執筆した小説作品を読むことが多く、あまり芸能人による小説は読んできませんでした。
ふと思い立って発表されてから随分と時間が経ってから本書を手にとってみました。
本作品は6人の主人公が登場するオムニバス小説として構成されています。
いずれの主人公にも共通するのは、社会の落ちこぼれであるという点です。
その落ちこぼれ方はさまざまであり、ホームレスに憧れ社会人をリタイアしたり、アイドル好きが高じて給料の殆どを貢ぐオタク、自分に自信を持てない二十歳の女性、ギャンブル狂いの中年男性、酷い家庭事情が理由で家出した少女などが登場します。
あえて社会からの落ちこぼれを主人公にする点に、著者の芸人らしい人間観察の特徴が現れている気がします。
率直に言うと、お笑い芸人の作家デビュー作品ということもあり、文章力や作品の構成力には専業作家には及ばない点が見受けられます。
一方で作品全体からはデビュー作ならではの意欲や勢いが感じられ、個人的には小説作品というより演劇の台本、または映画の脚本のような印象を受けました。
小説へ対して綿密な作り込みを要求する読者にとっては物足りなさを感じる内容かも知れませんが、エンターテイメント作品として読む分には充分に成立していると思います。
私個人はTV番組で拝見する著者らしさが発揮されている、つまり個性がしっかりと出ている作品であり、いわゆる無難な小説になっていない点は評価できます。
スマホ脳
著者のアンデシュ・ハンセン氏は、スウェーデン人の精神科医です。
本書は世界中で爆発的に普及したスマートフォン(スマホ)が、人体にもたらす深刻な影響を専門家の立場から解説した本です。
はじめスウェーデンで発売され、人口1000万人の同国で50万部のベストセラーになったそうなので、約12倍の人口を要する日本に当てはめると600万部という途方もない数字になります。
つまりスウェーデンでは社会現象になった作品ですが、本書が小説でもエッセイでもなく警鐘を鳴らす啓蒙書だったことを考えると、国中を巻き込んだ社会現象になったことが想像できます。
以前ブログでも紹介した同じくハンセン氏の「運動脳」はスウェーデン国内で67万部を売り上げており、精神科医でありながらスウェーデン1のベストセラー作家であると言えます。
内容はかなり専門的であるものの、世界中で行われた実験、そして医師としての知見からスマホが人間の脳へどのような影響を及ぶのかについて丁寧に分かりやすく解説してくれているため、一般読者でも充分に内容を理解することができます。
- 第1章 人類はスマホなしで歴史を作ってきた
- 第2章 ストレス、恐怖、うつには役割がある
- 第3章 スマホは私たちの最新のドラッグである
- 第4章 集中力こそ現代社会の貴重品
- 第5章 スクリーンがメンタルヘルスや睡眠に与える影響
- 第6章 SNSー現代最強の「インフルエンサー」
- 第7章 バカになっていく子供たち
- 第8章 運動というスマートな対抗策
- 第9章 脳はスマホに適応するのか?
私たち人(ホモ・サピエンス)は、10万年前にアフリカで誕生しまたが、スマホやSNSが本格的に普及したのはここ10年間であり、私たちの脳は未だに狩猟採取を行ってきた時代に最適化されたままだということです。
たとえば命の危険性が迫った際に「逃げるか闘うか」の選択を素早く行うためにストレスや不安が、より生存できる確率を高めるために社会性や好奇心という能力が準備されているのです。
しかしスマホの登場によってそうした能力が誤動作をするようになり、現代社会において精神の不調、不眠症、さらには知能の低下といった事態を引き起こしているのです。
医師らしくそのための解決方法が8章の「運動というスマートな対抗策」で解説されていますが、この部分を詳しく掘り下げたのが先ほど紹介した「運動脳」であり。興味のある人はそちらも読んでみてください。
大きな視点で見ると、インターネット技術の発展の中にスマホの誕生も含まれており、このスマホこそが手軽にインターネットを利用する手段として起爆剤になりました。
今やインターネットなしではショッピングや道案内、天気予報、さらにはニュースすら入手できなくなっている人が増えており、家族や友人とのやりとりも対面よりもネットを通じて行われる頻度の方が多くなっています。
わすか20年足らずという短期間で劇的にわれわれの生活が便利になったという見方ができますが、この"短期間で劇的"という部分に含まれている深刻な副作用が世界中で明らかにされつつあり、本書はすこしでも多くの人がその危険性に気付いてほしいという手引書なのです。
佐久間宣行のずるい仕事術
著者の佐久間宣行氏は1975年生まれでテレビ東京へ入社し、人気番組を手掛ける名プロデューサーとして活躍した後、現在は独立してラジオパーソナリティや演出家として多方面で活躍している方です。
私自身は昔と比べてTVを見る時間はかなり減りましたが、それでも幾つかの番組は見ることがあり、その中には佐久間氏の手掛けている「ゴッドタン」、「あちこちオードリー」といった番組が含まれていることから、彼の名前は以前から知っていました。
一方でTVプロデューサーというと勝手にアクが強く、気難しいといった印象があり、彼も剛腕プロデューサーとして頭角を現したのだろうと想像していましたが、本書には次のような言葉が並んでいます。
「僕はこうして会社で消耗せずにやりたいことをやってきた」どうも勝手に私が抱いていたイメージとは違うようであり、著者が私とほぼ同世代ということもあり気になって本書を入手してみました。
「誰とも戦わわず抜きん出る62の方法」
本書は一般的なビジネス専門書と比べて分かりやすい言葉で書かれており、エッセーのような読みやすさが特徴です。
同時で著者がメディアの最前線において現役で活躍していることもあり、本書で紹介されている方法はかなり具体的で実践的という印象を受けました。
かつてのテレビ東京では"お笑い番組"を扱っていませんでしたが、佐久間氏がそのジャンルをテレビ東京で切り開き、人気番組として成長させるまでの過程を知ることができます。
さらにクリエイターとしての視点だけでなく、プロデューサーとして上司や経営陣との調整方法や妥協の仕方など、多くの会社員にも当てはまる現実的な手法が紹介されています。
著者もかつては先輩たちと真正面からぶつかり、会社を辞めようかなと考えたこともあったようです。
しかしそこで自分自身を見つめ直し、周囲と戦わず自分のやりたいことを実現する方法、つまり「ずるくなる」ことを決心したそうです。
結果としてこの方法はうまく行き、本書を出版するまでに至ったのです。
それでも佐久間氏はかつて仕事でメンタルを壊しかけた経験もあり、そこから「メンタル」第一、「仕事」は第二ということを絶対に忘れてはいけないと主張しており、メンタルケアの方法についてもしっかりと言及しています。
全般的に現実的で合理的なアドバイスが書かれており、「TVプロデューサーという仕事は特殊で、そうした人の仕事術は一般的には通用しない」といった感じはまったく受けず、ビジネス書、自己啓発本としてしっかり成立している1冊です。
熔ける
著者の井川意高(いかわ もとたか)氏は、大王製紙の創業家3代目として40代で社長、会長を務めた経歴を持っています。
井川氏が世間で有名になったのは、100億円以上に及ぶ会社資金をギャンブルへ注ぎ込み、2011年に特別背任に問われて大きくニュースに取り上げられたからであり、私も連日のワイドショーの報道が印象に残っています。
100億円もの大金をすべてギャンブルで溶かしたという報道があまりにも現実離れしており、当時はとんでもなく無能なボンボン社長といったイメージを持っていました。
それから時間が経過し、帚木蓬生氏の「やめられない ギャンブル地獄からの生還」をはじめとしたギャンブル依存症に関する本を何冊が読み、井川氏の起こした事件の顛末にも興味が沸いて本書を手にとってみました。
内容は井川氏が、自らの生い立ちや経歴にはじまり、ギャンブルにはまって逮捕されるまでの一部始終を告白した本となります。
本書は2013年に著者の有罪が確定し、喜連川社会復帰促進センター(いわゆる刑務所)に収監される直前に発売されたものですが、文庫化するにあたり収監中、そして出所後のエピソードが加筆されています。
自伝的な部分では、井川氏の父であり大王製紙の2代目社長でもある高雄氏によって厳しく育てられたこと、また長男として父親の期待に応えようとする強いプレッシャーとストレスを受け続けながらも努力していたことが分かります。
その努力が実を結んで東大へ現役合格し、そのまま家業でもある大王製紙へ入社します。
入社後も父が息子を甘やかすことなく、製紙工場の現場などを経験させ、順調に父の跡取りとして一歩ずつ成長してゆく過程が描かれています。
この時点で私の著者へ対する印象はかなり変わり、彼が甘やかされて育ったわけでもなく、また子会社や不採算部門の立て直しの実績を見ると、無能どころかかなり優秀な経営者だったというのが率直な感想です。
また同時に井川氏がギャンブルへはまり込む過程が、典型的なギャンブル依存症そのものであることも分かってきます。
ギャンブル依存症は精神疾患の一種であり、経営者として正しい判断を下せる状態にあったとしても、ことギャンブルにおいては本人の「意志」では歯止めをかけることは出来なくなります。
大企業の創業一家、また経営者の立場にある井川氏が、パチンコや競馬といったギャンブルで満足できるわけもなく、彼の立場や経済力に見合った場所がマカオやシンガポールのカジノであり、100億円という金額であっただけなのです。
つまりギャンブル依存者として破滅してゆく過程は、平均的収入を持つサラリーマンがパチンコやスロット、競馬などで破産する過程と何ら違いはないということです。
一番気になったのは、ギャンブル依存症の治療を医師やカウンセラーの元で受けたという記述が一切なく、ギャンブル依存が再発しないか心配になってしまいますが、彼が逮捕された後も支援を行ってくれる友人が多く存在し、友人たちの存在が井川氏を立ち直らせたのかも知れません。
ギャンブルへ依存して桁違いの金額と社会的地位を失った人間のドキュメンタリーとして、また自伝としても興味深く読ませてくれる1冊になっています。
俄 浪華遊侠伝
幕末から明治にかけて活躍した大阪の任侠・明石家万吉を主人公にした歴史小説です。
今は講談社文庫から上下巻で出版されているようですが、私は分冊になっていない800ページ以上ある旧版で入手して読みました。
著者の司馬遼太郎といえば戦国武将や維新志士を主人公とした作品が多く、切った張ったの世界で生きる任侠を主人公とした作品は珍しいと思います。
しかしその本作品を読む進めてゆくと、すぐに主人公の万吉が戦国武将に勝るとも劣らない立身出世を果たした魅力的な人物であることが分かります。
万吉は幼少より赤貧の生活を経験し、わずか11歳で家を飛び出て無宿人の身となります。
彼の面白いところは、任侠らしく腕力に物を言わせて相手を屈服させるのではなく、殴られることによって名を高めてゆくことです。
「殴られる、斬られる。この二つに平気になれば世の中はこわいものなしじゃ」
と自らに言い聞かせ、何事にも自分の命を的にして臨んでゆくのです。
たしかに年端も行かぬ少年が、殴られても蹴られても平気でいる姿というのは不気味であり、得体のしれぬ迫力のようなものがあります。
もちろん万吉が名を馳せた理由はそれだけなく、頼まれると断らない侠気があったという点も挙げられます。
正確には侠気というよりも病的なほどのお人好しといった方が正しく、そのために何度も命を落としかねない危機を経験することになります。
そして何といっても面白いのは、この風変わりな任侠である万吉が、幕末の争乱という歴史的な節目に生きたという点です。
当時すでに高名だった万吉は、ひょんなことから武士の身分となり、新選組や長州藩士たちと関わりを持つようになり、鳥羽伏見の戦いにおいては60名の子分たちを率いて幕府方とした参戦する羽目になります。
もちろん万吉自身に佐幕や勤王といった思想はいっさいなく、頼まれて一肌脱いだ結果であり、その軍資金も開帳している賭場から捻出するといった有り様です。
大阪のおもだった博徒の親分たちは勝利した薩長軍によって次々と斬首されてゆきますが、困った人を見捨てられない万吉はかつて苦境に陥った長州藩士を命がけで匿ったこともあり、間一髪で命拾いすることになります。
作品中での軽快な大阪弁でのやりとり、万吉が行くところ何かしらトラブルが起こり、命も金も惜しまないが思慮もすこし足りないところなどは上方漫才を思わせるようであり、作品を読み進めるほどに万吉の魅力に取り憑かれてしまうのです。
幻の韓国被差別民
本作品には"「白丁(ペクチョン)」を探して"という副題が付けられています。
著者の上原善広氏は、自らの出自を被差別部落(同和地区)であると表明していますが、彼はそれをアイデンティティとして、差別を受ける側の立場から見た社会を描くような作品を発表しています。
もちろん表向きでは出自や職業による差別は禁じられていますが、こうした差別意識は現代においてもなお残っており、その代表的なものが日本ではかつて穢多(エタ)と呼ばれた屠畜をはじめとした精肉や皮革産業に関わってきた人びとです。
著者は穢多(エタ)とまったく同じものが隣国の韓国にもあることを知り、5年間に渡る取材を元に書き上げたルポルタージュが本書です。
つまり"白丁(ペクチョン)"とは韓国にける屠畜を生業として歴史的に差別され続けてきた人びとの名称となりますが、本書を読み進めてすぐにその取材が容易なものではないことが分かります。
それは殆どの韓国人が、歴史の授業で白丁とはなにかを知っているが、「現代では白丁は存在しない差別もない」という認識を持っているからでした。
その一番大きな理由として、第二次世界大戦と朝鮮戦争における住民の移動、それに続く1980年代の経済成長による産業構造の変化により、日本における被差別部落というべき明確な地理上の存在が消滅してしまったためだと言われています。
つまり主体的な社会運動により差別が消滅したというより、外的要因により"差別が分かりづらくなった"という現実があり、多くの当事者たちが「寝た子を起こすな」という認識のため、当然のように取材は難航します。
普通であれば取材はそこで行き詰まるのですが、著者は粘り強く取材を続けていきます。
こうした伝統的な差別意識は住民の入れ替わりが激しい大都市よりも、地方の方がより強く残っているはずだとい推測で各地へ出かけたり、専門家やかつて白丁への差別撤廃を目指した団体である衡平社の歴史を調べたりと、さまざまなルートからの取材を試みます。
こうした手がかりを元にして、おそらく多くの韓国人たちが普段は意識していない、いびつな形で残っている差別の現実を明らかにしてゆく過程が本書の醍醐味であるといえます。
はじめはかなり風変わりでニッチな分野の取材をしている作品だなと思いながら読んでいましたが、次第に本書の示唆しているテーマがかなり壮大なものであると気付かされます。
それは被差別部落問題を日本固有の差別問題であると捉えるのではなく、他国と比較することで人間社会の持つ普遍的な問題であると捉えることができるからです。
たとえば欧米で起こっている移民排斥の暴動といった時事的な出来事も、根っこは同じところに起因しているのではないかと思えてくるのです。
鯨の絵巻
吉村昭氏による動物をテーマに扱った短編集です。
著者はおもに歴史小説や戦史小説を発表していますが、時には動物をテーマにした創作小説も発表しており、過去に同様の作品として「海馬(トド)」という短編集を本ブログでも紹介しています。
本書には以下の5作品が収められています。
カッコ内には作品中で扱っている動物を追加しています。
- 鯨の絵巻(クジラ)
- 紫色幻影(錦鯉)
- おみくじ(文鳥、ヤマガラ)
- 光る鱗(ハブ)
- 緑藻の匂い(ウシガエル)
クジラは目立ちますが、それ以外についてはかなり地味な生き物を題材にしている印象を受けます。
ただしどの作品でもあくまで主人公は人間であり、登場する生き物は主人公たちと深い関わりを持っている存在として登場します。
これは「人間と動物との絆」といった性質のものではなく、「人間と自然との関わり」といった、より原始的な関係に近いような気がします。
それは本作品に登場する主人公たちが、人間社会よりも自然との関わり合いの中で暮らしているような印象を受けるからだと思います。
一言で表せば、世間はこうした人間たちを"変わり者"と見ることでしょう。
作品中では主人公たちなぜがこうした人生を選ぶに至ったのかというバックボーンがそれぞれ描かれており、緻密に作られたストーリーが展開してゆきます。
作品中では登場するそれぞれの生き物たちの性質が細かく描かれており、伝統的な鯨漁のやり方、養鯉場の仕事内容、文鳥やヤマガラへの芸の仕込み方、ハブやウシガエルの捕獲方法などが細部に渡るまで描かれており、著者がしっかりと取材や調査をした上で作品を作り上げていることがよく分かります。
とにかくすべての作品の完成後が高く、1つ1つの作品が上質なドキュメンタリー映画を楽しんだかのような満足感があります。
戦史の証言者たち
記録小説と言われるほど正確な記述を実践したことで知られる吉村昭氏ですが、その中でもとくに太平洋戦争を題材にした作品(著者は戦史小説と表現)では、当事者たちへの取材を入念に行い、作品を執筆する上で欠かせない要素でした。
やがて年月を経るにつれ当時の証言者たちが少なくなってゆき、著者は戦史小説を執筆することをやめることになります。
本書はかつて戦史小説を執筆する際に行った、証言者へのインタビュー取材を1冊の本にまとまたものです。
かつて著者のインタビュー取材に応じた9名が証言した内容は以下の通りです。
大宮 丈七
世界造船史に類を見ない巨大戦艦・武蔵の進水を担当した工作技士。
武蔵が長崎で建造されている当時の様子、軍事機密を守りながら世界最大重量の戦艦を進水させるまでの苦心を語る。
連合艦隊司令長官・山本五十六が視察へ赴く途中、P38ライトニング16機の待ち伏せにより撃墜され戦死する。
長官機を護衛し、唯一戦後まで生き残ったパイロットである柳谷氏が当時の出来事を語る。
海軍乙事件において参謀長・福留繁中将が不時着したセブ島でゲリラの捕虜となるが、日本軍との交渉の結果解放される。
この際にゲリラと交渉し、福留繁中将の解放に成功させた大隊長が事件の全容を語る。
海軍乙事件において捕虜の引き渡しを担当した大西大隊長の副官。
ゲリラとの緊迫した交渉過程を語る。
海軍乙事件において福留中将とともにゲリラの捕虜となった二式飛行艇の搭乗員。
捕虜の視点から当時を振り返る。
昭和17年6月10日、瀬戸内海での単独訓練中、沈没した伊号第三三潜水艦。
102名が殉職し、救助されたのはわずか2名であった。
大西氏は救助された2名のうちの1名であり、当時の状況を振り返る。
伊号第三三潜水艦の沈没事故で救助された2名のうちのもう1人。 同じく当時の状況を振り返る。
終戦後、沈没した伊号第三三潜水艦をサルベージした技術者。 海流の早い海域で、巨大な潜水艦を浮揚させるまでの苦心を語る。
浮揚した潜水艦内部を写真撮影した中国新聞記者。 浸水を免れた区画からは13個の遺体が、あたかも生きたままであるかのような状態で発見され、唯一それを撮影することに成功した記者の証言。
本書は1995年に出版されていますが、著者は近い将来に太平洋戦争が明治維新、日清・日露戦争と同じく歴史の一部となることは避けられないことから、取材によって得た当事者の肉声を活字として遺しておく重要性を考え本書を出版したとのことです。
おかげで私たちは本書に登場する証言者が故人となり時間が経った令和の時代においても当時の貴重な証言を読むことができるのです。
海上の道
著者の柳田国男氏は日本民俗学の開祖として著名な方であり、本ブログでもその著書を何冊か紹介しています。
民俗学とは民族のルーツを突き止めることを目的とした学問であり、文献資料だけでなくフォークロア(古く伝わる風習や伝承)を重視するといった特徴があります。
本書「海上の道」は、晩年の柳田氏が取り組んだ研究の論文であり、そのため難解と感じる読者が多いかもしれません。
本書の要旨をまとめると、柳田は日本人のルーツとなった人たち、そして稲作文化が琉球諸島から黒潮に乗って北上し、日本列島各地に広がったという仮説を立てています。
民俗学の難しく、そして面白い点は、冒頭に書いた通り日本各地に残るフォークロアを収集し解析してゆく点であり、その際に史料は必ずしも重要ではありません。
なぜなら史料は時代の勝者、つまり権力者側の視点から書かれた文献であり、そこからは当時の民衆の生活が見えてこないからです。
そのためたとえば日本各地に残る方言から、かつてその言葉が持っていた語源と意味を探ってゆくという気の遠くなる作業が必要になります。
沖縄の方言にはかつて日本人が使っていた古い言葉、つまり大和言葉が多く残っていると言われます。
琉球をはじめとした沖縄地方の歴史を専門で研究する沖縄学という学問がありますが、柳田はそれを日本人全体のルーツを探るためのスケールの大きな研究として取り組みます。
現代でも宮中祭祀として執り行われている大嘗祭、新嘗祭といった行事のルーツ、琉球人たちがはるか南に存在すると信じていた楽園ニライカナイと本州の仏教思想と結びついて同じくはるか南に存在する浄土とされた補陀落(ふだらく)を結び付けて考察するといった試みが行われています。
本書の解説を大江健三郎氏が行っているのも興味深い点です。
ご存知のように大江氏は小説家であり、専門家ではありませんが、彼の小説には神話や伝承といった民俗学にも通じるテーマがしばしば登場し、どこか柳田氏との共通点を感じさせられます。
学問的に本書に書かれている柳田氏の仮説が正しいかどうかは分かりませんが、想像力をかき立てられ、どこか懐かしさを感じさせてくれる1冊であることは間違いありません。
維新風雲回顧録
いわゆる幕末の明治維新では多くの"志士"と呼ばれる人たちが湧いたかのように出現しました。
そして維新を達成し、志士たちは新しい時代を担う指導者という立場へと変わっていった一方で、多くの志士たちが夢半ばで斃れてゆきました。
本書は22歳という若さで土佐藩を脱藩し、志士の1人として奔走した田中光顕自らが当時を振り返った回顧録です。
田中は生き残った志士たちの中でも特に長命で、1939年(昭和14年)に95歳という高齢で没しています。
本書は80代の頃の口述を元にしていると言われていますが、その頃すでに江戸は民衆にとって遠い記憶となり、維新の完成を見ることなく若くして斃れていった武市半平太、高杉晋作、坂本龍馬、中岡慎太郎といった著名な志士たちと共に行動を共にした経歴を持ちながらも当時存命していたのは田中以外にいなかったのではないでしょうか。
巻頭には司馬遼太郎氏が田中光顕を「いわば典型的な二流志士である」と評しながらも、 「二流の場所であるがゆえに、かえって西郷、木戸、大久保、坂本といったひとびととはべつな視点をもつことができた」と本書を紹介しています。
たしかに田中は幕末において藩(一国)の方針を左右するような立場にいなかったことは確かですが、それだけに一歩引いた目線でそういった立場にある人たちを観察し、軽いフットワークで土佐だけでなく京都や大阪、長州などさまざまな場所へ出没しました。
もちろん田中のそうした行動も新選組や見廻組といった幕府側の組織に命を狙われる危険性を伴うものでした。
本書は明治維新を自身の視点から振り返ったものであり、実体験を伴うものだけに、たとえば作家が執筆する明治維新とは違い、当事の心境や実際に交わした会話などが生々しく回想されているのが特徴です。
多くの志士たちとの交流があった田中ですが、彼がもっとも影響を受けたのが長州の高杉晋作です。
彼が持っていた佩刀を欲しがった高杉への交換条件として弟子入りした田中は、彼を近くで観察するにつれ天衣無縫、天才児であるという感想を抱き、わずか29歳で病死した高杉から生涯に渡って大きな影響を受けたようです。
もう1つ本書の特徴が、維新の過程で斃れていった志士たちへ言及することが多く、彼らの残した辞世の句を積極的に掲載している点です。
本書の最後に、明治に入り木戸孝允(桂小五郎)が田中へ向けて送った俳句が紹介されています。
世の中は桜の下の相撲かな
はじめ何のことか分からぬ田中が木戸へ尋ねると、「桜の下で相撲をとってみたまえ、勝ったものには、花が見えなくて、仰向けに倒れたものが、上向いて花を見るであろう、国事に奔走したものも、そんなものだろう」という回答が返ってきます。
これは身を賭して国事に奔走して斃れた志士たちは美しい花を見ることなく、例え幕府側にあっても生き残った人たち(本書では榎本武揚、大鳥圭介などを指している)は負けた側でも出世することを皮肉った、木戸らしい句に思えます。
この回顧録を世の中に発表したのは、国家の犠牲となり倒れていった殉難志士たちを偲ぶとともに、著者自身が人生の集大成として彼らの姿を後世へ伝えてゆく義務を感じていたからに他なりません。
友情 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」
ラグビー元日本代表、そして神戸製鋼、日本代表の監督を経験し、2016年10月に53歳という若さでお亡くなりになった平尾誠二氏を追悼した1冊です。
私の世代では「スクールウォーズ」がとにかく有名で、そのモデルとなった伏見工業高校が全国初制覇を果たしたときの主将としても知られています。
個人的には圧倒的な強さで日本選手権を7連覇していた頃に神戸製鋼で主将としてプレーしていた姿が一番印象に残っています。
本書では平尾氏と家族ぐるみで親密な交流のあったiPS細胞の作製技術を確立し、ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥氏、そして平尾氏の妻である恵子さんが当時の様子を振り返り、さらに平尾氏と山中氏が出会うきっかけとなった「週刊現代」の対談が収録されています。
タイトルに「友情」とある通り、平尾氏と山中氏との関係が大きくクローズアップされています。
山中氏にとって平尾氏の存在は大きなものだったようで、次のように振り返っています。
平尾誠二さんと僕との付き合いは、出会いからわずか六年間で終わってしまいました。けれど、四十代半ばを過ぎてから男同士の友情を育むというのは、滅多にないことです。
なんの利害関係もなく、一緒にいて心から楽しいと感じられる人と巡り会えた僕は幸せでした。
平尾氏がはじめに体調の異変に気付いた(吐血した)前夜も、山中氏は平尾氏と一緒に食事していたそうです。
そして病気が発覚した時点で余命3ヶ月という厳しい診断結果が出た時、山中氏も医師であるだけにその深刻さを理解して声を上げて子供みたいに号泣したといいます。
それでも平尾さんの病気を全力をかけて治したいという思いに駆られたそうです。
一方の平尾氏も色々な治療法がある中で「僕は先生を信じると決めた」と山中氏の治療方針に従うことに決めます。
忙しい中でもこまめに平尾氏の元を訪れる山中氏、辛い治療の中でも弱音を吐くどころか、忙しい山中氏を気遣う優しさを忘れない平尾氏の関係は、まさに"友情"にふさわしい関係だったと思います。
恵子夫人は2人の関係を次のように語っています。
今にして思えば、癌宣告を受ける前夜から山中先生が主人とご一緒だったことは、偶然ではない気がします。
二人の魂の結び付きは、それほど深かったのでしょう。そのことに、感謝の気持ちでいっぱいです。
平尾誠二の十三ヶ月に及んだ闘病生活に、山中伸弥先生は最初から最後まで寄り添ってくださいました。
当時、平尾誠二氏の突然の訃報を知ったときには、あまりにも早すぎる死にショックを受けたことをよく覚えていますが、本書によってはじめてその裏側に存在した友情と闘病の様子を知ることができました。
最初に悲しい結末ありきの本なのですが、それでも平尾氏の姿には読者を前向きにする明るさがあり、2人の関係を微笑ましいと思うと同時に羨ましいとも思ってしまうのです。
成瀬は天下を取りにいく
本屋大賞2024年をはじめ数々の賞を受賞した話題の作品です。
娘が読みたいということで購入した本ですが、私も読んでみることにしました。
主人公は滋賀県大津市に住む成瀬あかりという女子中学生です。
彼女は勉強も運動も得意であり、普通であれば間違いなくクラスの人気者となるはずですが、他人を寄せ付けない雰囲気と性格からクラスでは孤立している存在です。
しかし当の本人は孤立していてもまったく平気で、わが道をゆく、つまり自分が決めたことを実行してゆく強い意志と行動力があります。
随分変わった主人公だなと思いながら読み進めていきますが、次第に彼女の言動、そこから生まれる周囲の反応に魅せられゆくことに気付きます。
本書は6つの物語から構成されており、その中で主人公の成瀬は中学3年生から高校3年生へと成長してゆきます。
加えて物語の舞台はいずれも大津市を中心に展開されており、田舎でも大都会でもない地方都市を舞台としています。
著者の宮島未奈氏自身が大津市在住ということを読み終わってから知り、作品中で描かれる街の細かい風景や雰囲気に納得します。
作品を読み終わってから、なぜ成瀬が魅力的な存在に映るのだろうと考えてみると、おおよそ3点ほど理由が思いつきました。
まず最初に成瀬が同調圧力へ対してまったく無頓着で、クラスの中で孤立していても平気で毅然としている点です。
周りの言動に合わせる、顔色を伺うということに馴れてしまった多くの読者にとって、一介の女子学生である成瀬の姿にある種の憧れを抱いてしまうのではないでしょうか。
次に主人公の自信に溢れた行動力と強い信念が挙げられます。
たとえば自分にとって大事だと思ってはじめた行動でも、周りから理解されずに奇異な目で見られたりすると自信が揺らぎためらってしまうものです。
しかし成瀬は周りの視線など気にせず、自分で決めたことにまっすぐ突き進む強さを持っています。
最後に主人公の持つ不器用さが逆に魅力となる点です。
勉強も運動も得意な成瀬ですが、他人とのコミュニケーションは決して得意ではありません。
それでも心を開いた友だちや自分に興味を抱いてくれた周囲の人たちには、不器用なりに自分を分かってもらおうという努力や思いやりを怠りません。
さらに付け加えるならば肝心な部分が抜けていたりして、そうした人間味が読者たちの共感を呼ぶのではないでしょうか。
本作品は1日で充分に読み終えることのできる分量で、ストーリーもテンポよく進むので長編小説を読むのが苦手な人でも楽しむことができると思います。
ちなみに娘は続編の「成瀬は信じた道をいく」を読み始めており、読み終わったらいずれ私も手にとってみたいと思います。
アンドロイドは電気羊の夢を見るか?
アメリカの代表的なSF作家であるフィリップ・K・ディック氏の代表作です。
本書は根強いファンのいることで有名な1982年公開の映画「ブレードランナー」の原案となった作品としても有名です。
今から50年以上前に発表されたSF小説の中では古典の部類に入りますが、この時代の作品は未来を描いたものでありながら、どこか懐かしさを感じさせてくれます。
当時はインターネットの影も形もない時代であり、作品中では自動車が飛行し、人類は火星などに移住し、レーザーガンが武器として使われている一方で、未だに雑誌が紙媒体のままであったり、TVやラジオがメディアとして主流だったりします。
こうした現在より進んだテクノロジーと時代遅れのテクノロジーが混在するところがレトロなSF的世界観であり、個人的には嫌いではありません。
この作品で特筆すべきは、本物の人間や動物と見分けがつかないレベルで精巧に作られたアンドロイドの存在です。
つまり現代よりはるかにAIとロボット工学が発達した世界なのです。
一方でアンドロイドには人間同様の人権は認められておらず、あくまで人間の労働力として使役される"便利な道具"に過ぎません。
その結果として高度に発達したアンドロイドが主人である人間に反抗して逃亡する事件が発生するようになります。
こうしたアンドロイドたちを賞金首として狙うのがバウンティ・ハンター(賞金稼ぎ)である主人公・リック・デッカードです。
当然のように逃亡した精巧なアンドロイドは人間社会へ紛れ込み容易に見抜くことはできませんが、そのための唯一の方法が精密な検査(フォークト=カンプフ検査法)なのです。
腕利きであるリック・デッカードはこの検査法にも精通しており、アンドロイドと対決する場面などはアメリカらしいスパイ小説の要素もふんだんに盛り込まれており、読者を夢中にさせてくれます。
作品中の高度に発達したアンドロイドには確実に"心"や"感情"のようなものが芽生え始めており、リックがアンドロイドへ対して抱く感情もしだいに変化が見られるようになります。
詳しくは作品を読んでの楽しみですが、やはり読書として意識せざるを得ないのは日進月歩で進化を続ける"AI"の存在です。
ここ数年でAIの技術は一気に進化し、これがアメリカの好景気を支える大きな産業へ成長しつつあります。
実際にアメリカでは、今まで人間が担ってきた仕事をAIが肩代わりするケースが増えつつあります。
一方でAIシステムの持つリスクを抑制するための法規制も整備され始め、AIの戦争利用、AIが人種、政治的意見、宗教的信条による差別を助長する危険性が指摘されています。
加えて作品は核戦争により荒廃した地球が舞台になっており、決して明るい未来ではありませんが、現在ウクライナやパレスチナで起きている戦争を考えると荒唐無稽な未来を描いたSF作品と笑い飛ばすことは出来ないはずです。
未来を描きつつも人間社会が抱える根本的な問題を浮き彫りにするのが名作SF小説の必須条件であり、そうした意味では間違いなく本作品はそれに当てはまるのです。
ルポ路上生活
東京オリンピックの開会式があった2021年7月23日から約2ヶ月に及ぶ路上生活体験記を綴った1冊です。
著者の國友公司氏は1992年生まれであり、当時29歳という若さで路上生活を試みる今どき珍しい気骨のあるルポライターのようです。
路上生活者、つまりホームレスを題材にした本は著者のように実際に体験したものを含めてかなりの数が出版されています。
一方で時代とともに生活スタイルや社会情勢は変わってゆき、それはホームレスであっても避けられません。
そうした意味で本書は最新のホームレス事情を知る上で貴重な作品であるといえます。
私自身、頻繁に都内へ行くことが多いためホームレスの人を見かけることはよくあります。
しかしジロジロ見るのも失礼であり、じっくりと彼らの様子を観察する時間もないことから、彼らの生活を詳しく知っているわけではありません。
著者自身も「ホームレスは一体、どんな生活をしているのか?」という素朴な疑問から自身で路上生活を始めてみたといいます。
また場所が変わればホームレスたちの生活様式が変わることが予想されるため、著者は新宿、上野、そして荒川の河川敷というおもに3箇所でホームレスを体験します。
ホームレスというと貧困の最前線で飢えと隣合わせの生活というイメージを抱く人がいると思いますが、すくなくとも東京でホームレスを続ける限りその心配はまったくないようです。
それはさまざまな宗教団体やNPOが各地で炊き出しを行っており、著者は都内各所の炊き出しスケジュールに詳しいホームレスとともに1日7食の炊き出しツアーを敢行し、満腹で苦しむといった体験をします。
ちなみに炊き出しには多くの人たちが並びますが、その8割くらいはホームレスではなく、生活保護受給者たちであるといいます。
さらに著者が予想していたことであり、私も実際に目撃して大変そうだなと思ったのが冬の路上生活です。
都内とはいえ真冬には気温が氷点下にまで下がることもあり、夜は凍えて寝れないのではないかと心配してしまいますが、やはりさまざな団体から支給される防寒着や寝袋で案外快適に過ごせるようです。
しかも毎年支給されるためホームレスたちは冬シーズンが終わると寝袋や防寒着は荷物になるので、捨ててしまうといいます。
それよりもホームレスたちにとって夏の暑さの方がキツイといいます。
たしかに熱が放出され続けるアスファルトの上で寝る夜は、裸になったとしてもその暑さから逃れる術がありません。
著者は7000円を所持してホームレスになりますが、炊き出や配給によって食料には余裕があり、新宿区などが無料シャワーを提供していることから、お金に困ることは少なかったようです。
転売屋の元に行われる買い出しのバイト、パチンコの抽選の列に並ぶバイト、さらに宗教の研修へ行くと現金が支給されるなど、それなりに現金収入を得る方法があるようです。
基本的に都心に住むホームレスは寝るスペースしかありませんが、小屋を建てて住む河川敷のホームレスはスペースに余裕があるため、空き缶拾いによって現金収入を得ることもできます。
つまりホームレスたちは食の心配がないことに加えて、酒やタバコ、さらにはギャンブルを楽しむことも可能なのです。
著者と交流のあったホームレスたちの多くは、社会復帰や生活保護を受給してアパートに住む生活を望まない人が多いようですが、だからといって彼らが社会生活と無縁であるわけではありません。
ホームレスの間にも序列があり、そして多くのルールがあります。
健康を害したり、暴力や窃盗といった犯罪に巻き込まれる危険性も高く、けっして安全で気ままに暮らせる身分でないことだけは確かです。
私たちはとかくホームレスたちを違う世界に住んでいる人たちと思いがちです。
それだけにホームレスを実際に体験した著者だからこそ分かる、ホームレス側からの見る社会への視点、そして彼らのリアルな生活は新鮮であり、多くの気付きを与えてくれるルポタージュです。
日本人が知らない台湾有事
中国と台湾の間に広がる緊張関係について報じられることがありますが、多くの日本人は隣国同士の問題であることから漠然とした不安を抱くとともに、とくに日本の領海へ侵入を繰り返す中国へ対して危機感を募らせている人が多いのではないでしょうか。
中国側は台湾を「中国の領土の不可分の一部」と主張し続けており、当然のように台湾はこれに対して反発し、日本、そして同盟国である米国も中国の主張を承認していません。
近い将来、台湾と中国との間で戦争が起きる可能性はどのくらいあるのか?また戦争になった場合、具体的にどのような事態が起こることが予想されるのかを言及しているのが本書です。
まず本書の前半ではさまざまなシンクタンクや政府機関が行った台湾侵攻シュミレーションの結果を紹介しています。
台湾へ向けられる人民解放軍の戦力、それに対する台湾側の戦力分析から始まり、中国側が台湾上陸を目指すための海上輸送能力、具体的な上陸予想箇所などと併せながら、楽観的、悲観的シナリオをそれぞれ紹介しています。
代表的なアメリカのシンクタンクCSIS(戦略国際問題研究所)の報告によれば、「中国の台湾侵攻は困難で、ほとんどの条件下で失敗する」といった結論に至っています。
ただしこれには条件があり、アメリカ軍が遅くとも2週間以内に参戦すること、日本が中立的立場をとらず台湾を支援するといったことが挙げられています。
続いて本書では人民解放軍の真の実力を分析しています。
ニュースでは中国が莫大な予算を投じて軍拡路線を突き進んでいると報じられていますが、空母や潜水艦、航空戦力、保持しているミサイルの種類やその数、核兵器、現代の戦争で重要になってくるサイバー戦部隊、さらには宇宙軍といった点にまで言及しています。
単純な数だけでなく、技術力や性能といった点も細かく分析しており、本書でもっとも多くのページが割かれているその情報量の多さに驚かされます。
著者の小川和久氏は、自衛隊、新聞記者などの経験を経て日本人初の軍事ジャーナリストとして独立した方であり、本書の内容は自衛隊の高級幹部に話しているのと同じレベルであるといいます。
もちろん戦力分析やシュミレーションは中国側でも行っており、著者によれば彼らは現時点でそう簡単に台湾侵攻が成功しないことを冷静に受け止めているといいます。
一方で日本側は台湾有事が起こった際の立場や戦略すら整理できていないと手厳しい指摘をしています。
つまり台湾有事が起こった際に、その対策を国会で議論している間に手遅れになりかねない状況にあるといいます。
日本と台湾との間に軍事同盟は締結されていませんが、台湾有事の際にアメリカは日米同盟を根拠にした軍事的な協力を日本へ期待しています。
そして協力を行えば当然のように日本も戦争に巻き込まれる可能性があります。
まずは隣国の親日国である台湾を我が事のように捉えて協力するのか、あくまで第三者として中立的立場を貫き日本へ戦火が広がることを防ぐのかを明確にする必要があります。
いずれにせよ日本と中国との間には尖閣諸島問題を抱えていることから分かる通り、台湾有事は決して人ごとではないのです。
巨大企業に勝つ5つの法則
タイトルから中小企業が巨大企業と競争するための戦略を解説した本だと容易に想像できますが、ビジネス本の視点としてありふれたものであり、かつ15年近く前の2010年出版ということで個人的にはあまり内容には期待していませんでした。
一方で私自身は1度も大企業に所属したことはなく、小さな世帯の企業の方が性が合っているという自覚があることから、なにかヒントらしきものが1つでも書かれていればと思い古本として購入したものです。
まず結論から言うと、よい意味で裏切られた1冊でした。
私自身も間近で見てきましたが、大企業はフットワークが重く、新しい手法や分野に挑戦する意欲に乏しいという傾向があります。
それでも圧倒的な資金力と組織力で安定した経営を実現し、社員の待遇は厚く、大規模なプロジェクトを遂行できるという面もあり、一般的に見ればやはり巨大企業の方にメリットが多いと感じます。
先ほど挙げた巨大企業のデメリットについては本書でも言及されていますが、本書ではそれを体系的に解説し、さらに新しい視点を提供してくれます。
それは「劣勢であることを強みにする」という逆説的な発想です。
とはいえ"劣勢"は"劣勢"であり、それ自体が有利へ働くことはありませんが、本書では以下の通り述べられています。
後がないから全力を出すしかない。
巨大企業と対峙した小企業にとっては「有事」であり、組織が実力主義となり全力で取り組むことができる。
大企業が持つ過去の成功体験はノイズとなり、必ずしも新しい市場で役立つとは限らない。
(成功の)未経験者の方が画期的な製品やサービスを生み出しやすい。
経験がない者は、体面や外見と気にすることなく他者から「貪欲に学ぶ」ことができる。かなりシンプルなように見えますが、本書ではこうした1つ1つの項目について具体的な事例が付け加えられており、理解しやすい内容になっています。
この「貪欲に学ぶ」という行為はもっともノウハウを効率的に吸収できる方法である。
後半に入ると「変人を」重視する、サムライをリーダーにするといった、社内組織の秩序を保つために大企業が実行しにくい抜擢人事についても言及しています。
ここで挙げられている具体的例は、個人的にファンでもある「プロジェクトX」にも登場しそうな人たちであり、参考になると同時に楽しく読むことさえできます。
はじめに紹介したように約15年前に出版された本ですが、今でも充分に参考にできる点が多く、内容もよくまとまっている優れたビジネス書としてお勧めしたい1冊です。
こうして社員は、やる気を失っていく
多くのモチベーションの高い社員によって構成される企業は業績が良く、離職率も低くなります。
つまり社員のモチベーションを高めることは、企業が生存・成長してゆく上で欠かせない要素になりますが、その方法を紹介して解説するだけでは普通の切り口のビジネス書になってしまいます。
本書はこれを逆の視点、つまり社員がやる気を失ってゆくNGな上司の言動、企業文化や制度を紹介してゆき、社員のモチベーションを下げる要素を取り除いてゆくといったアプローチをとっています。
本書ではその過程で"ゼロベースシンキング"、"推論のはしご"、"内発的動機付け&外発的動機付け"、"DESC法"、"目標管理制度(MBO)"、"ウェルビーイング(Well-being)"、"ライフ-キャリア・レインボー"といった多くの実績のある手法や、働くことに関する研究・実験結果を引用して説得力を高めています。
ただし本書を最初から最後まで読んでゆくと最終的にはかなり多くの手法が登場することになるので、目次から自分たちが当てはまりそうな箇所を抜粋して実践してゆくのが効率的だと思います。
加えて本書は部下を持つ社長や管理職を対象にしていますが、例えば小さなチームを率いるリーダーであっても実践できる内容が含まれいます。
以下に本書の主要部分である2章と3章の目次を紹介してみます。
■第2章 社員がやる気を失っていく上司に共通する10の問題と改善策
- 目を見て話さない。目を見て話せない。 - メンバーとまともに向き合わない上司
- 理由や背景を説明しない - 「意味のない、ムダな仕事」と思わせる上司
- 一方通行の指示 - 双方向のコニュニケーションがとれない上司
- コントロールできる部分を与えない - 1から10までを指示する上司
- 話を聞かずに結論を出す - 頭ごなしに決めつける思い込み上司
- 意見も提案も受け入れない - 「自分が絶対」のお山の大将上司
- 言うことに一貫性がない - 行き当たりばったり上司
- 感覚だけで評価する - 結果を出しても評価されないと思わせる上司
- 失敗を部下のせいにする - 責任転嫁し、自己保身に走る上司
- 部下の仕事を横取りする - いつまでたっても「自分が主役」上司
■第3章 「組織が疲弊していく会社」に共通する15の問題と改善策
- 個人が仕事を抱えすぎている - 不平等で不満ばかりの組織
- 仕事を押しつけ合う - 会社的視点、共働の意識がない組織
- 物事を決められない - コミュニケーション機能が不全な組織
- 前例と成功体験から抜け出せない - 新しいものを生み出せない組織
- 「理念」が言葉だけ - 細部に魂が入っていない組織
- 「挑戦」「改革」・・空手形の言葉ばかり - 言葉と中身が一致していない組織
- 社長がめちゃくちゃ忙しい - 社員を導くリーダーが不在の組織
- 管理職が逆ロールモデル - めざすべき人物が不在で不幸な組織
- いつもピリピリしている - 不機嫌、不安、不快がはびこる組織
- マイナス要因の犯人探しに執心 - 「性悪説」による不信感と不寛容な組織
- よくわからない人事異動がある - 「え、なんで?」不透明・不可解・不当な組織
- いまだに長時間労働が美徳 - 時代の変化についていけない組織
- 女性が出世しない - 価値観が偏った不条理な組織
- 子育て、介護で働きにくい - 働きやすい制度の不足・不備がある組織
- 長期的な展望を描けない - キャリア設計が不安、不明な組織
目次からわかる通り、経営コンサルタントである著者(松岡保昌氏)は、人間心理を徹底的に考え抜くスタンスで仕事に取り組んでいるとのことです。
モチベーションは目に見えないものであるが故に見落としやすいものであり、本書から参考になる要素は多そうだと感じました。
雲の墓標
本書は阿川弘之氏による戦争文学ですが、すこし変わった形式で書かれています。
それは主人公・吉野次郎が学徒動員されて海軍へ入隊した直後の昭和18年12月12日から、特攻隊として出撃を命令された昭和20年7月9日までの日記をひたすら掲載するという形をとっている点です。
作品中の主人公は、はじめは自由な学生時代を謳歌していた日々と軍隊生活のあまりの違いに戸惑い、その理不尽さに憤りを覚えるという当然の反応を示すことになります。
やがて学生生活を懐かしみつつも1人前の飛行士になるため訓練に励む日々が続きます。
そこからは本望ではないものの、軍隊に入ったからにはベストを尽くすという若者らしいひたむきさが感じられます。
しかし軍隊にいると、やがて日本の戦況が圧倒的に不利な状況であることを知り、自身が再び生きて学業の道へ戻れる可能性が低いことを実感します。
たとえ自分の命を捧げることになっても戦争の大局へ影響を与えることのできない無力さ、自らの人生の意味を考えて葛藤が続くことになります。
ついに戦局が差し迫った状況となり、かつては志をともにした学友たちが特攻隊として空へ飛び立ち、あるいは訓練中の事故死などで命を失っていく日常を目の当たりにすることで、さらに心境の変化が生じていきます。
最終的に主人公は、心の底から晴れ晴れとした気持ちで出撃し、両親へ対して思い残すことはないので、どうか安心してくださいと日記の中で綴っています。
若い頃に特攻隊に関わる話を見たり聞いたりしたときは、国を守るために若い命を散らした若者たちの潔さを感じる一方で、なぜ手段を選ばずにとにかく生き残る道を模索しなかったのだろうと疑問に思うことがありました。
しかし自身も海軍予備員をして戦争を経験した阿川氏が描く作品の力、もしくは私自身の年齢のせいなのか、主人公の心情の変化に共感できる部分が多くありました。
ともに青春を過ごしてきた学友たちが次々と命を失ってゆく中で、自分だけが生きながらえても仕方ないというあきらめの感情も多少あったと思いますが、最終的には自身が生きた時代、そして与えられた環境の中で自分の生き方を自分で決めたという覚悟がそこにはあったような気がします。
おそらく主人公の心境は、当時の作者自身が抱いていた感情ではないでしょうか。
日々の出来事を綴った日記という形式をとっているため、著者は直接的に戦争へ対して肯定も批判も行っておらず、意識してイデオロギー的なものを作品中から排除しています。
そのため本書は時代を超えて読者の共感を呼ぶことのできる完成度の高い戦争文学作品といえるでしょう。
美味放浪記
本書は作家の檀一雄氏が国内外を問わず各地の名物料理を味わう旅をエッセーにしたものです。
作家にはグルメが多い印象がありますが、よく考えると美味しい料理を食べるのは誰にとっても嬉しいはずです。
たとえばTVでグルメロケが得意な芸能人がいるように、その美味しさを文字で表現することに関しては作家の右に出る職業はありません。
檀氏は自らを、美食家ではなく繁華街や市場にある立喰屋・立飲屋をほっつき廻るのが性に合っていると謙遜していますが、私から見ると立派な美食家に思えます。
それは高級料理を好んで食べるという意味ではなく、さまざまな地域にある独特の食文化、たとえば発酵食品やら内臓料理といったクセの強いものであっても先入観なく何でも平気で口に入れることができるからです。
本書は国内編、そして海外編で半々に分かれており、目次を見るだけで読むのが楽しみなラインナップが揃っています。
<国内篇>
- 黒潮の香を豪快に味わう皿鉢料理(高知)
- 厳冬に冴える雪国の魚料理(新潟・秋田)
- 郷愁で綴る我がふる里の味覚(北九州)
- 中国の味を伝えるサツマ汁(南九州)
- 日本料理・西洋料理味くらべ(大阪・神戸)
- 瀬戸内海はカキにママカリ(山陽道)
- さい果ての旅情を誘う海の幸(釧路・網走)
- 素朴な料理法で活かす珍味の数々(山陰道)
- 夜店の毛蟹に太宰の面影を偲ぶ(札幌・函館)
- 野菜のひとかけらにも千年の重み(京都)
- 攻撃をさばいて喰べるワンコソバ(津軽・南部)
- 飲食の極致・松坂のビール牛(志摩・南紀)
<海外篇>
- サフラン色の香りとパエリアと(スペイン)
- 初鰹をサカナに飲む銘酒・ダン(ポルトガル)
- 迷路で出合った旅の味(モロッコ)
- チロルで味わった山家焼(ドイツ・オーストリア)
- 味の交響楽・スメルガスボード(北欧)
- 保守の伝統がはぐくむ家庭料理(イギリス)
- カンガルーこそ無頼の珍味(オーストラリア・ニュージーランド)
- ボルシチに流浪の青春時代を想う(ソビエト)
- 贅沢な味 ア・ラ・カ・ル・ト(フランス)
- 悠久たる風土が培う焼肉の味(韓国)
- 食文化の殿堂・晩秋の北京を行く(中国)
本書を執筆は1960年代の経験を元に執筆されたものであると推測されますが、国内篇だけを読んでみても私の知らない料理が数多く登場します。
檀氏は料理を人類学的、歴史的に考察することなど考えたことがないと言いながら、今現在で消えてしまった食文化も本書に収録されている可能性があり、今から約60年前の貴重な食文化を伝える本としても価値があります。
空白の日本史
著者の本郷和人氏は、東京大学史料編纂所という場所で研究、教員を行っている歴史学者です。
東京大学史料編纂所というとあまり聞き慣れませんが、東京大学付属の研究所として史料の収集、調査、分析などを行っている組織のようです。
当然のように歴史は"史料"を元にして調査・分析が進められ、やがて通説となるものが確立して学生たちが学ぶ歴史の教科書などに掲載されるようになります。
一方で古代から現代に至るまですべての出来事が史料として残っている訳ではありません。
つまり史料が残されていない時代、もしくは出来事に当たる部分が、本書タイトルにある"空白"ということになります。
もし史料が絶対的な根拠となるならば、記録が残されていない過去は何も言及できないということになります。
しかし著者は、こうした「空白」を埋めるのも歴史研究家たちの仕事であると主張しています。
それでも想像力や自分にとって都合のよい解釈だけで空白部分のストーリーを埋めるだけでは研究とは言えず、科学的な根拠や論理に基づき埋めてゆくことが大切だと主張しています。
本書では具体的な例とともに、その性質ごとに9つの空白をテーマに挙げています。
- 科学的歴史の空白
- 祈りの空白
- 文字史料の空白
- 国家間交流の空白
- 軍事史の空白
- 文献資料のの空白
- 女性史の空白
- 真相の空白
- 研究史の空白
著者は科学的な手法に基づいた歴史分析を軽視すると歴史がイデオロギーに利用され、「神武天皇が紀元前660年に即位したとされる皇国史観」「日本に鎖国はなかった」といような説がまかり通ってしまう危険性があると警鐘を鳴らしています。
また先人のすぐれた学者が残した研究を無視する、つまり敬意を払わない傾向があることにも憂慮しているようです。
本書で例として取り上げられているものとして、朝尾直弘氏の「信長は神になろうとした」説、尾藤正英氏の「水戸光圀は勤王家、尊王家ではなかった」説、高群逸枝氏の「平安時代における招婿婚(男が妻方で夫婦生活を過ごす婚姻方式)」説など、著者にとってはどれも説得力があり一考の価値があるものの、誰も反論も再評価もしないため宙ぶらりんになっていると指摘しています。
こうした主張は一般読者というより、歴史研究に携わる人たちへ向けられたものですが、専門家が歴史と向き合う姿勢についても興味深く読むことができ、歴史好きであれば視野を広げるという意味では決して無駄にはならない1冊になっています。
野村の授業 人生を変える「監督ミーティング」
著者の橋上秀樹氏は、プロ野球ファンであれば元ヤクルトの野手として、引退後は複数の球団でコーチを努めてきた指導者として名前を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
現在は今年からプロ野球のイースタンリーグに参入しているオイシックス新潟アルビレックスの監督を努めています。
そんな橋上氏の野球人生にもっとも影響を与えたのが、ヤクルト、阪神、楽天などの監督を努めた名将と言われる野村克也氏です。
野村氏の野球を一言で表せば、データに基づいた論理的な采配が特徴であり、今でこそテクノロジーの発達とともにデータを活用するのは当たり前になっていますが、それをいち早くプロ野球へ取り入れた功績があります。
本書のタイトルにある「監督ミーティング」とは、野村監督が春季キャンプなどのまとまった時間がとれるときに選手たちへ行った講義のことを指しています。
そこでの話題は野球だけに留まらず、人生とは何か? 仕事とは何か? といったテーマを選手たちへ考えさせる内容だったようです。
野村監督は「人間的成長なくして、技術的な進歩はない」という強い信念があったようです。
橋上氏自身、そこでの教えを書き写したノートは10冊以上になり、本書は「監督ミーティング」のエッセンスを抜き出したものであり、私自身は未読ですが 野村の「監督ミーティング」のという作品の続編となるようです。
野村監督は野球に留まらず、経営など多くの本を読んできた読書家としても知られています。
プロ野球球団は、1軍~3軍選手、それらの監督コーチ陣、多くの裏方スタッフ、さらには球団社長やオーナーなどを含めるとかなり大きな組織であるといえます。
つまり監督という立場にある人間が、人材育成や組織論について学ぶのは自然の流れであり、監督として戦力的に弱小と言われるチームを何度も優勝に導いてきた実績を持つ人の言葉は価値があるのではないでしょうか。
そのため本書は、野球とは関係のない多くの読者にとっても参考になる1冊であると言えます。
本書には橋上氏が野村監督より教えを受けた多くの言葉が収録されていますが、目次からその一部を引用してみようと思います。
- 有能なリーダーは、前リーダーのよいところを取り入れる
- 感性を磨け。鈍感なヤツは何をやってもダメだ
- 勝負強いヤツとは開き直ることができるヤツだ
- 相手を決めつけるな、簡単に理解できると思うな
- 「データの落とし穴」にはまってはいけない
- 誰であっても教えを請いにいく素直さ、貪欲さ
- リーダーは考え方の基準を部下たちに示さなければならない
- リーダーがその仕事をいちばん好きにならなければならない
- 誰に聞いても「いい人」は、いいリーダーではない
- 「オレが100%、正しいわけじゃない」という教え方
- 味方のチャンスは相手のピンチ
一般的な会社組織においても通じる言葉が並んでいるのはないでしょうか?
会社の経営論や組織論からプロ野球チーム監督としてのヒントを学んだように、プロ野球という厳しい勝負の世界で長年結果を出し続けてき野村監督の教えから再び会社組織へフィードバックできる点は多いはずです。
史実を歩く
史実を元にした綿密な取材から生み出される吉村昭氏の作品は、"記録小説"と呼ばれます。
それは作品の舞台となる場所へ何度も赴いて資料を集め、専門家や市井の郷土史研究家たちへの取材を重ねるといった地道な活動に裏付けられています。
本書は、著者が今までは発表してき作品のいわば舞台裏、つまり創作秘話を明らかにした作品であり、ファン必見の1冊です。
吉村氏は多くの作品を残していますが、本書でその取材・執筆の過程を紹介しているおもな作品は以下の通りです。
- 破獄
- 長英逃亡
- 戦艦武蔵
- 桜田門外ノ変
- ニコライ遭難
- 生麦事件
いずれの作品の場合も取材への熱意と徹底ぶりは作家というよりも、まるで学者のようです。
しかし著者はそうした膨大な資料集めを以下のようにそれほど大変ではないと言い切っています。
地方へ行くだけでなく都内に足を向ける時も、そこへ行けば必ず眼にしたい資料があるはずだ、と考えて出かけてゆく。
長年このようなことを繰り返してきたので、勘というか、まずまちがいなく望んでいる資料を見出すことができる。
~中略~
傲慢のようであるが、事実なのだから仕方がない。期待をはるかに超えた資料を眼にして、興奮することもある。
ただ作品執筆のための調査は順調に進められても、肝心の執筆活動では大きなしくじりをしたことがあるそうです。
たとえば「桜田門外ノ変」では物語の書き出しを誤り、252枚もの執筆済み原稿用紙を庭の焼却炉へ投げ入れた経験があるといいます。
著者には最初の一行で小説の運命はすべてきまるという信念があり、強いプロフェッショナルとしての信念を感じます。
ちなみに吉村氏は酒豪としても有名であり、取材や資料収集のために訪れた地方で飲む小料理屋での一杯は何よりの楽しみだったに違いありません。
アメリカ彦蔵
主人公がある日突然、異世界に転生して活躍するストーリー、いわゆる"転生モノ"と言われるアニメやラノベが人気の分野となっているようです。
これを現実世界に例えるなら、異国にたどり着いた江戸時代の漂流者がそうした主人公たちに一番近い存在ではないでしょうか。
かつて和船が嵐に遭い、船が転覆することを免れるための最終手段として帆柱を切り倒すことが行われました。
しかし帆を失った船は"坊主船"と呼ばれ、コントロールを完全に失い潮の流れに身を任せるしかありませんでした。
そこで飢えと渇きのために多くの船員たちの命が失われましたが、中には幸運にも救出される人が存在しました。
とくに19世紀に入ってから太平洋で多くのアメリカ船籍の捕鯨船が操業するようになり、彼らに救出される日本人漂流者が増え、本書の主人公である"彦蔵"もその1人でした。
鎖国政策を続けてきた江戸時代においては、日本人にとって外国は完全に未知の世界でしたが、アメリカの地を踏んだ彦蔵をはじめとした元漂流者たちは、自分たちとまったく異なる言語と文化を持つ人間と接触することになるのです。
しかもそこでは蒸気機関で動く船や鉄道、蛇口をひねると水が出てくる水道、夜でも街を明るく照らすガス灯、さらには遠く離れた人間同士が連絡を取り合う電信など、未知のテクノロジーにも遭遇します。
まさしく彼らにとっては、完全な異世界に紛れ込んだ状態といってよいでしょう。
著者の吉村昭氏は、ほかにも漂流を題材にした作品を手掛けていますが、本書はその集大成といってよい1冊に仕上がっています。
本書の主人公は彦蔵ですが、作品中には彦蔵以外にも多くの日本人漂流者たちが登場します。
彼ら全員が例外なく故郷へ帰ることを望みますが、中には鎖国されている日本への帰国が叶わず異国の地で骨を埋めることを決心する人も出るなど、さまざまな人生を送りします。
本書の主人公である彦蔵は、彼らの中でもとくに数奇な運命を辿ることになります。
彼は15歳という若さで漂流から救出され、やがて英語を完全にマスターします。
そして多くの支援者たちの力によって教育を受け、日本人としてはじめてアメリカ大統領との面会を果たします(それどころか彦蔵は生涯において3人の大統領と面会することになります)。
恩人の勧めによって彦蔵はキリスト教へ改宗してアメリカ国籍を得ることになり、アメリカ人"ジョセフ・ヒコ"として幕末の日本の地を再び踏むことになります。
横浜で暮らすことになった彦蔵は新聞を発行し、日本における"新聞の父"と呼ばれるようになります。
それからも自らの意志で再びアメリカを訪れたりしていますが、維新後は日本人の妻を娶り、浜田彦蔵という名前で日本で暮らすことになります。
単行本で550ページにも及ぶ大作ですが、作品中には多くの漂流民たちの人生が丁寧に描かれており、情報化社会を生きる現代の私たちが世界中どこを訪れても彼らほどの驚きと戸惑いを感じることはないことを思うと、壮大な1つの物語といえるでしょう。
法師蝉
吉村昭氏の短編集です。
記録文学といわれるほど精密に史実を調査して執筆するのを得意とした著者ですが、本書のような純文学も発表しています。
史実を題材とした場合、著者は過去の出来事について登場人物の経歴を可能な限り詳細に取材し文献を調べ、誰がいつどこでどのような内容の発言をしたかだけではなく、その時の天気や月齢カレンダーまで徹底的に調査します。
こうして明らかになった細かい事実を積み重ねて過去の偉業や事件などを掘り下げていきますが、本書のような純文学にもそうした作風が生きています。
創作する物語の舞台となる街の風景、たとえば商店街にはどのような店が並んでいるか、主人公が泊まったとある地方の旅館の内装など、おそらくこうした描写は著者が頻繁に行った取材旅行の経験から生まれてきたものだと思われます。
本書に掲載されている一連の作品には共通点があります。
それは人生の秋を迎えた男たちが主人公であるという点です。
"人生の秋"というと定年、もしくは定年してから数年が經過したタイミングであり、具体的な年齢でいえば60~70歳くらいと推測されます。
次の世代に後に託して第一線から身を引き、子育てや住宅ローンといった責務からも解放される一方で、身体はある程度健康で老け込むにはまだ早過ぎる時期といったところでしょうか。
こうした境遇になり悠々自適日々を過ごす人もいると思いますが、本書に登場する主人公たちはいずれも闊達さよりも哀愁の方が強く漂ってきます。
いわゆる家に居ることが多くなり、仕事を引退してやること(やりたいこと)が無い、元気なのは妻の方というパターンです。
やはり文学作品には、若者に負けないバイタリティ溢れる老人よりも、秋風の中で襟に首をすぼめながら背を丸めて歩く初老の男性の方が絵になります。
いずれも主人公たちの心境を巧みに描いており、それは著者自身が本作品を"人生の秋"を迎えた年齢で執筆したからに他なりません。
本書には以下9作品が収められており、いずれも完成度の高い作品に仕上がっています。
- 海猫
- チロリアンハット
- 手鏡
- 幻
- 或る町の出来事
- 秋の旅
- 果実の女
- 法師蝉
- 銀狐
個人的には40代以上が読むと味わい深く感じられる一方で、若すぎる読者の場合、"哀しい"よりも"悲しい"が勝ってしまうかも知れません。
また男性だけでなく、是非とも女性にも読んでほしい1冊です。
登録:
コメント
(
Atom
)