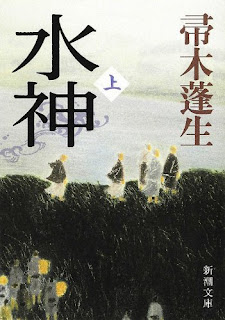エンブリオ (下)
前回紹介したように、本作品では胎児(エンブリオ)を題材にした最先端医療が内在する倫理的道徳的な問題をテーマにしています。
人為的に流産させた胎児を培養することで拒絶反応のリスクを極めて低くした臓器移植が実現し、これが本作の舞台となるサンビーチ病院で日常的に行われている医療行為なのです。
流産させられた死亡胎児は"組織の移植元としての道具"と見なされる一方で、"難病の治療に大きな効果をもたらす"のも事実であり、実際の法律においても"グレーゾーン"として手が付けられていないのが現実のようです。
こうした前回紹介した内容の他に、下巻ではもう1つの大きな問題を取り上げています。
本作の舞台となるサンビーチ病院は地方にある私立病院であり、その秘密裏で胎児に関する最先端医療が行われているという設定です。
言うまでもなく最先端医療は、今まで治療が困難だった病気へ大きな成果を上げる可能性がある以上、そこへ患者のニーズが集中するという結果は容易に想像できることです。
つまり大きな医療マーケットを創造する有望株となる訳ですから、巨大な医療関連企業がそうした病院の持つ最新技術へ関心を持ったとしたら、裏でどのような駆け引きが行われるかをテーマに取り上げています。
院長の岸川は、倫理的道徳的な問題は第二義として、とにかく自らの経営する病院において先端医療を研究・実現することを目的にしています。
一方でそうしたノウハウを特許化し、莫大な利益を得ようする金銭的な欲望は少ない人物でもありました。
そんなサンビーチ病院へ大資本を持ったアメリカ企業があの手この手で迫り来る中、岸川はどのように対抗してゆくのか?
本作品には、いわゆる"正義の味方"や"悪の化身"といった二元論で割り切れるような人物は殆ど登場しません。
最先端医療の虜になった人間、カネに目をくらました人間、そして手段を選ばずに健康な体を取り戻したい、子どもを授かりたいといったさまざまな欲望と葛藤が渦巻く世界なのです。
本作品には医療、さらに人類にとってきわめて現実的な近未来が描かれているような気がします。
エンブリオ (上)
タイトルの"エンブリオ"とは、受精後8週目までの胎児を意味する専門用語であり、本書によれば広義には出産するまでの胎児全般を指す場合にも用いられるようです。
言うまでもなく日本人の平均寿命は世界でも最高水準にあり、それに裏付けされる医療技術も高く評価されています。
一方で日本では毎年約100万人の新生児が誕生していますが、その裏では同じく毎年約30万件もの人工妊娠中絶が行われているのです。
最近では妊婦の出生前診断(血液検査)によりほぼ確実にダウン症の診断ができる検査が国内の病院に導入されるニュースが話題になりましたが、「命の選別」という反論も根強くあり、倫理的道徳的にはまだ議論の余地があり、法律の整備もまだ充分ではありません。
本書は2002年に発表されながらも、こうした人工中絶をはじめとした"胎児"の問題にいち早く真正面から切り込んだ作品です。
著者の箒木蓬生氏は医療を題材にした小説を多く手掛けていますが、本作品からは最先端医療技術へ言及する意欲が特に強く感じられます。
よく練られたストーリーというよりは、胎児へ対する、または胎児を利用した(近い将来実現する可能性のあるものを含めた)最先端の医療行為が実現した結果、どのような事態が現実に起こりえるのかをシュミレーションしたものが本作のストーリーを構成しているといえるでしょう。
主人公である岸川が経営する私立病院(サンビーチ病院)の中では、倫理を無視した医療行為が行われているという設定です。
皮肉にも「倫理を無視した医療=最先端の医療」という図式が成り立つわけであり、こうした技術の発達が人類の脅威になり得る現実は、原子力や軍事技術の発展にも共通するのではないでしょうか。
医療の発展が人類にとっての福音であることを疑わない岸川の自信は、次のセリフに集約されています。
「サンビーチ病院でやっていることは、すべて正解だ。誤答はひとつもない」
しかし内心では、自らの医療行為が世間に波紋を巻き起こすことを充分に自覚しており、
「ある先駆的な医療行為が宗教的、哲学的、倫理的、法律的、社会的な波紋を起こすのは、医学の歴史を振り返れば明白です」
という演説を学会で発言しています。
つまり岸川の目指す"先駆的な医療行為"は、地方のサンビーチ病院の中でのみ行われいるのであり、この閉鎖的な空間で濃密に繰り広げられるストーリーの中には、医療全般のあり方を問うような壮大なテーマを含んでいる問題作なのです。
安楽病棟
多くの医療ミステリー作品を手がける箒木蓬生氏の作品です。
タイトルから分かる通り、本書のテーマは"安楽死"です。
倫理的な意味合いで"尊厳死"が用いられることがありますが、いずれにしても終末医療で議論になるテーマです。
物語は、老人たちが入院している痴呆病棟が舞台になります。
前半では9人の老人たちが痴呆病棟に入院するまでの経緯を、その過ごしてきた人生ともに淡々とエピソード風に紹介してゆきます。
そして中盤から後半にかけては新人看護婦(城野)の視点から、看護や介護の風景、そして痴呆症にかかりながらも個性的な老人たちの素顔や病棟の日常をきめ細やかに描いています。
重篤な痴呆症になると自らの過去や家族の名前すら思い出せなくなり、加えて老衰によって体が不自由になるにつれ、食事や排便にも支障をきたすようになってきます。
(当たり前ですが)それでも、彼(彼女)たちには今まで歩んできた個性豊かな人生があり、数々の喜びや悲しみと共に多くの人生の時間を過ごしてきた先輩であることを気付かされるのです。
ようやく終盤になって本格的な医療ミステリーへと変わってゆくのですが、小説の場面々々ではっきりとメリハリをつけて書き分けられている印象を受けました。
しかし医療ミステリーとしての"安楽死"は本書の核となる部分ではありません。
あくまでも痴呆症老人たちの日常をなるべく医療現場に近い形で読者へ伝え、そして問題提起してゆくのが箒木氏の狙いだと思います。
私たちは"痴呆老人"を一括りにしてイメージしがちですが、実際の痴呆症の人たちには十人十色の個性がはっきりと出ます。
つまり若い頃の経験や習性などは、失われつつある思考能力や判断力の中でもしっかりと残るのです。
読者の中には、自らの名前さえ思い出せない重度の痴呆症になった時点で安楽死を望む人は結構いるのではないでしょうか。
しかしながらそれは健常者から見た視点であり、実際に痴呆症患者になった時点で"安楽死"の意思を伝えることは困難になりますし、仮に「死にたい」と言ったところで"老人のぼやき"としてしか受け取られないでしょう。
そこで主治医の判断により患者へ安楽死をもたらすという行為は果たして正当化されるのでしょうか?
もちろん現在の日本では一切認められないどころか殺人罪となりますが、一方で回復の見込みがない中で心臓が止まる瞬間まで全力で治療を続けるという行為は患者にとって過酷であり、高齢化社会を迎える日本にとって医療費の負担も大きな問題となってきます。
さらに(息子や娘といった)家族の意思が加わると、そもそも本人の(安楽死の)意思がねじ曲げられてしまうことも容易に想像できます。
本作を読み進めると多くの問題を突きつけられますが、それは"正義"や"悪"といった二元論では解決できないテーマなのです。
昔の日本には、自らの死期を悟った時点で食を絶って静かに衰弱死してゆく老人が多くいたようですが、栄養点滴といった医療技術が確立している現在では、おそらくこうした死に方は出来ないだろうと思います。
今の私には、痴呆や老衰によって不自由になる自分自身を実感を持って想像することは出来ませんが、客観的に考えれば本作品に出てくる多くの老人たちの姿が将来の私自身の姿である可能性は充分に現実的なのです。
「行き過ぎた医療技術の進歩が果たして人類へ幸福をもたらすのか?」、「医療技術の進歩に人間の倫理観が追いついていない」といったテーマは、箒木氏のすべての医療ミステリーに共通しているのです。
史記の風景
「史記」は前漢の時代に司馬遷によって書かれた歴史書であり、ジャンルを超えて世界で最も著名な本の1冊です。
2000年にもわたる古代中国の歴史を52万以上の文字で綴り、単に歴史上の事件を記録するにとどまらず、その内容は文化や風習、人物伝にまで渡り、後世に多くの影響を与えました。
史記から生まれたことわざや故事には枚挙にいとまがなく、日本でも奈良時代から「史記」は読み続けられ、その影響力は計り知れないものがあります。
たとえば現在使われている"平成"の年号1つとってみても「史記」にその由来を求めることができます。
著者の宮城谷昌光氏は、「史記」に登場する周や春秋戦国時代の人物を題材に多くの歴史小説を発表しており、「史記」の魅力を誰よりも知っている作家といえます。
一方で専門家でない私たちが漢文で書かれている「史記」を原文で読むのはきわめて困難なのも事実です。
本書はそんな「史記」を専門的に解説するのではなく、小説家ならではの自由な発想と解釈でその魅力を分かり易く伝えてくれる1冊です。
元々は新聞や雑誌で企画ものの連載として掲載されたものであり、基本的に1話完結の100章からなるエッセー風の文章で書かれています。
そのため気軽に読みながら新しい発見に出会う頻度も多く、いつの間にか「史記」の魅力に引き込まれてしまいます。
まさに教養と娯楽の2つの要素を満たしてくれる良書ではないでしょうか。
本書の中には太公望や晏子、孫臏といった小説の題材となった人物も数多く登場するため、宮城谷氏の作品を幾つか読んいるとより一層楽しめるでしょう。
のんのんばあとオレ
漫画家・水木しげるの自伝3部作ともいえる「のんのんばあとオレ」、「ねぼけ人生」、「ほんまにオレはアホやろか」。
水木氏の自伝はどれもクオリティが高く、世にある数多の自伝の中でも最高レベルだと思います。
本作「のんのんばあとオレ」は3部作の記念すべき最初の作品であり、水木氏の幼少期から(出兵するまでの)青年期の自伝となります。
タイトルにある"のんのんばあ"とは、幼い頃の水木氏に多くの伝承や民話、そして怪談を聞かせてくれた近所に住む神仏に使える祈祷師の老婆のことです。
"のんのんばあ"から受けた影響がのちの「ゲゲゲの鬼太郎」を始めとした妖怪マンガを書くきかっけになったことは、水木ファンの間では広く知られています。
今年92歳になった水木氏は今も健在であり、まさしく「三つ子の魂百まで」を形作った強い影響を当時の水木少年に与えたのです。
"のんのんばあ"は民族学的な表現をすれば"シャーマン"であり、大正終わりから昭和のはじめ頃までが、人々の日常の中にこうした種類の人々がいた最後の時代だったのかも知れません。
なぜ水木氏が特別にのんのんばあに可愛がられ、妖怪に興味を持ったかということを簡潔に説明しています。
オレは、生まれつきともいえるほど、葬式とか死とかに興味を持っていた。
茶わんとなべのふたで、チンチンジャンジャンと、葬式坊主のありさまを再現することが得意で、母によくしかられていたものだった。
だから、死とはわれわれの知らない別の世界へ行くことだとのんのんばあに聞かされていたこともあって、すこし気持は悪いが、どのようにして霊界に行くのか見たくてしかたがない。
水木少年は、ガキ大将をはじめとした子どもたちの社会の中でさまざまな遊び(イタズラ)に夢中になる一方で、"人間の住む世界とは別の世界"の存在も疑うことなく肌身に感じながら少年時代を過ごしたのです。
日常の中で水木少年は、のんのんばあからさまざまな話を聞かされて多感な時期を過ごします。
本作に出てくるほんの一部ですが、次のような水木少年とのんのんばあのやり取りが各所に散りばめられています。
うす暗い台所の天井のしみを見ては、あれは、夜、寝静まってから「天井なめ」というお化けが来てつけるのだ、とまじめな顔をしていう。
天井をよくみると、なるほど、それらしいシミがある。疑う余地はない。
「だれもいないのに鐘がなるのは、人の住まぬ荒れ寺に、どこからともなく野寺坊というのが来て鐘をならすのだ」
どうしてそんなに(フロ場)掃除をするのかとオレが聞くと、この腐った木にたまるあかを食べに「あかなめ」という妖怪が来るといけないからだと、のんのんばあは真剣に答えた。
もちろん本作品の主題は水木しげるの少年期の自伝であり、決して怪談ばかりを収録した本ではありません。
戦争の影が確実に忍び寄りつつある暗雲たちこめた昭和初期という時代でしたが、水木しげる氏をはじめとした子どもたちの無邪気でかけがえのない少年時代があふれる躍動感で書かれており、現在の我々が読んでも眩しいくらいに輝いています。
日本史の謎は「地形」で解ける
著者の竹村公太郎氏は、国土交通省の官僚として全国各地のダム建設、河川整備事業に関わってきた経歴を持っています。
よって竹村氏は地理や気象に造詣が深く、それを自身が好きな歴史という分野に紐付けて執筆したのが本書です。
本書の概要は序文にある次の言葉に集約されています。
何しろ地形や気象から見る歴史は、今まで定説と言われてきた歴史とは異なる。
このような説を発表すれば、素人が何を言うか、と歴史の専門家たちからの叱責を覚悟しなければならない。
しかし、地形と気象は動かない事実である。そのぶれない地形と気象の事象をどう解釈して、どう表現するかは各自の自由である。その解釈の根拠としてぶれない地形と気象を共有していれば、議論は拡大せず、客観的にある方向に向かっていく。
「なぜ信長は比叡山延暦寺を焼き討ちしたか」、「なぜ頼朝は鎌倉に幕府を開いたか」、「元寇が失敗した本当の理由とは何か」といった出来事にはどれも諸説ありますが、著者はこうした疑問に大胆にも地形を用いて迫ってゆきます。
著者は歴史好きですが、いわゆる歴史学者ではありません。
それゆえ先入観を持たず、自らが得意とするアプローチで大胆に歴史の謎に迫る姿勢は新鮮であると同時に、説得力を持って読者へ語りかけてきます。
そもそも"歴史学者"という存在が曖昧なのかも知れません。
彼らが専門的、かつ体系的な知識を持っていることは認めますが、彼らの間でも歴史上の出来事へ対する解釈が異なる事例は多々ありますし、根拠となる文献が存在しない場合などは、永遠に正しさが証明されないこともあるでしょう。
一方で国民的歴史小説家であった司馬遼太郎氏のように学者並みの知識量を持った人がいたり、郷土の歴史に精通した玄人顔負けのアマチュア研究家の人がいるのも事実です。
もちろん歴史の謎すべてが地形で解けることは思いませんが、本書を読み進めながら、歴史が持つ魅力である"ひとぞれぞれの解釈の自由"を改めて気付かせてくれる良書だと思います。
遠野物語・山の人生
民俗学の開祖である柳田国男氏の代表作である「遠野物語」、そして山にまつわる民間伝承などを研究、考察した「山の人生」、学会での講演内容を収録した「山人考」の3編が収録されています。
「遠野物語」で語られる"河童"や"座敷わらし"はあまりにも有名であり、作品の舞台となった岩手県遠野市では"遠野民話"を活用して観光にも力を入れているようです。
「遠野物語」は柳田氏自身が遠野で民話を直接収集したわけではありません。
知人となった遠野出身の佐々木喜善氏の知っている地元の民話を柳田氏がインタビューして書き留めたものが「遠野物語」となったのです。
そこには119編もの民話が納めらていますがどれも簡潔で短いものであり、2時間もあれば全編を読み終えてしまう分量です。
そして「遠野物語」に納められている物語には2つの特徴があります。
1つめは桃太郎のような昔話のような説話じみた要素がなく、また怪談のよう恐怖を強調する演出がほとんど殆どない点です。
飾り気のない素朴な伝承そのものといった描写には、柳田氏が主観を排除して正確に物語の"筋(すじ)"を書き残そうとした、後に大成する民俗学者としての冷静な態度が見て取れます。
実際に佐々木氏は訛りの強い方言で語ったようですが、本書に収録されている話はすべて標準語の文体で書かれています。
2つめの特徴は物語の新鮮さです。
中には古くから続く伝承に言及したものもありますが、多くは数十年からつい数年前の体験や出来事に言及した物語が多いということです。
よって当事者となった人名が正確に伝わっていたり、本書が執筆された時点で存命だった人物も存在します。
山々の奥には山人住めり。栃内村和野の佐々木嘉兵衛という人は今も七十余にて生存せり。この翁若かりしころ猟をして山奥に入りしに・・・・(略)
のように若い頃の体験を語る老人の話もあれば、
昨年のことなり。土淵村の里の子十四五人にて早池峰に遊びに行き、はからずも夕方近くになりたれば、・・・・(略)
といったつい最近の出来事も収録しています。
これも柳田氏が時期や地名、名前などが判然としない大昔のエピソードよりは、怪奇な体験であろうともなるべく信憑性の高い内容を重視した結果だといえます。
江戸から明治に時代が移り変わり、急速な科学や経済の発展により便利になってゆく一方で、自然や神々へ対する畏敬の念が失われてゆく世の中へ警鐘を鳴らすといった着眼点は素晴らしいの一言に尽きます。
大げさに言えば柳田国男は、平野の都市部ではとっくに失われてしまい、山深い里でかろうじて語り継がれていた"伝説"を救いだした功労者なのかも知れません。
柳田氏の必死の努力にも関わらず、それでも失われた伝承があることを柳田氏は"遠野物語・第12話"に書き留め惜しんでいます。
土淵村山口に新田乙蔵という老人あり。村の人は乙爺という。今は九十に近く病みてまさに死なんとす。
年頃遠野郷の昔の話をよく知りて、誰かに話して聞かせ置きたしと口癖のようにいえど、あまに臭ければ立ち寄りて聞かんとする人なし。
処々の館の主の伝記、家々の盛衰、昔よりこの郷に行われし歌の数々を始めとして、深山の伝説またはその奥に住める人々の物語など、この老人最もよく知れり。
○惜しむべし、乙爺は明治四十二年の夏の始めになくなりたり。
ちなみに「遠野物語」が明治43年に発表されています。
つまりほんの僅かな差で、多くの伝承、すなわちそこに隠れている先人たちの知恵が失われたことを意味するからです。
臓器農場
本ブログではすっかりお馴染みになるつつある帚木蓬生氏の作品です。
箒木氏の比較的初期の作品ということもあり、この頃多く執筆していた医療サスペンスです。
出だしのストーリーを簡単にまとめると次のような感じです。
作品の舞台は、九州のとある港町にある最先端医療を行う民間総合病院。
この聖礼病院に新人看護婦として赴任した天岸規子は、本人の希望通り小児科に配属されることになる。
規子は看護婦として現場の経験を積む毎日を送るが、ある日奇妙なウワサを耳にする。
それはごく限られた医師や看護婦のみが立ち入ることの出来る特別病棟に"裏の産婦人科"が存在し、聖礼病院が実績を上げている臓器移植手術に深く関わっているというものだった。。。
著者の箒木氏は現役の医師であり、そこへ優れた作家としての力量が加わることで、作品内で描写される医療現場の風景が臨場感と説得力を持って読者へ迫ってきます。
新人看護婦が正義感と責任感を背負い命をかけて巨大な病院の闇を暴くという設定には少し無理を感じますが、それでも圧倒的な迫力に押されて思わずストーリーに引きずり込まれてしまいます。
箒木氏は常に世界の最先端医療にアンテナを張り、そこへ自らの医学的知見を加えることによって他の作家にはなかなか真似の出来ない小説の分野を切り開いているのではないでしょうか。
また本作品では「臓器移植」、「奇形児」、そして何よりも「救われる命と犠牲になる命」といった重いテーマを真正面から取り扱っています。
これらは殆どの人にとって関係のない事柄であり、できれば真剣に考えたくないテーマかも知れません。
本書を通じて普段向き合うことのない重いテーマと読者が自然と向き合うことの出来るというのが、著者の本当の狙いなのかも知れません。
妖怪と歩く―ドキュメント・水木しげる
本ブログでまだ紹介できていませんが、漫画家"水木しげる"の自伝は間違いなく日本で3本の指に入る傑作であり、中でも「のんのんばあとオレ」、「ねぼけ人生」、「ほんまにオレはアホやろか」の3冊はすべての人にお勧めできる作品です。
太平湯戦争へ出兵して戦地で片腕を失いながらも奇跡的に帰還した壮絶な体験、売れない貸本作家として長い赤貧の生活を過ごした体験、もちろん「ゲゲゲの鬼太郎」の作者として漫画家として成功した経験はどれも起伏に富みながらも、微塵の悲壮感すら感じさせないその天真爛漫さに衝撃を受けます。
陽気にそして逞しく生きてゆく水木しげるの自伝は、その略歴からは決して伝わってこない圧倒的な迫力に満ちています。
水木氏が魅力あふれる人間であることは間違いありませんが、(失礼ながら)大変人であることも間違いありません。
しかし自伝であるが故に水木氏を客観的に見た時の"等身大の人間像"が分かりにくくなっていることも事実です。
本書はノンフィクション作家・足立倫行氏が1年間にわたる密着取材を行い執筆されたドキュメント作品であり、ある意味で水木ファンの待望だった1冊ではないでしょうか。
本作品の元になった密着取材は1993年に行われ、その時の水木氏は70歳を迎えていました。
足立氏は水木氏と故郷(境港市)一緒であることをきっかけに水木氏に興味を持ちますが、いわゆる熱狂的な水木ファンではありませんし、妖怪に特別興味がある訳でもありません。また足立氏は戦後生まれのため、水木氏とは一世代以上年齢が離れています。
さらに足立氏はノンフィクション作家という職業のため水木氏に密着取材をしながらも、冷静にそして微妙な距離感で眺めつつ本ドキュメンタリーを執筆している姿勢が伝わってきます。
当時の水木氏は、水木プロの経営者として多数のアシスタントを抱えながら精力的に執筆活動に行い、加えて年に3回も海外取材に赴き、さらに故郷(鳥取県境港市)にオープンした水木しげるロードの視察やイベントなどにも出席するといった、とにかく忙しい毎日を過ごしていました。
もちろんマンガ家は自営業ですから、引退時期は自分で決めて辞めることが出来ます。
にも関わらず水木氏は、パプアニューギニアの文明から離れた環境でのんびりと余生を過ごしたいという南洋幻想を常々抱いており、こうした二面性が水木氏の魅力でもあります。
本書の1つの山場は「アメリカの霊文化を訪ねる旅」と題されたアメリカンインディアンのホピ族を訪問する旅行です。
そこで伝統的に行われている神聖な儀式"ニーマン"を見学した水木氏の興奮した様子などに彼の思考がよく表れています。
「すごいです!あの祭りは予想以上に素晴らしいです!民族にとって祭りは一巻の書物と言われますけど、まさにその通りです!」
~中略~
水木は自説を強調するときの癖で、顔を少し傾け、唇を尖らせ、中空に振り上げた拳を何度も上下させた。
「いつ始まるともなく始まり、いつ終わるともなく続く、そこがいいんです。魂がこもってるんです。長い間聞いていても飽かない。オーケストラのような響きがありますよ、あの音楽は。精霊たちと本当に感応しあってるわけです!」
またホピ族の長老で精霊のメッセンジャーでもあるバンヤッカへ、精霊と妖怪との関係について熱心にインタビューを試みる水木氏の様子は、彼自身が妖怪マンガを書きながら人智を超えた妖怪(神)の存在を心底信じているのが分るエピソードです。
水木氏は戦時中にラバウルで分遣隊に所属している時に土民軍に襲撃され、たまたま歩哨として部隊から離れていたおかげで1人だけ生き残ったという経験を持っています。
その他にも多くの兵士たちの死を間近に見てきましたが、決して"死"や"人生"というのを達観することはありませんでした。
それどころか、むしろ死んでいった戦友の分まで貪欲に生きようとする旺盛な生命力に溢れています。
一見複雑そうに見えますが、実際の水木氏の人間像は単純であり、平和な時代に育ち小さな出来事に右往左往する私たちにとって水木氏の存在があまにも眩し過ぎるが故に、その正体が見えにくくなっているのかも知れません。
婚約のあとで
前回に引き続き、またもや恋愛小説を手にとってみました。
著者は昭和を代表する作家・阿川弘之氏の娘で、TVでも活躍している阿川佐和子氏です。
本業はエッセイストのようですが、本書のような本格的な長編小説も手がけています。
化粧品会社に勤めながらも、恋人と婚約を交わした20代後半の波(なみ)の何気ない日常からストーリーが始まります。。
続いて波の妹で海洋生物研究所の助手である碧(あお)のストーリーと展開してゆき、その他にも総勢7名の女性が次々と登場し、オムニバス形式で物語が展開してゆく手法で書かれています。
タイトルのように婚約を前提とした恋愛もあれば、不倫という形の恋愛、結婚してからも続く恋愛、もちろん普通に付き合っている恋愛という形もあります。
しかし恋愛へ対する考えは、年齢や立場、そして性格などによって千差万別であり、女性作家ならではの切り口で彼女たちの心理を巧みに描写しています。
そして本作の主人公はあくまでも"彼女たち"であり、全編にわたって"男性の存在感が薄い"のも特徴です。
恋愛小説であるため当然のように多くの男性が登場しますが、彼らの行動や発言はあくまでも登場女性たちの視点を通じたものであるのが特徴です。
もちろん女性読者をターゲットとしている理由が大きいでしょうが、視点を"女性"に絞ることでストーリーの純度を高める効果もあります。
女性の(もちろん男性も)恋愛の価値観は人それぞれであり、"自由な恋愛"そして当然のように生じる"結果としての責任"というのが本書に一貫して流れるテーマのように感じます。
男性読者としても、オムニバスの最大の魅力である1章ごとにストーリーが切り替わることで飽きることなく最後まで楽しめますが、やはり女性が読むとより共感できるのではないでしょうか。
眠れぬ真珠
普段滅多に読むことのない恋愛小説というジャンル。
読書の秋ということで、思い切って手にとってみました。
著者の石田衣良氏は、どんなテーマで小説を書いてもテンポの良いストーリーで読者を惹きつけてしまうタイプの作家であり、普段は敬遠しがちな恋愛小説の敷居を低くしてくれるのです。
本作のヒロインは、45歳のバツイチ独身で版画家として活躍する内田咲世子(さよこ)。
3歳年上で画商の三宅卓治という愛人はいるものの、咲世子自身は結婚を諦め、仕事に徹した有能なキャリアウーマンといった感じの女性です。
その咲世子がある日、17歳年下(28歳)の青年・徳永素樹と出会った時から大きく日常が変化してゆくのです。。
登場する人物の年齢から分かる通り、「大人のための恋愛小説」であることはすぐに気付きます。
そして物語の設定も昼メロのようであり、少なくとも若者向けのラブストーリーや爽やかな青春小説の類ではありません。
そもそも恋愛小説を読み慣れている読者であれば、「眠れぬ真珠」というタイトルから雰囲気を推測できるかも知れません。
ともかくありがちな登場人物と設定という素材を目の前に、真正面から切り込んだ恋愛小説と表現できるかも知れません。
もちろんドロドロしたシーンが登場することもあり、読者によっては抵抗を覚えるかも知れませんが私はすんなりと読むことができました。
今の時代、20代後半と40代半ばの恋愛自体は珍しくありませんが、男性作家にも関わらず女性の心理に鋭く迫った描写には説得力を感じます。
ヒロインが私自身の立場とはかけ離れているのはもちろんですが、性別や年齢を超えて共感できるところが小説ならではの魅力であり、新鮮な読了感を得た1冊でした。
自省録
マルクス・アウレリウス・アントニヌス。
広大な領土を統治したローマ帝国の皇帝として、後世からは五賢帝の1人に数えられています。
当時から完全に政治や軍事機構が整備されていたローマ帝国でしたが、それゆえ皇帝が最終的な判断や決裁を行うことも多く、まるで大企業の社長のように忙しい立場でした。
もちろん皇帝としての権力を持ってすれば部下にすべてを任せ、自身は政務から離れて贅沢な生活を送ることも可能だったでしょうが、少なくともマルクス・アウレリウスは自らの責務を忠実に果たそうとしました。
ただしマルクス・アウレリウス自身は、ストア派のギリシア哲学に大きな影響を受け、本心は皇帝よりも学者として一生を送りたい願望を密かに抱いている内面的で繊細な精神の持ち主でもありました。
そんなマルクス・アウレリウスの著書として有名な「自省録」ですが、原題は「自分自身に」ということから分かる通り、元来はひとに読んでもらうためでなく、自分自身への戒めや感慨などを綴った手記として記録されたものです。
そんな自省録の和訳として1956年に岩波文庫から出版され、多くの重版を重ねている神谷恵美子氏による本書「自省録」は日本でもっともスタンダードな1冊です。
ローマ帝国という広大で強力な組織を統べる立場としての重責はとてつもなく重いものでしたが、彼が個人としてどのように考えを持ち、また反省しながらどんな理想を目指そうとしたのかが、よく分かる本です。
引用しやすい箇所を少し紹介してみます。
何かするときいやいやながらするな、利己的な気持からするな、無思慮にするな、心にさからってするな。君の教えを美辞麗句で飾り立てるな。余計な言葉やおこないをつつしめ。なお君のうちなる神をして男らしい人間、先輩の人間、市民であり、ローマ人であり、統治者でもある人間の主たらしめよ。(第3巻 5章)
ローマ帝国としての絶大な権力を乱用することを戒め、常に熱心でありながらも謙虚であり続けようとした心境がよく表れています。同様の記述は何度も本書の中に登場します。
もっともよい復讐の方法は自分まで同じような行為をしないことだ。(第6巻6章)
人の誤りを出来る限り許そうと務めた心優しい皇帝であると同時に周りの空気に流されず、自らの良心や理性によって慎重に物事を判断する哲学を持っていました。
昔さんかに讃めたたえられた人びとで、どれだけ多くの人がすでに忘却に陥ってしまったことであろう。そしてこの人びとを讃めたたえた人びともどれだけ多く去ってしまったことであろう。(第7巻6章)
後世からも讃えられるような存在からも無縁でいたいという、名誉欲さえも彼は自分の中から追いだそうと努めていました。
これはそのまま本書に幾度となく登場する彼の死生観に繋がっています。
どんな立場であれ、この本を読む読者が何らかの責任を果たさなければならない立場であり、またその重責や煩わしさに苦悩しているのなら、本書は多くの示唆と勇気を与えてくれます。
2千年近くが経過している現代においても、当時のローマ帝国皇帝ほどの責任を背負っている人は殆ど居ないはずなのですから。
龍馬を創った男 河田小龍
坂本龍馬がもっとも影響を受けた人物は?
真っ先に思い浮かぶのは龍馬が師として仰いだ勝海舟ですが、福井藩主・松平春嶽も外せません。
もしくは武市半平太、中岡慎太郎といった同志、西郷隆盛や桂小五郎といった盟友だったも知れません。
その中で藩士でもなければ明治維新で活躍した志士でもない、土佐城下に住む絵師である河田小龍を挙げる人は、なかなかマニアックではないでしょうか。
小龍は少年の頃から絵師を目指す傍らで、学問にも熱心に取り組みます。
長崎でオランダ語を学んだことをきっかけに、土佐の漁師として漂流し10年間ぶりに帰国したジョン万次郎(中浜万次郎)と起居を共にし、その見聞録をまとめた「漂巽紀畧(ひょうせんきりゃく)」は藩主の山内容堂をはじめ、当時の知識人たちに大きな影響を与えました。
つまり小龍は、土佐の中にいながら当時の知識人の中でも有数の海外通でもあったのです。
18歳で江戸へ剣術修行へ向かい、19歳に土佐へ一時帰国した坂本龍馬が小龍からはじめて海外情勢を聞き、後年の海援隊(亀山社中)の構想を得るにあたり大いに影響を受けたというのが、本書のテーマにもなっています。
残念なことに小龍の日記の大部分が2度の災害で焼失しているため、きわめて資料が少ないというのが現状のようです。
それでも小龍の塾(墨雲洞)からは、長岡謙吉や近藤長次郎といった海援隊で隊士となる人物を多く輩出していることからも、小龍と龍馬の強い結びつきを推測することができます。
小龍に活躍の場を与え世界情勢へ目を向けるきっかけを与えてくれたのは、山内容堂に重宝され参政として藩政改革を行った吉田東洋です。
東洋と小龍は互いに盟友と呼べる関係でしたが、東洋は自ら(墨雲洞)の門下であった武市半平太たちによって暗殺されるといった痛ましい経験をしています。
小龍を中心として墨雲洞には、今まで挙げた人物のほかにも後藤象二郎、板垣退助、岩崎弥太郎といった後の土佐の偉人たちが集い時世を論じ合ったといいます。
つまり河田小龍は幕末の土佐藩を語るにあたり欠かせない存在であり、長州藩の吉田松陰と松下村塾のように積極的に評価されるべきなのかも知れません。
魔王と呼ばれた男・北一輝
本書のタイトルにある通り北一輝をはじめて"魔王"と呼んだのは、有名な国家主義的思想家であった大川周明です。
戦後に過去を振り返って北一輝を次のように評しています。
北君は実に善悪の分別など母親の胎内におき忘れてきた人で天衣無縫というのは彼の事でしょう。
あるとき北君がひどく義理に外れた行為をしたので私が之を詰ると、義理人情に拘泥して革命ができるかというから、僕は之に反駁して、僕の革命は義理人情を回復するためにやるのだと言ったのがねえ、どうも危なっかしくて見ていられないことを平気でやる人だったですよ。
世の中には神がかりはあるが北君は魔がかりだと僕がいってから、人が彼を魔王と呼ぶようになりました。
まさに明晰な頭脳と人を魅了する弁舌、圧倒的な威圧感とカリスマ性を持った北は、人を惹きつけてやまない魔力を持った人物でした。
彼の著書「日本改造法案大綱」は、二・二六事件を引き起こした青年将校たちを感化し、北自身もその精神的な支柱として隠然たる力を備えていました。
一方で体制側の視点から見ると彼は革命家であり、また国家社会主義者であり、手段を選ばずに国家転覆を企てたテロリストとして見なされてきました。
もっと分かり易く表現するなら北一輝は「暴力装置」そのものであり、恐喝やテロ、裏切りといったことを平然とやってのける狂信的な思想家ということになるでしょう。
しかし人間・北一輝の中身は複雑であり、独学によって思想体系を作り上げて革命家として奔走しますが、やがて熱心に日蓮宗を信仰し始め、彼の後半生は"現実と神仏の世界の狭間"に生き続けたといえます。
本書は今まで注目される機会の少なかった彼の著書「霊告日記」の記録を元に、北の持つもう1つの顔を考察した本です。
「霊告日記」は昭和4年4月27日から書き始められ、二・二六事件により北が逮捕される直前の昭和11年2月28日まで、ほぼ毎日記録された日記です。
その内容は異色なもので、北が法華経を唱え、妻すず子に降霊した神仏や神霊のお告げやヴィジョンが記載されています。
"お告げ"を行う存在も多彩で、観音やスサノオといった神仏から、西郷隆盛や大山巌、明治天皇、さらには宮本武蔵といった人物までもが登場するオカルトな内容です。
そう考えると確かに「霊告日記」を歴史的な検証を行う資料としては扱いにくいのですが、著者は「霊告日記」にこそ、北の判断材料や行動指針、そして潜在的な願望までもが含まれていると考え、詳細な考察を加えています。
さらに付け加えるなら本書は、北とその妻・すず子が持つ霊能力(予知能力)をある程度までは認めるといった解釈さえ許容しています。
これをどのように評価するかは読者に任せますが、本書を読む意義は充分あるように思えます。
とくに昭和初期の歴史は入り組んでおり、年表を並べて政治家と軍部が対立し、やがて軍の内部でも統制派が皇道派を抑えて権力を掌握し、太平洋戦争に突入するといった単純な図式では、歴史の半分しか理解できないのではないでしょうか。
血盟団事件における井上日召、五・一五事件における大川周明、そして二・二六事件における北一輝の役割や彼ら(民間右翼団愛)の横のつながりを知ることで、より立体的に時代の背景が見えてくるのではないでしょうか。
二・二六事件の結果、銃殺刑となった青年将校たちはその直前に「天皇陛下万歳」「大日本皇国万歳」と三唱したといわれますが、同じ運命を辿った北一輝は完全に神仏の世界に没頭し、ただただ静かに死を受け入れました。
一方で北が獄中で詠んだ句に「若殿に兜とられて負け戦」というものがあります。
"若殿"とは昭和天皇のことに他ならず、こうした句の中に北一輝という人間の凄みが垣間見れるような気がしてなりません。
水木しげるの妖怪101ばなし
タイトルから想像できると思いますが、水木しげる氏が101体の妖怪をイラストと共に解説している本です。
読書というより、フリーマーケットでたまたま入手してから、気の向いた時に眺めているといった感じです。
私にとって"妖怪の知識"はすべて水木しげる氏から得たといってもよく、小学生の頃は「ゲゲゲの鬼太郎」に夢中になった時期もありました。
"つるべ落とし"、"こなきじじい"、"一反木綿"、"ぬりかべ"、"小豆洗い"、"河童"などなど、、子どもの頃にみたイラストがそのまま掲載されいるのを見ると、懐かしさとともに改めて興味が湧いてきたりします。
劇画調でありながらも、どこかユーモアのある水木氏の画風は、そのまま私にとって"妖怪のイメージ"として定着しています。
水木氏は妖怪の熱心な研究家であると同時に、幼い頃から妖怪の存在を身近に感じることのできる繊細な心を持っていました。
少年向けに書かれた本にも関わらず、各地の民間伝承やその妖怪が登場する昔の書物を丁寧に解説し、また自らの体験をさりげなく紹介している点などは、大人が読んでも楽しめて好感を持てます。
もし"妖怪は昔の人びとの空想の産物に過ぎない"として片付けられてしまうのなら、人間が自然や昔から信仰されてきた神々(八百万の神)へ対する畏敬の念を忘れてしまった時であり、それはきっと悲いことに違いありません。
21世紀になった現在でも妖怪が町の片隅に、そして山奥や墓地にひっそりと生息し続けると考えた方が、豊かな気持になるということを教えてくれたのが水木しげる氏なのです。
どくとるマンボウ青春記
本ブログではお馴染みの北杜夫氏の"どくとるマンボウシリーズ"です。
タイトルから分かる通り、本書は北氏の青春時代を余すことなく書き綴ったエッセイです。
具体的には、旧制松本高等学校から東北大学にかけての学生時代を振り返っています。
旧制高等学校といえば白線帽と高ゲタ、ボロボロの学生服の上からマントをまとい、酔っ払いながら哲学議論をやったり、ストームと呼ばれるバカ騒ぎなどに代表される自由な気風で知られています。
さらには普段の振る舞いも粗野で野蛮であることを誇り、"バンカラ"という気風で知られています。
北氏の学生時代は、そうした旧制高校の時代に青春時代を送った最後の世代です。
一方で世の中は、日太平洋戦争とその敗戦によって多くの人びとが犠牲になり、深刻な物資不足に悩まされた"暗黒の時代"でもあったのです。
それでも若者の有り余る時間とエネルギーは、そんな暗黒の時代さえも明るく照らすようなパワーに溢れていました。
北氏らしいユーモア溢れる逸話が沢山収められていますが、中には当時の日記や俳句なども引用して、当時の多感な時期の心情も紹介されていたりします。
本書から幾つかのエピソードを拾って紹介してみます。
紙にイロハを書き、一本の箸を何人かで持って、
「コックリさま、コックリさま、お出でになりましたでしょうか。学期末の試験では誰と誰が落第(ドッペ)るでしょうか、お教え願います」
などと真剣にやっている光景は、どうしても尋常なものをはいえなかった。
普段はろくに勉強しない学生たちも、やはり落第は怖かったようです。
ある教師は、終戦の翌日、生徒たちを整列させておいてこう述べた。
「負けるが勝ち、ということもある」
幼稚園ではあるまいし、この訓話もちょっとひどすぎる。今となって思えば、この文句もあんがい深い意味がありそうに見えるが、そのときその教授はたしか幼稚園の先生の水準において述べたのだ。
旧制高校には色んな教師がいたようです。
もちろん生徒が先生に酷い仕打ちをすることも珍しくありませんでした。
西寮の末期に、一人が言いだした。
「どだい女というものは不潔で低級なものだ。そんなものを愛するのは俗物のやることだ」
もっとも彼のそのばに本当に低級な女性であれ一人現れれば、彼はそんなことを言わなかったろう。
「われわれはすべからく少年を愛さねばならぬ。これこそ高邁なギリシャの少年愛(クナーベン・リーベ)である。」
私たちはこれに賛同の意を表した。
男だけで寮生活を続け、さらにまったく女性からモテないとなると、こうした方向に暴走するのもしょうがない気がします。
著者が青春を過ごした時代から70年が経過しますが、今もまったく色褪せることのない、現在の学生が読んでも共感できる名著ではないでしょうか。
韓非
中国の戦国時代末期に登場した"韓非"。
日本では"韓非子"と呼ばれる機会の方が多いかもしれません。
私自身、"韓非"に興味を持ったというよりも、貝塚茂樹氏の著書を通じて中国思想史に触れてみたいという動機で読み始めた1冊です。
貝塚氏は著名な学者でありながらも一般読者人にも分かり易く解説してくれる著書が多く、中国史古代史に興味がある方であれば、是非彼の著者を読んでみることをお勧めします。
韓非の著書を読んだ秦王・政(のちの始皇帝)は感動して傾倒しますが、秦を訪れた韓非を脅威に感じた李斯の讒言により、毒殺されるという数奇な運命を辿ることになります。
それでも彼の法治主義の思想は、秦の国家統治の政策に採用されることになります。
法家の源流は、斉の管仲、鄭の子産、魏の呉起、秦の商鞅などに求めることが出来ますが、彼らはいずれも政治家や将軍として活躍した人物であり、学者として思想を確立することはありませんでした。
法家を思想として完成させたのが韓非であり、諸子百家の中では後発であるため、彼の思想はさまざまな影響を受けており、彼の著書である「韓非子」を過去の研究内容や最新の考古学の成果を元に厳密に検証してゆくといった手法で、韓非の思想を解説してゆきます。
従来は韓非は筍子とはじめとした儒家の影響を強く受けたとされてきましたが、貝塚氏は韓非の若い頃は道家に、その後は管仲や商鞅に影響されたという説を主張しています。
具体的な内容は少し専門的な内容になるため、興味のある方は本書を読んでみてください。
秦の始皇帝が中国全土を統一する直前に法家の思想家として活躍した韓非の生きた時代は、群雄割拠による戦乱が終わると共に、中国思想史の黄金期である諸子百家が終焉を迎える時代でもありました。
しかし韓非の生まれた韓は、秦や魏、楚といった強国に囲まれた危機存亡にある小国であり、溢れる才能を持ちながらも志を遂げることは出来ませんでしたが、2000年以上の時を経て彼の著書の知ることは決して無駄ではないと思います。
ちなみに法家の源流となった管仲や子産、商鞅らは宮城谷昌光氏によって小説化されているため、壮大な春秋戦国時代に興味のある方は是非こちらも読んでみることをオススメします。
本田宗一郎の真実―不況知らずのホンダを創った男
「ホンダ」の創業者といえば本田宗一郎ですが、彼の右腕以上の存在として"実質的にホンダを経営"していのが、藤沢武夫だったことは広く知られています。
本田は会社の実印を藤沢に預け、自身は現場の技術屋に徹し続けました。
もちろんこれは2人の間で了承されていたことであり、本田は藤沢に背中を預けることが出来たからこそ革新的な技術を生むことが可能になり、経営を一任された藤沢の裁量だからこそ2度に渡る大きな経営危機に際して資金繰りできたのです。
タイトルからは分かりにくのいですが、本書は本田・藤沢の生い立ちから出会い、そしてホンダにおける数々のエピソード、引退後の生活に至るまで、元社員たちの証言も交えて迫ったノンフィクションです。
この2人は創業から間もない頃こそ頭を突き合わせて「ホンダ」の未来を構想し続けましたが、成長軌道に乗るにつれ殆ど顔を合わせる機会が無くなり、本田は工場に、藤沢は本社でいることが常でした。
また注目されることの好きな技術屋・本田と、控えめで冷静な経営者・藤沢は正反対の性格であり、そのマネジメント手法や遊び方すら違うものであったため、2人の間には不仲説が噂されたほどです。
実際2人から発せられる命令が正反対であることもしばしばであり、もし同じ場所で働いていたならば衝突を避けられなかったに違いありません。
彼ら2人もそれを充分に認識し、組織のNo1とNo2が正面衝突することを避けるために意図的に距離を置いていたようです。
しかしそれすらも大同小異であり、「ホンダ」を世界的な自動車メーカーに成長させるという2人の目的は完全に一致していました。
普通の企業であれば"2人のトップ"が存在することは考えられませんが、実際に「ホンダ」を成長させることで自分たちの正しさを証明したのです。
何よりも息がピッタリと合っていたエピソードとして、後継者たちに会社経営を託すことを決め、同じタイミングで会社を引退したということが挙げられます。
もちろん2人の間に挟まれ苦労した社員たちもいましたが、同時に彼らも2人の関係や性格をよく理解していました。
光り輝くスポットを浴び、世間から注目され続けた本田宗一郎。
そして実質的に人事や財務において本田以上の権力を持ちながらも、影武者に徹した藤沢武夫の人生を対照的であり、ノンフィクションよりも、まるで小説の物語のような気がしてきます。
私自身も社会人としての月日を経るにつれ、性格や流儀は違えどもお互いの距離を保ちながら認め合い、尊重するといった関係が何となく理解できるようになった気がします。
本田宗一郎と「昭和の男たち」
自動車メーカとしての「ホンダ」、そしてその創業者としての本田宗一郎。
数々の伝説的なエピソードの中で、昭和36年(1961年)に果たしたマン島TTレースの初優勝をもっとも有名なエピソードとして挙げる人が多いのではないでしょうか。
当時のマン島TTレースは世界でもっとも権威のあるバイク競技であり、ようやく戦後の復興期から脱しつつあった当時の日本が優勝することなど、世界中の殆どの人が予想していませんでした。
しかも従来のタイムを大きく更新し、125cc、250ccの両クラスにおいて1~5位までを独占する"圧倒的な優勝"でした。
今でこそ日本の技術力が世界的に評価されていますが、当時のようやく成長期に入ったばかりの日本の技術力は欧米に比べて大きく遅れている状態でした。
その中で本田宗一郎と中心とした「ホンダ」の成し遂げた功績は、単に一企業としての評価に留まらず、国家的な偉業と評価しても決して大げさではありませんでした。
本書は、日本のバイクメーカの中でさえ後発だった「ホンダ」が戦後荒廃の中で創業し、わずか15年足らずの間に自社開発したエンジンで世界の頂点を極めるまで、つまりホンダ初期の成長期を描いたノンフィクションです。
そこには先見性のある技術力や優れた販売戦略、緻密な経営によって世界の頂点を極めたというスマートなイメージはありません。
むしろ泥臭い根性と情熱で成し遂げた"昭和スポ根"のような風景が見えてきます。
怒りにまかせて職人を殴りつける宗一郎、馬力の上がらないエンジンとの格闘、未知の海外レース環境に苦戦するチームなど、何もかもが困難の連続であり、ホンダ社員たちは衝突、葛藤を繰り返しながらも、その壁を1つ1つ乗り越えてゆきます。
それはまるで目標に向かって一直線に進む純粋なエネルギーのようなものです。
ホンダの躍進は、戦後に復興と成長してゆく日本の姿と重ねられることが多いですが、まさしくその通りだと思います。
一方で現在において、当時のホンダと同じような状況を再現するのは困難だと思わずにはいられません。
連日工場に泊まりこんで食事とわずかな睡眠以外すべてを仕事に捧げる毎日、失敗すれば容赦なくハンマーで殴られる理不尽な職場は"ブラック企業"と今日であれば言われるでしょう。
しかし当時は娯楽はおろか物資さえ不足しており、働く場所があるだけで幸せだった時代だったのです。
豊かであっても未来の幸福を確信するのが難しい現代、貧しくても明日の可能性を信じることの出来た戦後の日本。
現代の私たちから見ても、そんな彼らの姿が羨ましくさえ思ってしまいます。
高邁な理論ではなく、ダイレクトにそしてシンプルに"働く"ことの意味を教えてくれるような1冊です。
孟子
以前ブログで貝塚茂樹氏の「孔子」を紹介しましたが、孔孟思想と称されるように儒教において孟子は、孔子に次いで重要な人物です。
ちなみに「孟子」は、儒家・孟子の人名であり、彼自身が書き残した著書名でもありますが、本書「孟子」は、"孟子自身の生涯"に触れつつも、その大部分は"著書としての孟子"を解説しています。
孟子は孔子の死後約100年後に生まれた人物のため2人の間に直接的な師弟関係はありません。
また孟子の生きた戦国時代は、孔子の生きた春秋時代と大きく異なる点がありました。
それは中国思想の黄金期ともいえる諸子百家が活躍した時代だったということです。
百家争鳴といわれるように、墨家、法家、道家、縦横家などに代表される学者や思想家が諸国を遊説し、戦国七雄に代表される国々も身分や出身地にこだわらず優れた人物を求めていました。
それは一人静かに学問や思想を追求する時代は終わり、各派が積極的に教説をアピールし続けなければならない時代に入ったことを意味します。
そのためか書物としての"孟子"には、他流派との論争、諸国の王や大臣を説き伏せる場面が多く登場します。
つまり体系的な儒教の教えというよりも、レトリックを駆使して儒教の正当性を主張する内容が多く見られ、"学者"としてよりも"雄弁家"として孟子が強く印象に残ります。
魏の恵王が政策を問う場面において孟子が例えとして用いたのが「五十歩百歩」であり、現在も有名なことわざとして使われています。
ほかにも「去る者は追わず、来る者は拒まず」といった言葉も孟子から生まれています。
中国古代史の第一人者である著者(貝塚茂樹氏)の手による「孟子」のすぐれた現代語訳、そして簡素で分かり易い解説からなる本書は、孟子を知るためのベストな1冊だと思います。
マンボウ恐妻記
タイトルから分かる通り、北杜夫氏が夫婦をテーマに執筆したエッセーです。
これまでも北氏のエッセーでたびたび妻(喜美子さん)が登場しますが、いずれも本書のように口論でも腕力でもかなわない文字通り"恐妻"として登場します。
しかし北氏は、躁鬱病であることで有名です。
憂鬱のときは気力が沸かず、無口で原稿も殆ど書けない状態に陥ります。
いったん躁になるとバリバリと仕事をこなし、それ以外にも次々と新しいことを始めます。
その結果、作家としての地位を築き上げながら借金を重ね、破産寸前まで株投資にのめり込むことになります。
普通に考えれば、これは尋常なことではありません。
それでも"恐妻"は北氏を見放すことはありませんでした。
つまりそんな北氏と40年にわたり暮らし続けた喜美子さんは、"恐妻"どころか"賢妻"ということになり、やはりタイトル自体が北氏ならではのユーモアであることが分かります。
北氏は精神科医としての資格と経験を持っており、あとから自らの躁鬱状態を冷静に見つめてユーモラスにしてしまうのが、彼のエッセーの真骨頂であるといえます。
1人娘の斉藤由香氏すらあとがきに「よくぞ、この夫婦は離婚しなかったなと思う。」と書かれるほど波瀾万丈に満ちた夫婦生活を楽しく読むことのできるエッセーです。
パレスチナ
来年には第二次世界大戦が集結してから70年が経とうとしています。
日本も枢軸国として戦争に参加し多くの犠牲者を出したましたが、日本人の大半が戦争を知らない世代に入っています。
しかし20世紀後半~21世紀に入っても世界から戦争が絶滅したわけではなく、世界の各地が戦争が続いています。
本書のタイトルになっている「パレスチナ」はその代表的な例といえるでしょう。
"パレスチナ"は古くは"カナン"と呼ばれ、この地にユダヤ人によって建国されたのが"イスラエル"です。
パレスチナとは地域を指す言葉で、正確な国境が存在していたわけではなく古くより"カナン人(=パレスチナ人)"と呼ばれる人たち(人種的では大半がアラブ人たち)が暮らしてきました。
そこへイギリスをはじめとした西欧諸国がユダヤ人を後押して突然入植し始めたわけですから、元々住んでいたパレスチナ人との間に衝突が起こるのは、当然の結果だといえます。
中東戦争と呼ばれるイスラエルとアラブ諸国との戦争は、すべての原因がそこにあるといっても過言ではなく、著者は「パレスチナ問題を理解するためには、前世紀末(19世紀)からの現代史を見るだけで充分だと私は思っている。」と断言しています。
本書はイスラエル、そしてパレスチナ人キャンプと何度も取材に訪れた広河隆一氏が、イスラエルを建国したユダヤ人、そしてパレスチナ人との関係を中心に、それを取り巻くアメリカを含めた西欧諸国、そしてアラブ諸国を含めた戦争の真相へ迫るために書いた1冊です。
われわれ日本人が「パレスチナ問題」と認識しているのは、多くの先入観、そして偏った報道に歪められ、何よりも前提となる知識を持っていないことに本書は気付かせてくれます。
例えば"ユダヤ人"という言葉1つとっても、我々日本人は黒い服と帽子をかぶった白人を思い浮かべる人が多いと想いますが、実際のユダヤ人には白人、アフリカ系(黒人)もいれば、インド人、中国人に代表される黄色人種の人びとさえいるのです。
"ユダヤ人"とは、ユダヤ教徒という宗教的な集団を意味し、キリスト教徒やイスラム教徒のユダヤ人は存在しないのです(つまりイスラエルから"ユダヤ人"とは認められません)。
また多くのパレスチナ人の土地を一方的に没収し、そこへユダヤ人が入植したため多くの難民が発生し、イスラエル国内に残ったパレスチナ人たちも経済格差に苦しめられています。
さらにパレスチナ人たちは土地を没収され、理由もなく警察に拘束されても"合法"とされる法律の中で生きているのです。つまりイスラエルにはユダヤ人以外に"法の平等"は存在しません。
もっとも悲劇的なのは、イスラエルによる無差別空爆、無差別虐殺であり、テロリスト掃討という名目の元に無実の多くの人間が殺害されているのです。
パレスチナ人たちもPLO(パレスチナ解放機構)を組織してイスラエルへ武力闘争を続けていますが、圧倒的な軍事力を誇るイスラエルとの戦力差は歴然としており、自爆テロというさらなる悲劇を生んでいます。
イスラエルにとってもユダヤ人の生存を賭けた戦いである以上、一切の妥協は許されないという姿勢も理屈では成り立ちますが、それにしても多くの市民が犠牲になる現状には疑問を抱かざるを得ません。
本書は1987年に出版されて30年近くが経過しようとしていますが、状況が改善しているとは言えず、平和からはほど遠い状況であることに変わりがありません。
つい最近(2014年7月23日)にもイスラエルよるパレスチナ・ガザ地区爆撃によって多くの市民が犠牲になり、国連の人権理事会でイスラエルを非難する決議案の採決を行った際に、日本政府は"棄権票"を投じました。
投票結果が賛成29、反対1(アメリカのみ)、棄権17だったことを考えると、実質的に日本は完全にイスラエル側(アメリカ含めた西欧諸国)の立場であったことが分かります。
わが国の政府が過去の戦争から学ぶことのできない愚かな決断を行ってしまったことが非常に残念です。
日本政府は人道的支援の立場からパレスチナ難民への支援を行っていますが、世界でもっとも悲惨な戦災が及んでいるも関わらず、国連平和維持活動(PKO)先として候補にすら上がりません。
パレスチナ問題を深く知ってもうために、1人でも多くの日本人に読んでもらうことを願います。
高野長英
鎖国状態の日本へ突如来航した黒船が当時の日本人へ大きな衝撃を与え、明治維新へのきっかけとなった。
漠然とこんな幕末のイメージを持っている人は多いのではないでしょうか?
たしかに黒船来航は象徴的な出来事ではありましたが、この出来事によって日本人たちが突然危機感を抱き始めて、新しい思想に目覚めたわけではありません。
黒船が来航する以前から、アジアで進行しつつあるヨーロッパ諸国の帝国主義と植民政策に強い危機感を抱き、優れた技術を外国から積極的に取り入れて日本を近代化すべきと考えていた知識人は決して少なくはありませんでした。
高野長英は、その知識人たちの中でも代表的な役割を担い、佐幕派、尊王派といった垣根を超えて幕末の多くの志士たちへ思想面で多大な影響を与えました。
高野長英といえば同じく蛮社の獄で幕府から弾圧された渡辺崋山と一緒に言及されることが多いですが、両者が活躍した内容はだいぶ異なります。
渡辺崋山は田原藩の家老という立場で開明的な考えを持ち、蘭学者たちのパトロンや指導者として活躍しました。
一方の高野長英は蘭学医を目指すためシーボルトの門をたたき、やがて武士としての家督さえも捨ててヨーロッパ列強国の技術や政策を精力的に学び翻訳を行った学者として活躍した人物です。
この2人に共通するのはその考えがあまりにも先進的であり過ぎ、当時はまだ盤石だった江戸幕府から反体制の人間として弾圧され、非業の死を遂げたということです。
ただし渡辺崋山は当時としては開明的な思想を持っていましたが、高い身分の武士であったことから最後まで封建制度の枠を脱却することが出来ず、主君(藩主)のために切腹したのに対し、高野長英は周到な準備の上で脱獄し、長く続いた潜伏生活の中でも自首を考えたことはありませんでした。
華山も長英も蛮社の獄が鳥居耀蔵を中心とした幕府内部の権力争いの犠牲者であることを知っていましたが、その立場や考え方には大きな違いがあったといえます。
長英は明治維新後に正四位を追贈されたことからも分かる通り、その死後に評価された人物です。
そのため伝記にある長英の姿は美化され、事実の信憑性が疑われるものが混じっているようです。
本書は信頼できる史料を検証し、伝聞といった不確かな要素をなるべく排除して書かれた、高野長英の等身大の姿に迫ることを目的に書かれた伝記です。
著者は蘭学に専念するために借金を重ね、酒と遊興のために浪費する長英の気質を、後世の学者である野口英世になぞらえて評価している部分などは、思わずニヤリとしてしまうほど説得力があります。
日本史好きの読者なら、幕末前夜に活躍した1人の偉大な蘭学者の伝記として是非抑えておきたいところです。
ブナの森を楽しむ
山道を車で走行していると、もっとも目にするのは整然とそびえ立つ杉林です。
もちろん人工的に植えられた木々であり、そこは薄暗く野生動物の住処という雰囲気は微塵も感じられません。
かつてブナは日本の森を象徴する代表的な木であり、ヒトを含めた多くの動物や昆虫たちの食料をとなり、そして多様な生態系を育んできました。
ところがブナを木材という商品価値で見ると、その価値の低さから急速に伐採されてその姿を消してゆきました。
特にブナの原生林に至っては殆ど残されておらず、白神山地が世界遺産に指定されたことからもその希少性が分かります。
本書は長年渡り森を研究のフィールドをしてきた著者(西口親雄氏)が、ブナの森の魅力を余すことなく伝えた1冊です。
専門的な内容が含まれるものの、ブナの特徴や見分け方から紹介してくれるため、一般読者でも取っ付き易い内容になっています。
ブナの木と共に暮らす日本特産種の昆虫たち、そこで行われる食物連鎖といった話題から、ヨーロッパのブナ林との比較、後半には森林管理に関する提言や、森を守るボランティア活動といった政策面についても言及しています。
例えばブナは多くの野生動物にとって貴重な食料源であり、ブナを中心とした本来の森が残されていれば秋に人間を襲うクマの被害は少なくなるでしょうし、杉一辺倒の人工的な針葉樹林ではなく、根をしっかりと張る広葉樹が植えられていれば、土砂災害を軽減することが出来たかも知れません。
さらに世界遺産に登録された白神山地へ観光客が押し寄せる現状にも苦言を呈しおり、あとがきでは貴重なブナの原生林を保存するために次のよう書いています。
日本のブナ林のなかでどこか一ヶ所ぐらい、入山禁止の原生林があってもよいのではないかと思う。その条件をもっともよく備えているのが、白神山地といえる。
しかし、白神山地のブナ林が、朝日連峰、熊栗山・裏八幡平・八甲田連峰のブナ林より、とくにすぐれているとは思えない。なぜおおぜいの人が白神山地に入りたいのか、理解に苦しむ。
~中略~
また一般の登山家に申したい。東北には、楽しいブナの森がいっぱいある。なにも白神まで行く必要はない。白神はクマゲラに返そうではないか。
森林と身近に接していない私を含めた多くの日本人にとって、ブナ森の本当の価値を気付く機会は殆どありません。
本書は、そのような読者の視野を広くしてくれる貴重な本ではないでしょうか。
孔子
前回紹介した「毛沢東伝」に続いて、貝塚茂樹氏による著書です。
本書の冒頭には次のように書かれています。
わが国をふくめて、およそ中国を中心とする極東の世界において、孔子の言葉を書き残した「論語」という本ほど長い期間にわたって、広い範囲の読者をもった書物はないであろう。
著者が指摘するように孔子の没後2500年が経過しているにも関わらず、未だに自己啓発書や経営書に「論語」を引用した箇所を多く見かけますし、江戸や明治においても武士や学者のもっとも基本的な素養は「論語」によって培われたといっても過言ではありません。
いわば東洋において「論語」は(広く読まれているという意味で)西洋の「新約聖書」にもっとも近い存在ではないでしょうか。
一方で、春秋時代後期に生きた孔子の生涯を知っている人は殆どいないのではないでしょうか。
つまり「論語」を引用する本を現代でもやたらに見かけますが、当時の時代背景や孔子自身の意図から飛躍して、完成された金言集として無条件に用いられることが多いように思えます。
私にとって本書は、そうした孔子や儒教へ対する先入観や誤解に気付かせてくれた1冊です。
まず"孔子=聖人"といったイメージは彼の死後に後世の弟子たちが作り上げたものであり、生涯に幾度もの苦汁をなめ、晩年に至っても一番弟子である顔回の夭逝を嘆き、"仁"の実践が自身においても容易ではないということを正直に告白している姿からは、等身大の人間像が浮かび上がってきます。
孔子が神の使いでもなければ、悟りを得た現世からの解脱者でもないことは、弟子の子路から"死"の意味を尋ねられた時の、次の言葉に集約されているのではないでしょうか。
いまだ生を知らず、いずくんぞ死を知らん。
つまり「いまだに生きることすら分からないのに、死のことが分かるはずないよ」ということであり、どこまでも謙虚であり、つねに生の中での実践を重視し続けた孔子らしい言葉でもあります。
また孔子の教えである儒教は為政者による帝王学であり、庶民が学ぶべき学問ではないという理解は間違っているということです。
これはしばしば論語に「君子は~」と書かれていることから誤解されることが多いのですが、著者によれば論語で用いられている"君子"は、そのほとんどが"道徳的な修養を続ける未完成の人間"の意味で用いられており、何よりも孔子自身が貴族といった出自ではありませんでした。
自らの追い求める最高の形を神や真理の中に追い求めたのではなく、夏や殷、周といった過去の王朝に理想を追い求めたとい点も特筆すべき点です。
著者は孔子への敬意は失わずに、学者としての立場から冷静で客観的な視点で孔子の生涯を描いています。
孔子について書かれた本は数多くありますが、本書が半世紀以上前に書かれた本にも関わらず、屈指の良書であることは間違いありません。
毛沢東伝
中国史学者である貝塚茂樹氏が毛沢東の前半生を研究して執筆した本です。
毛沢東への興味よりも貝塚氏の著書を読んでみたいという気持があり、たまたま最初に入手したのが本書だったというのが正直なところです。
貝塚氏は中国史(特に専門は古代史)の学者であり、のちに京都大学で名誉教授となりました。
すでに昭和63年に故人となっている方ですが、中国史の分野で後世の学者や作家に大きな影響を与えています。
本書が執筆された昭和32年時点では日本において毛沢東を歴史的に考察するという作業が殆ど行われていませんでした。
その先鞭をつけたという意味で価値のある1冊です。
具体的に本書で言及されている期間は、毛沢東の誕生した1893年から長征を終えて日中戦争に突入する1937年までです。
毛沢東の前半生は革命家として、後半生は独裁者としての顔を持っています。
つまり本書では毛沢東の革命家時代を言及しており、本書が発表された当時は百花斉放百家争鳴が開始されたばかりで、のちに批判の的となった大躍進政策は姿形もありませんでした。
列強諸国による侵略、中国を新しく支配しつあった国民党が存在する中にあって第三の勢力として登場した中国共産党ですが、その歴史は苦難の連続であったといえます。
蒋介石率いる国民党軍に包囲され立てこもった井崗山(せいこうざん)、劣勢の中で包囲網をくぐり抜けて敢行した長征は、毛沢東にとって薄氷を踏む思いの日々であり、その中にあって揺るぎない信念と絶望することを知らない強靭な精神力、そして大胆な戦略眼は英雄としての資質があったと評価するしかありません。
常に民衆と共に活動し続けた姿を言及する本書を読むと、どこか西郷隆盛と重なるイメージがあり、未だに中国人たちが敬意を抱く存在であることも納得できます。
少なくとも本書に書かれている範囲では、後に独裁者としての顔をもたげることになる彼の姿を感じることはできません。
それだけに留まらず毛沢東には、学者、思想家、教育者、軍人、詩人としての一面を持っており、その人物像はあまりにも巨大です。
世界的に見ても20世紀を代表する歴史的人物の1人であり、今後の中国史において秦の始皇帝や漢の高祖と比肩しうる重要な人物となることは間違いありません。
日中戦争という過去や現在の両国関係の冷え込みを考慮すると、特に日本人にとって現時点で歴史上の評価が難しい人物なのではないでしょうか。
ビタミンF
重松清氏の短篇集です。
本作に登場する主人公は、いずれも40歳前後の妻子のいるサラリーマンという設定です。
つまり平凡な人生を送っていると考えられている成人男性であり、著者の重松氏がもっとも本書を読んで欲しいと願う読者層でもあるのです。
私が子供の頃の40歳男性といえば完全な"オジサン"であり、"冴えない中年"という漠然としたマイナスのイメージしか持っていませんでした。
しかし自分が同じ年代になってみると、子どもの頃に抱いていた印象とはだいぶ違うことに気付きます。
学生時代のような体力こそありませんが、まだまだ老けこむ年ではありません。
自分より一回りは若い部下がいる一方、上の世代の人間も星の数ほどいます。
つまり典型的な中管理職の立場であり、勢いに身を任せられるほど若くもなければ、老練の策士にもなりきれない中途半端な時期なのです。
しかし本書に登場するような妻子ある中年サラリーマンであれば、仕事の最前線でそれなりの責任を任せられている立場であり、子育て真っ最中の時期だけにやがて訪れる受験や進路を考えなければいけませんし、教育費や家のローン含めた経済的な不安、そして老年に差し掛かった両親に健康上の問題があれば、それも心配の種になります。
そんな中年男がふと立ち止まり過ぎ去った若い時代や、何となく見えてきた人生のゴールに思いを巡らすとき、すべてを投げ出したくなる衝動が出てきても不思議ではありません。
本書に登場する主人公たちは決して"カッコいいヒーロー"のような存在ではありませんが、直面した問題に正面から向き合い、時には家族や同僚の力を借りながら泥臭く乗り越えてゆく物語が収められています。
見方を1つ変えれば、人生でもっとも忙しくプレッシャーを感じる日々は、もっとも充実した日々であり、それを"青春"と表現しても間違いではありません。
架空の栄養素"ビタミンF"を物語というカプセルに詰め込んで日本の中年男性に届けたい。
そんな作者の想いが充分に伝わってくる1冊です。
影法師
「永遠の0」、「BOX!」によって一躍国民的作家となった百田尚樹氏の長編小説です。
舞台は江戸時代の8万石の茅島(かやしま)藩。
そこで筆頭国家老を務める名倉彰三は、下士の身分から異例の抜擢を受け、干拓事業と藩財政の立て直しの功により、揺るぎない地位を築きました。
初老に差し掛かった彰三には、少年の頃よりの竹馬の友として、また尊敬する憧れの存在として磯貝彦四郎という人物がいつも心の片隅を占め続けていたのです。
その彦四郎は20年以上も前に不始末により藩を逐電し、つい最近になって困窮の中で労咳のために亡くなったという噂を聞きます。
そこから今まで彰三が知ることのなかった彦四郎の過去が明らかになってくるのです。。
ちなみに"茅島藩"というのは、物語の内容から日本海に面した近畿地方から北陸地方のいずかに存在する架空の藩という設定です。
本書には「永遠の0」との共通点があります。
それを一言で表すと"自己犠牲"であるといえます。
零戦に特攻隊として乗り込んだパイロットたちは、国家や家族のために自らの命を捧げました。
また誤解を恐れずに言えば、武士たちもまた国(藩)や名誉のためには、自らの命を断つことを躊躇しませんでした。
自身の成功や幸福を追求する啓蒙書が溢れる現代において、他人に自身の夢を託し、そのために自らの人生を犠牲にする生き方は考えられません。
百田氏は打算的で効率よく生きることが"賢い人生"とされる風潮に疑問を投げかけ、かつての日本人が持っていた価値観を再認識し、自らを犠牲にする生き方が多くの人びとを感動させるという事実を作品を通じて証明したかったのではないでしょうか。
タイトルの「影法師」は、それを象徴的に表しているといえます。
大きな伏線で構成されている物語のため詳しい内容は書きませんが、大胆なストーリー構成、そして初の時代小説という試みには、小説作家として円熟しつつある百田氏の勢いが伝わってきます。
個人的には少しストーリーを綺麗にまとめ過ぎている印象を持ちましたが、これは読者の好みの問題かも知れません。
今もっとも多くの読者に受け入れられている作家であり、「永遠の0」に共感した読者であれば是非本書も抑えておきたいところです。
病牀六尺
病床六尺、これが我世界である。
しかもこの六尺の病床が余には広過ぎるのである。
有名な書き出しではじまる正岡子規の随筆です。
結核による長年の闘病生活で殆ど寝たきりになった子規は、死の二日前までこの随筆を書き続けました。
すでに7年近くにわたり闘病を続けてきた連載開始の時点で、彼は自分が死の床にあることを悟っていました。
本書には壮絶な闘病の日々が記されていると思えば、実際には"絶望"という雰囲気は微塵も漂っていません。
それは何となく漂う"諦め"のようですが、実際には静かに"死を受け入れた心境"だったように思えます。
自身が苦痛により絶叫や号泣する姿、そして看病する母や妹への愚痴さえも風景を描くかのように綴っており、そこには強がりも恐怖も感じさせない自然な文章として表現されてゆきます。
俳人として、また文章家として写実(写生)を取り入れ、近代日本文学へ多大な影響を与えたといわれる正岡子規は、その最晩年の随筆に至ってそのスタイルを完成させたのかも知れません。
話題は闘病の日々、俳句の批評、新聞で読んだ時事に関すること、絵画の感想や食事の内容等々多岐に渡り、そのまったく衰えない好奇心に、その背景を知る後世の読者は驚かずにはいられません。
病魔により肉体は衰弱しても、その精神は最後まで衰えませんでした。
これは正岡子規の強靭な精神力と努力が成し遂げたものではなく、彼が持って生まれた性格や才能によるものだと考えるしかないのではないでしょうか。
本作品は青空文庫としても公開されているため、気軽に手にとってみてはいかがでしょうか。
サロメの乳母の話
本書は塩野七生氏による歴史フィクション短篇集です。
歴史上の人物を近い位置で見ていた人(あるいは動物)が回顧して語るという面白い設定で書かれています。
本書に収録されている短編の題名からその設定が分かります。
(カッコ)は補足のために付け足してあります。
- (オデュッセウスの)貞女の言い分
- (新約聖書に登場する)サロメの乳母の話
- ダンテの妻の嘆き
- 聖フランチェスコの母
- ユダの母親
- カリグラ帝の馬
- (アレキサンダー)大王の奴隷の話
- 師から見たブルータス
- キリストの弟
- ネロ皇帝の双子の兄
そして最後には「饗宴・地獄篇」という短編が収められており、歴史上"悪女"と評された女性たちが、地獄で開催される夜会で一堂に会するというユニークな設定で書かれています。
歴史上の人物を主体的に描くのではなく、別の視点から描くことでユーモラスを取り入れ、歴史を敬遠してしまう人でも読みやすい内容になっています。
もっとも著者自身にはそういった意図はなく、単に遊び心で試みただけかも知れません。
「ローマ人の物語」に代表される壮大なスケールの歴史小説で有名な塩野氏ですが、案外こうした短編作品の中にこそ自身の人物評や歴史観を率直に表現しているのかも知れません。
歴史を楽しむ秘訣は想像力であることを再認識させてくれた1冊です。
アフリカの蹄
帚木蓬生氏のサスペンス作品です。
主人公はアフリカ最大の医療研究所へ心臓外科医として勤務している日本人医師・作田信。
ある日、近くの黒人居住区の間で突如奇妙な発疹が流行り出す。
その正体は絶滅したはずの天然痘であり、その裏には巨大な陰謀が存在するのであった。。。
そして日本人医師・作田はその陰謀へ立ち向かうことを決意するのであった。
導入部のあらすじは大体こんな感じですが、著者が本書で取り上げているテーマは明確です。
それは南アフリカのアパルトヘイト(人種隔離政策)であり、白人優位の社会政策によって虐げられる黒人たちに焦点を当てています。
そこにジェノサイドやホロコーストといった要素を入れることによって、スケールの大きなサスペンス作品としての背景を構成しています。
本来であれば、こうした巨大な陰謀に立ち向かうのは特殊な戦闘訓練を受けた兵士やスパイといった主人公が相応しいのですが、武器すら持たない"一介の日本人医師"であるというのが、箒木氏らしい設定です。
もちろん著者自身の職業が"医師"であることも関係していますが、そこには"暴力"へ対しては"非暴力"で抗議するといったメッセージも込められています。
本作品が発表されたのたは1992年であり、著者が意欲的に長編サスペンス作品を描き続けた時期であることから"勢い"を感じます。
それでも安易にスリルを求めず、世界中に根強く残る人種差別といった重く深いテーマを掘り下げてる部分は、著者個人の道徳観、そして自身の職業である医師としての良心が垣間見ることができます。
風花病棟
本ブログで何度か紹介している箒木蓬生(ははきぎ ほうせい)氏の作品です。
本書には短篇が10本収められていますが、おもに長編を発表することが多い著者の作品の中では珍しい1冊です。
箒木氏自身が精神科の開業医であることをから医療をテーマに扱った作品が多く、それは本書にも当てはまります。
客観的に見れば、医師は患者の病気や怪我を治す立場であり、患者は治療を受ける立場です。
また私を含めた大部分の人が当てはまる患者の主観からすると、医師はどこか距離感を感じる存在でもあります。
それは医師が治療に対する専門知識や技術を持っており、状況によっては自分たちの生命を委ねざるを得ない"特別な力"を持った人間という意識がそうさせてしまうのではないでしょうか。
彼らの素顔が"普通の人間"であることを頭では理解していても、いざ自分が患者になったときのこうした感覚は拭うことができません。
分かり易くいえば、医師と患者との間に横たわる明確な上下関係を感じてしまうのです。
一方で医師にとって患者は「お客様」であるという考えも、医療の中に商業主義が入り込んでいるような気がしてイマイチしっくり来ません。
本編に収められた作品は、どれも患者と向き合う医師をテーマに書かれおり、そんな私の迷いを感動と共に少しずつ氷解させてくれるような作品が並んでいます。
著者はあとがきで次のように述べています。
病気は即苦悩と直結する。
患者は悩み、苦しみ、それでも生きていかなかればならない。
医師が心打たれるのは、そうした患者の懸命な生き方なのである。百の患者がいれば百の悩みがあり、それぞれに課せられた問題に懸命に立ち向かう姿を、医師は見せつけられる。
私は、まさにここにこそ、<患者こそが教科書>という言葉の本当の価値があるのだと思う。
医師は患者によって病の何たるかを教えられるのではなく、人生の生き方を教えられるのである。良医は患者の生き方によって養成されるのだ。
箒木氏の優れたところは、自らが信念として持っている患者との向き合い方を優れた小説として表現できるところです。
本書に収められている作品は、スーパードクターが難病を手術によって治療するようなストーリーは1つも収録されておらず、どこまでも地に足を着けて医療現場を描こうとしている姿勢にも共感が持てます。
すべては一杯のコーヒーから
著者の松田公太氏による起業ノンフィクションです。
内容については本書の紹介文をそのまま引用させていただきます。
27歳で起業を志し大手銀行を退職した青年は、体当たりの交渉でスペシャルティコーヒーの日本での販売権を得た。本書ではじめて"スペシャルティコーヒー"という単語を知りましたが、簡単に説明すると高品質なコーヒー豆を使用し、焙煎から抽出までを高いレベルで実現したコーヒーのことを指します。
銀剤に待望の1号店を開業した後は、店内に寝袋を持込み泊まりこみで大奮闘。
ビジネスにかける夢と情熱は、コーヒーチェーンを全国規模にまで大成長させた。
金なし、コネなし、普通のサラリーマンだった男になぜできたのか?
感動のタリーズコーヒージャパン起業物語。
価格も品質に比例するため、300円~500円くらいのメニューが一般的ではないでしょうか。
"スペシャルティコーヒー"の分野では、スターバックスが有名なチェーン店ですが、同社が豊富な会社資金で日本上陸を果たしたのとは対照的に、タリーズは少ない個人資本によって日本出店を実現しました。
つまり信用度が低いため金融機関や不動産会社との取引は厳しく、失敗したときのリスクも高いことを意味します。
一方で組織の意思決定が迅速で柔軟であること、そして何よりも成功したときのリターンが大きいといったメリットもあります。
創業者であり代表取締役社長であった松田氏の生い立ちや起業に至るまでの経緯は、これから起業を目指す人のみならず多くのサラリーマンに勇気と感動を与えてくれます。
起業家が執筆した本の中でも高いレベルの作品だと思います。
ただし個人が起業した会社が急激に成長してゆく過程で社内意見の食い違いや同業者たちとの対立は避けて通ることは出来ず、決してキレイ事だけでは成功できません。
本書で紹介されている内容以外にも多くのキレイ事では片付けるのできない出来事があったことは間違なく、起業家の本を読むときに気をつけて欲しい点です。
ちなみに松田氏は2006年にタリーズの代表取締役を退任し、現在は参議院議員として活動しています。
またタリーズコーヒージャパンは、飲料メーカ・伊藤園のグループ会社として現在も順調な成長を続けているようです。
もちろん私がその心境の変化を知る由もありませんが、松田氏にはタリーズ起業の時と同じ情熱を持って政治に取り組んでもらいたいと願うばかりです。
孫ニモ負ケズ
北杜夫氏が1人娘に誕生した初孫"ヒロ君"との日常をエッセー風に描いた作品です。
もちろん祖父にとって初孫が可愛いには違いありませんが、それを素直に書き記す作家でないことは、氏の作品を何冊か読んできた読者であれば容易に想像できます。
子どもは3歳にもなれば飛び跳ねて遊び始めますが、北氏は歳をとり体が思うように動かなくなっています。
加えて長年にわたって躁鬱病を患っているため、精神的にもヒロ君の天真爛漫さについてゆく気力もありません。
やがてヒロ君の元気さに圧倒され、両親との関係と違った独特の関係が築かれてゆくのです。
孫にとって組み易い格好の遊び相手であり、著者にとってみれば自らは孫の"オモチャ"であり、そんな境遇を嘆いて「悲劇のジイジ」としての日常を綴っていきます。
もっとも北杜夫氏は若い頃より自虐的でユーモア溢れるエッセーを得意にしていましたので、老いたとはいえスタンスはまったく変わっていません。
孫にとって「威厳のある祖父」という存在よりも、身近で親しみやすい「ダメなジイジ」であり続けたいという著者の願いが込められた1冊です。
歴史の世界から
本書は司馬遼太郎氏のエッセイと紹介されていますが、実際には少し異なります。
本書は昭和35年~55年にかけて新聞や雑誌、そして書籍の解説として司馬氏が執筆した文章が1冊にまとめられたものです。
決められたテーマに沿って書かれた文章が殆どですが、そのテーマが多岐にわたるため結果的にエッセイ集という形で出版されています。
本書には「国民的作家」と評された、司馬氏の飄々とした、そして独特な表現で筆を進めてゆく文章をたっぷりと堪能できる1冊です。
言うまでもなく司馬氏は歴史小説を専門分野にしてきましたが、その独自の視点が多くの日本人に影響を与えベストセラーを次々と生み出しました。
個人的には、自身の考えを率直かつ大胆に表現する物言いが好きです。
本書でいえば大阪城を
この城が栄えた時代というのは、貧乏くさい日本史のなかで、唯一といっていいほど豪華けんらんたる時代だった。
と表現し、まったく別の話題でオーストラリア首都の印象を
私の予備知識ではキャンベラは万博会場のように人工的な町で、行ったところで人間のにおいは希薄だろうということがあった。
といった具合で表現し、しかもこの表現を結論としてではなく、いきなり冒頭や文中に登場させるのが、いかにも司馬遼太郎らしさを感じます。
同時に自分の考えを誤解されたくない場合(主に自分自身の身の回りの出来事)には、必要以上に遠回しな表現をしてしまうのも司馬遼太郎らしさといえます。
本書でいえば、自身の先輩で恩師ともいえる海音寺潮五郎氏への回想にその特徴がよく表れています。
最初に作品を評価してくれた海音寺氏へ感謝を伝えたい気持ちがある一方、当時作家として未熟だったことを自分自身が一番認めているという葛藤が、次のように文章を結ばせています。
以上のようなことは私事のなかでも門外に出す必要のない私事に類している。
ことごとしく書いてひとに読んでもらったところでなんの意味もなさないとおもっているが、氏の全集の読者のためには多少の意味をなすかもしれないとおもって、あえてこの話題をえらんだ。
司馬遼太郎氏の文書は総じて散文的でありながらも、その独特のリズムに引き込まれてしまうと、まるで近所を散歩しているかのように歴史の舞台を身近に感じる不思議な錯覚を与えてくれます。
デカルト
本書は約50年前に初版が発行されていますが、何度も重版され続けているデカルト入門書のスタンダードといえる1冊です。
著者は京都大学の名誉教授であった野田又夫氏です。
デカルトは17世紀前半に活躍したフランスの哲学者であり、数学者としても知られています。
その理論的かつ明快な姿勢から、近世合理主義哲学の開祖とされています。
有名な著書に「方法序説」があり、その中の「我思う、ゆえに我あり」は彼の思想を表す有名な言葉として知られています。
本書ではデカルトの思想を解説するだけでなく、その生涯にも詳しく触れらています。
ただし専門知識として掘り下げるというよりは、本書の原型がNHKで放送された古典講座の原稿を元にしていることからも分かる通り、必要十分な教養知識として網羅しているレベルのため、"哲学"を題材にした本の中ではそれほど難解な内容ではありません。
デカルトの生きた時代を前後してガリレイやニュートンが活躍しており、ヨーロッパでは科学の時代の幕が開けようとしていました。
それでも当時は科学へ対する理解よりも、宗教的な世界観が大勢を占めていた時代でした。
実際にガリレイは異端訊問によって教会から有罪判決を受けるという悲運に見舞われます。
デカルト自身は数学者であったこともあり、カトリック教徒でありながらも哲学へ対する態度は科学者に近い立場でした。
つまり科学が大幅な進歩と便利さをもたらした後世の我々から見ると、デカルトの哲学は合理的、論理的であるがゆえに理解しやすいのです。
加えて後世へ大きな影響を与えた哲学者としても、専門家でない大多数の人にとってデカルトは"哲学の入り口"として最適ではないでしょうか。
宗教哲学入門
教養書からもう1歩踏み込んだ専門書に近い1冊です。
宗教を哲学的に考察するという内容に何となく興味を持って手にとった1冊です。
そもそも宗教哲学という体系的な専門分野があることを本書ではじめて知ったのですが、その起源は16世紀ドイツの有名な哲学者"カント"まで遡るようです。
特定の宗教を理論的に考察してゆく神学とは異なり、宗教哲学は宗教一般の真理、絶対有(もしくは絶対無)の本質を理解するための学問であるため、特定の宗教や宗派を批判することはしません。
とはいえ無数に存在する宗教を一括りにして考察するのは現実的ではないため、本書では世界三大宗教といわれる仏教、キリスト教、イスラム教を取り上げています。
前半では本書の前提知識としての世界三大宗教の生い立ちや教義の説明を行い、さらには個別に哲学的な考察を行ってゆきます。
中盤では宗教の提示する真理を虚構だとする(宗教批判の)哲学への反論を展開しています。
特にニーチェやマルクスといった代表的な無神論者に的を絞って、最終的には彼らの思想こそが反哲学的であると断じています。
後半では世界三大宗教を横断的に宗教哲学として考察してゆき、各宗教に共通する救済、絶対者、信仰、そして真理といった内容へ踏み込んでゆきます。
最終章では「現代という時代の深層ないし底流にあるものはニヒリズム・無神論なのである」とし、確かな価値を見出すことのできない時代だとしています。
情報化が進みリアリティが失われつつある現在は道徳が退廃しつつあり、その先に「第三次世界大戦=人類破滅」が潜む危険性さえ指摘しています。
大げさだと思う反面、現代の大勢を無神論が占めているという部分は否定できません。
瞑想や只管打坐による自力本願の実践、念仏や経文による他力本願を日常的に実践している人は、私含めて同年代にはまず見当たりません。
これは当然のようにも思えますが、日本が仏教国であることを前提とするならば、むしろ異常な状態なのかも知れません。
私自身に当てはめて言えば宗教による絶対的な救済を心から信じられないからであり、この気分は多くの現代人にも共通するのではないでしょうか。
一方で宗教を積極的に否定する理由も持たないのですが、一概に言ってしまえば宗教に対する"無知"や"無関心"が理由であることに尽きます。
とはいえ、いきなり熱心な信者となるのも現実的ではありません。
内容は少々難解ですが、私と同じ関心を持つ人であれば、宗教全般の本質を理解する一端として本書を手に取ってみるのもよいかも知れません。
南極風
前回の「未踏峰」引き続き、笹本稜平氏の小説です。
物語の冒頭は以下のような文で始まります。
ニュージーランド南島の西岸を貫くサザンアルプス -。ニュージーランドでトレッキングが盛んなのは知っていましたが、本格的な氷河があることまでは知りませんでした。
最高峰のマウント・クックをはじめとする三〇〇〇メートル級の高峰と無数の氷河を擁するこの山脈には、登山の対象となる山が数多い。ここマウント・アスパイアリングもそんな山の一つで、標高は三〇三十三メートル。広大な氷河を内懐に抱き、鋭く天を衝く頂きは南半球のマッターホルンの異名を持つ。
本書はそんなアスパイアリングを目玉にした日本人向け山岳ツアー会社「アスパイアリング・ツアーズ」で起きた山岳事故をきっかけにして起きるミステリー小説です。
どんなに知識や経験そして技術を持ってしても自然が相手である以上、山岳事故をゼロにすることは不可能なのかも知れません。
仮に吹雪によって遭難の危機を迎えた時、ビバークするのか下山するのか、また下山するのならどのルートを選ぶのか?
こうした判断の1つ1つが生死を分ける厳しい世界です。
本書はこうしたテーマを取り上げてミステリー小説化したユニークな作品です。
「アスパイアリング・ツアーズ」でツアー責任者の立場にあった森尾正樹は、ツアー中に起こった事故を巡って突如刑事責任を追求されることになります。
森尾にとって自分を告発した人間が謎であるにも関わらず検察が起訴するといった事態に陥り、見に覚えのないまま拘置所に抑留されることになります。
そこには検察当局(国家権力)との闘いも大きな1つのテーマとして含まれています。
何ら政治的な背景を持たない1人の人間が国家権力を相手にしなくてはならない。
森尾は、そんな自らの正義を貫き通す困難な道を選ぶのです。。
登山の描写は本格的な山岳小説そのものであり、実際の山岳事故を取り上げているかのようなリアリティと迫力があります。
現在と過去の回想場面が頻繁に入れ替わる手法で書かれていますが、ストーリー自体がそれほど複雑ではないため、むしろリズムの良さを感じます。
いろんな要素を楽しめる贅沢な小説であり、お勧めできる1冊です。
未踏峰
社会人として挫折を味わった橘裕也、アスペルガー症候群の戸村サヤカ、知的障害を抱える勝田慎二。
現代社会が彼らを寛容に受け入れることは難しいのかもしれません。
それでも北八ヶ岳で山小屋を営む通称"パウロさん"は、そんな彼らを好意的に受け入れます。
大自然の懐で質素ながらも充実した毎日を山小屋で過ごすうちに、彼らは生きがいを見つけるようになります。
やがてパウロさんたちは、みんなでヒマラヤにある未踏峰の登頂を目指すように提案します。
ただし未踏峰とはいっても6千メートル級の無名ゆえの未踏峰であり、それは決して快挙を果たすことを目的としたものではありません。
心に傷を負い人生の再起を誓う彼らが、再び自信を取り戻すための儀式として登頂を目指すのです。
そして何よりも裕也たちを受け入れたパウロさん自身が、世界的なクライマーとして活躍していた頃に負った心の傷を癒やすための儀式でもあったのです。
もちろん山は人間を癒やすために存在するのではなく、時には過酷な自然が人の命を奪うこともあります。
それでも小さな存在である人間は偉大な山へ畏敬の念を抱き続けるのです。。。
山の素晴らしさを綴っただけの物語ではなく、人間同士が助け合うことでお互いが救われるという大切なメッセージが込められている作品です。
壮大な自然は、そのきっかけを作ってくれる存在なのかも知れません。
ふたつの枷
終戦記念日が近づく暑いこの時期には、第二次世界大戦や太平洋戦争を扱った本を読むことを習慣にしようと考えています。
去年の夏には浅田次郎氏の「終わらざる夏」を読みましたが、今年はかなり前から古処誠二氏の作品を読むことに決めていました。
それは古処氏が戦争や自衛隊を題材にした作品を意欲的に発表している若手の作家であり、今まで何冊かの作品を読んでもその意気込みが伝わってきたからです。
ただし雰囲気は作品によってかなりの違いがあります。
本書「ふたつの枷」には、4つの短編~中編小説が収録されていますが、今まで読んだ作品の中ではもっとも"戦争文学"に近い印象を持ちました。
小説の舞台はビルマ、サイパン、フィリピン、ニューギニアとそれぞれ違いますが、いずれも太平洋戦争当を日本軍を中心に描いています。
著者は私とそれほど年齢が離れていないこともあり、当然のように戦争を体験した世代ではありません。
しかし作品中の描写はリアルさを感じる内容であり、特に日本兵をもっとも苦しめた飢餓やマラリアなどの風土病の描写をはじめて読んだときの迫力に驚いたことを今も覚えています。
本書に収められている作品はどれも単純なストーリーであり、意外性を持ったものはありません。
その分、兵士たちの置かれた状況や心理などがじっくりと描かれています。
彼らは屈強で選び抜かれた人間ではなく、おそらく現在の我々とそれほど変わらない民間人たちが徴兵によって強制的に兵士となったに過ぎません。
つまりたった2世代生まれる時代が変わるだけで、私も戦地で戦う経験をしていた可能性が高いのです。
もちろん戦争の体験など絶対にしたくありませんが、だからこそ本書を読む価値があります。
一般的に我々の世代が戦争へ無関心だという意見には私も同意せざるを得ません。
終戦記念日が近づくこの時期に是非おすすめしたい1冊です。
ニンジアンエ
著者の古処誠二氏がテーマとして取り上げることの多い太平洋戦争を背景に書かれた小説です。
小説の舞台はビルマ(現ミャンマー)です。
当時のビルマはイギリスの植民地でしたが、日本軍が大東亜共栄圏の確立を目的としてビルマへ進軍し、一時はイギリス軍を駆逐することに成功します。
いずれにしてもビルマ人にとっては自国の中で外国同士が戦争をはじめる訳ですから、彼らが一番の被害者であることは間違いありません。
日本軍やイギリス軍もそれを充分に自覚しており、宣撫班を組織して地元住民たちの理解と協力を得るための活動を続けてきました。
本作のストーリーは日本軍の宣撫班に同行する新聞記者の視点から書かれています。
一介の従軍記者の視点を利用することで日本軍、イギリス軍、そしてビルマ人といった3つの異なる立場に属する人間たちの思惑や行動を描いてゆきます。
実際には軍の中にも兵士や将校といった階級の違い、そして地元のビルマ人の中にも様々な立場をとる人びとがいるため、実際にはもっと複雑な構造になりますが、記者の視点から描くことで読者の頭の中を整理してくれます。
兵士たちは遠い祖国に家族を残して銃弾やマラリア、空腹の脅威に晒されながら、彼らなりの正義を掲げて異国で戦争を遂行します。
いずれにしても日本やイギリス兵士にとってビルマは祖国ではなく、最後は生き残って故郷に帰る希望を抱いています。
一方でビルマ人たちは?
いずれの国が戦争に勝利しようともビルマ人にとっては支配者の顔ぶれが変わるだけであり、彼らは生涯に渡ってそこに住み続けなければなりません。
つまり、どの立場にあっても誰も望まない状況を作り出すのが戦争の矛盾でもあるのです。
著者の古処氏は戦争という人災を淡々と描写してゆきますが、あえてそうすることで作品の中に痛烈なメッセージを埋め込もうとしているように思えます。
風の中のマリア
オオスズメバチ(学名:ヴェスパ・マンダリニア)。
昆虫の頂点に立つ獰猛な捕食者であり、人間にとっても危険な生物です。
本書はスズメバチのワーカー(働きバチ)を擬人化した"マリア"を主人公にしています。
マリアのワーカーとしての仕事は、幼虫のエサとなる昆虫を捕獲するハンターです。
スズメバチにとって無抵抗にも等しい昆虫もいれば、時には同類のスズメバチ、カマキリやオニヤンマといった危険な武器を持った昆虫さえも狩りの対象にしなければなりません。
そしてワーカーの寿命はたったの30日。
つまり主人公マリアの一生も30日であり、本書はそんなオオスズメバチの生涯を物語にするといった面白い手法で書かれています。
当然のように擬人化されたオオスズメバチは物語の中で喋ることもあれば思考することもあります。
オオスズメバチたちが自らの遺伝子(染色体)について話し出したときは少々驚きましたが、幼虫から成虫になるまで、狩りの方法、そして何よりも女王バチが1から"巣"という名の帝国を築いて、やがて滅びるまでの過程を壮大な物語として読むことで自然に知識を得ることができます。
オオスズメバチに猛毒があることは知っていても、その生態系については殆ど知らない人が多いのではないでしょうか。
全体的には子ども向けを意識した描写で書かれているため、中学生が読んでも充分楽しめますし、小学高学年でも読めるのではないでしょうか。
もちろん大人が読んでも知的好奇心を充分に満足させてくれる出来栄えです。
人気作家の百田尚樹氏が手掛けただけあってストーリーも無難にまとまっており、夏休みの読書に最適な1冊です。
ひとびとの跫音〈下〉
正岡子規の亡き後、正岡家の養子となった"忠三郎"を中心とした人びとの軌跡を描いた長編小説です。
前回も書いた通り、"忠三郎"はけっして歴史的な偉人ではありません。
それでも一見すると平凡にしか見えない人間の人生が、決して無味乾燥なものではないことを本書は教えてくれます。
例えば忠三郎は、正岡子規をけっして"利用する"ことはありませんでした。
正岡家の跡取りとして子規の残した遺品を丁寧に整理して保存することはしても、人に子規の養子であることを話すこともなく、彼の中には、父の名前を利用して一銭たりとも得ようとしない確固たる掟があり、生涯それを破ることはありませんでした。
そして忠三郎とは学生の頃からの友人で、同じく著者の知り合いであった"タカジ"がもう1人の主人公として登場します。
"タカジ"は若くして共産党に入りますが、やがて思想犯として逮捕され戦前・戦時中の12年間を刑務所で過ごすといった"忠三郎"と比べると、少し変わった経歴を持っています。
彼は生涯にわたり共産思想を捨てませんでしたが、決して著名な思想家や指導者とは言えず、戦後も地道な活動を続けた人物です。
著者の話題はこの2人のみならず、その両親や兄弟、妻、友人などにとりとめもなく広がってゆきます。
まるでこの作品全体が余談でもあるかのように、気の向くまま自由にテーマを見つけては書き綴ってゆくという表現がぴったりです。
そして唐突に2人の物語は終わりを迎えます。
"忠三郎"が7年間に渡る闘病生活の後に病没すると、そのわずか8日後に"タカジ"も後を追うように病院で息を引き取るのです。
こうして淡々と続いてきた物語が突然終わりを告げますが、読了後は案外人生もそのようなものと思えてしまうのです。
ひとびとの跫音〈上〉
数多くの歴史小説を手掛け"国民的作家"とまで評された司馬遼太郎氏の長編小説です。
主人公は正岡子規の養子となった正岡忠三郎です。
彼は子規の死後に正岡家の養子となりますが、父と違い俳人や文筆家を志すことはありませんでした。
それどころか阪急鉄道という一般企業に入社し、その生涯において歴史の残る輝かしい業績を残すこともありませんでした。
もちろん自身の代表作である「坂の上の雲」において正岡子規が主人公の1人だった経緯もありますが、忠三郎を主人公にした一番の理由は、彼が著者にとって身近な知人だったからに他なりません。
著者は小説の冒頭で次のように書いています。
私は、この会社にかつて勤めいていた忠三郎さんのことを書こうとしている。ことというのは、想い出なのか、事歴なのか、あるいは人間についてなのか、いまのところよくわからない。
そして本書を読み進んで驚くのは、歴史上の偉人を対象にするときとまったく同じ調子で、自らの知人である忠三郎さんを書いていることです。
つまり歴史上の偉人も、身近な知人も、まったく同じ距離感で小説を書いています。
それは歴史小説を通じてさまざまな人間像を描き続けてきた司馬遼太郎氏の集大成を見るかのようであり、本書はそのスタイルの完成形なのかもしれません。
溥儀―清朝最後の皇帝
歴史上はじめて"皇帝"を名乗ったのは、紀元前221年に中国統一を成し遂げた秦の始皇帝です。
それから2000年以上に及ぶ中国史で、最後に皇帝の座についたのが溥儀です。
しかも溥儀はその生涯において3度も皇帝の座に就いています。
1度目は清の皇帝として、2度めは中華民国の皇帝として、そして3度めは日本によって建国された満州国の皇帝としてです。
しかし歴代の殆どの皇帝と溥儀との間には決定的な差があります。
それは溥儀が1度も実権を手にしていないことです。
つまり溥儀自身が命令できる軍隊が存在したことはなく、そのすべてが傀儡としての皇帝という立場だったのです。
その生涯は歴史と運命に翻弄され続けた数奇な人生と表現するしかありません。
清朝末期、満州国の建国という歴史を紐解けば必ず溥儀が登場するにも関わらず、彼の連続性のある生涯を知る機会がありませんでした。
溥儀自身の手による自伝「わが半生」が著名ですが、中華人民共和国の一市民として共産党の監修&検閲の元に書かれた本であるため、歴史的な価値はあっても客観性に乏しい内容であることが容易に想像できます。
その点で著者の入江曜子氏は、19世紀末期から20世紀初頭にかけての清や満州を題材とした本を多く手掛けており、溥儀の生涯をナビゲートしてくれる人物として申し分ありません。
溥儀は多くの民衆たちの尊敬と熱狂を集めた人物であると同時に、それを利用する人間に用済みと判断されるといつ抹殺されてもおかしくない立場でもありました。
そこに溥儀という人間の歩んだ人生を複雑さを垣間見ることができます。
結果的に溥儀は確固たる信念を持つことなく、天寿をまっとうします。
ただし、それだけで彼を愚かな君主として断定することはできません。
溥儀が歴史上重要な役割を担ったことは間違いなく、20世紀に生きた彼の評価を行うには、21世紀に生きる我々にとって時期が早過ぎるのかも知れません。
日本辺境論
哲学・思想研究家である内田樹氏による1冊です。
本書は「日本人文化論」について書かれており、著者はその特性を"日本人は辺境人である"と表現していることから本書のタイトルになっています。
本書の前半では日本人が辺境人である理由を、太平洋戦争、オバマ大統領の就任演説、中国文化との交流の歴史など様々な例を取り上げて説明してゆきます。
日本は宗教、思想にとどまらず、日本語でさえも"きょろきょろ"しながら他国の標準を取り入れてきた経緯があり、日本が世界標準を作り出すことは決してないと結論付けています。
後半では日本人の特性が欠点だけではなく、優れた長所にもなり得る点を中心に論じられてゆきます。
その最たる例が日本には世界標準を作り出す能力はないが、世界標準を学ぶ能力については抜きん出ているというものです。
日本人は学びに対しては無防備に開放を行い、学ぶ対象への意味や有用性を一旦保留して、一時的に「愚鈍」になることで知的パフォーマンスを向上させることができるのです。
それは師匠や先生に対して、ほとんど何の疑念も挟まずに師事する弟子や生徒といった伝統的な構図から見て取ることができます
本書をタイトルだけで判断すると大胆で極論めいたように感じるかも知れませんが、実際に本書を読むと著者が学者(教授)であるだけに、その理論的根拠や構成の組み立ては決して飛躍したものではなく、思わず納得してしまうものばかりです。
さらに日本人を辺境人であると定義したのは著者がはじめてではなく、半世紀以上も前から優れた政治学者であり思想家でもあった丸山眞男などの知識人たちが指摘してきたことでもあり、それなりのバックボーンの上に成り立っている考えでもあるのです。
新書という分量だけに緻密で重厚といった内容ではありませんが、"技術立国"や"クールジャパン"といった表層的な事象だけでなく、もう少し日本人論を掘り下げて考えてみたい人にとっては最適な1冊ではないでしょうか。
鷹ノ羽の城
白石一郎氏が20代の頃に発表した歴史小説です。
戦国時代の肥後で白人との混血児である武将・和仁人鬼親宗の活躍を描いた作品です。
人鬼は実在した武将ですが、彼が混血児だったという記録はありません。
ただし「異様な赤ら顔で目が輝き、幼い頃から毛深く、手足が熊のような大男」という記録が残っており、当時は宣教師が九州に寄港し始めていただけに、けっして荒唐無稽な設定ではありません。
それでも著者が若かったせいか、かなり大胆な設定で書かれていると思います。
和仁家は大友家の支配下にある豪族でしたが、新興勢力の竜造寺家、さらに急激に勢力を伸ばしつつある名門・島津家といった三つ巴の争いが繰り広げられた地域であったため決して安泰な状態ではありませんでした。
子どもの頃からその日本人離れした外見によって父親からも疎まれ、山奥で忍びの一族によって育てられるというのが作品序盤のあらすじです。
やがて成人の歳となり、外見上の差別や戦国武将として過酷な運命の中で生きてゆく過程が後半部分になります。
もし主人公が普通の日本人という設定であれば、何の新鮮味もない普通の戦国小説で終わってしまいます。
世間から差別され、自らの出自に悩む武将が戦乱の世を渡ってゆく複雑な心境が克明に描かれており、混血児という設定が強烈なスパイスとなり、読者に斬新さを与えてくれます。
水神(下)
前回紹介したように、本作品作品は筑後・江南原の5人の庄屋が自費を使って水道を建設するまでを描いた歴史小説です。
大筋のストーリーは単純であるにも関わらず、上下巻にも及ぶ長編小説の形をとっています。
水路を建設するまでの経過を詳細に追っていったことも長編になった要因の1つに挙げられますが、何よりも作品全般に渡って当時の農民たちの暮らしを描くことに紙面を割いたことが大きな理由です。
江戸時代の年貢は"五公五民"と言われたように、一般的には収穫の半分を税として納めるのが一般的でした。
それでも土地が豊かであれば暮らしに困窮することはありませんでしたが、ひとたび干ばつや洪水に襲われると、農民たちの暮らしは一気に過酷なものとなりました。
減税のための嘆願は必ずしも聞き入れられるものではなく、小説の舞台となった慢性的に水不足に悩まされている地域では、農民たちが常に過酷な生活を強いられてきました。
まず白米を口にする機会はなく、粟や稗といった穀物が中心の食事が普通であり、いったん飢饉が訪れれば野草はもちろん、木の皮ですら食料になりました。
さらに口減らしのために老人や子どもが犠牲になるのも土地の痩せた地域では珍しいことではありませんでした。
農民たちは決して牛馬のように言葉を発しない存在ではなく、自然と寄り添うようにして知恵を振り絞って日々の暮らしを続けていました。
打桶に従事する庄屋の下男"元助"の視点を中心に描かれた農民たちの暮らしは、貧しくも生命力を感じさせるものであり、本当の主人公が彼ら農民たちであるのは明らかです。
まるで民俗資料を小説化したかのような本作品を農民小説と名付けてもよいかもしれません。
水神(上)
このブログではお馴染みになりつつある帚木蓬生氏の歴史小説です。
舞台は筑後にある久留米藩。
その領内にある江南原には水量豊かな筑後川が目の前を流れていますが、台地であるため水の恵みを得ることができない地形でした。
そのため常に水不足に悩み続け、そこに暮らす農民たちの暮らしは長年に渡り苦しく貧しいものでした。
そこで農民たちの苦しみを救うべく5人の庄屋が立ち上がり、筑後川に堰を設けて水道を建設する決意を固めます。
5人の庄屋(山下助左衛門、今重富平左衛門、猪山作之丞、栗林欠兵衛、本松平右衛門)たちは、この大事業を自費で受け持つことを決意し、さらに事業失敗の際には死罪をも覚悟した血判を藩へ差し出して懇願するのです。
ストーリー自体は5人の庄屋が水路を建設する決意を固め、それを実現するまでを描いた単純なものです。
にも関わらず、本作は上下巻の2冊に渡る長編小説として書かれています。
そこには著者が当時の農民たちの暮らしを詳細に描写し、読者へ伝えようとする強い意志を感じます。
物語は筑後川で朝から晩まで筑後川に大きな桶を投げ込み、水を細い溝へ流し続ける"打桶(うちおけ)"と呼ばれる仕事に従事する農民"元助"が登場するところから始まり、作品自体もこの元助の目線を中心に進められてゆきます。
元助の父親は島原の乱を鎮圧するために足軽として出兵し、鉄砲で負傷して帰らぬ人となります。
父の顔さえ知らずに育った元助は片足が不自由であり、"打桶"に一生を費やすことを宿命付けられた農民でした。
"打桶"によって多少の水が田畑へ流れますが、水不足を解消するにはあまりにも僅かな量であり、村人たちの暮らしにとっては取るに足らないものです。
日本各地に水不足を解消するための水道の建設例がありますが、著者の出身地が福岡県であることから、久留米藩を舞台にした本作は郷土の歴史を扱った作品ということになります。
描かれる四季の風景や、登場人物の方言には著者の郷土への愛着が感じられ、大作を描くといった気概が読者にも伝わり、ついつい物語の世界へ引き込まれてしまうような迫力があります。
武士の家計簿
日本の歴史や古文書の専門家である磯田道史氏が、ある日偶然に古書店から入手した"武士の家計簿"をきっかけに、その内容を解析・研究して執筆した本です。
家計簿を残したのは、金沢藩の「御算用者(ごさんようもの)」を長年勤めた猪山家です。
現在の会社であれば、"経理部"といった職務ですが、猪山家自体は下級武士の階級であり、歴史的にも殆ど無名といってよい存在でした。
しかし発見された家計簿には、饅頭1つに至るまでの詳細な帳面が36年間にも渡って記録されていたといい、手紙などの書面も一緒に保存されていました。
私たちが見ても数字が羅列されているだけの無意味な古文書にしか見えませんが、地道な調査によって内容を明らかにすることで、ある武士の一家の歴史を雄弁に語ってくれるという、まったく新しい視点で書かれています。
本書の要所には図表を使った解説が入れられおり、たとえば現在の通貨と照らし合わせた価値などが一般読者にも分かり易く書かれている点は評価できます。
日常の暮らし、結婚や出産、そして葬式といった一家に欠かすことの出来ないイベントから、藩内における出世、明治維新による幕府体制の解体といった大きな出来事が、武士の一家にどのような影響を与えたのかがノンフィクションで書かれいるといってもよいでしょう。
支配階級である武士によって運営されていた日本の諸藩は慢性的な財政赤字に苦しんでおり、当然のように藩に仕える下級武士の暮らしは決して裕福なものではありませんでした。
それでもエンゲル係数はけっして高くはなく、儀礼や行事に多くの出費が費やされていた現状が明るみになります。
武士にとって血縁の繋がりは現在よりも遥かに濃いものであり、そののために生じる"義理"は、たとえ借財してでも欠かすことが出来なかったようです。
また明治時代が到来し、文明開化の中で旧支配者階級となった"武士"たちが、新しい時代への適用に苦戦する姿までもが分かってきます。
それでも猪山家は会計といった新しい時代でも必要とされる"技能"を持っていた幸運な家系であり、家族が路頭に迷うことなく時代を乗り切ることに成功します。
2010年には映画化され話題になった作品ですが、歴史小説とは一味違う楽しみを与えてくれる1冊です。
登録:
コメント
(
Atom
)